![]()
交通事故・不法行為一般
交通事故ないし不法行為一般に関する重要裁判例(最高裁判所判決等)を実装しました。
身体損害と精神損害の訴訟物の個数(最判昭和48年4月5日民集27巻3号419頁)
ア身体傷害による財産上および精神上の損害の賠償請求における請求権および訴訟物の個数
イ不法行為による損害賠償の一部請求と過失相殺
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人中村健太郎,同中村健の上告理由第一点について。
訴外甲は,被上告人乙の運転する自動車が道路の中央線をこえて進行してくるのを約八五メートル前方に発見しながら,その動向を注視せず,漫然中央線寄りをそのまま進行したものである旨の事実を認めて,甲に本件事故発生についての過失があるものとし,他方,被上告人乙にも過失があると認めて,原判示の割合による過失相殺をした原審の認定判断は,原判決挙示の証拠関係に照らして正当として肯認することができないものではなく,右認定判断の過程に所論の違法はない。論旨は,畢竟,原審の専権に属する証拠の取捨判断及び事実の認定を非難し,さらに,原審の認定にそわない事実関係を前提にして右過失に関する原審の判断の違法をいうものであって,採用できない。
同第二点について。
記録によれば,本件の経過は,次のとおりである。すなわち,
被上告人乙は,第一審において,療養費二九万六二六六円も逸失利益一一二八万三六五一円,慰藉料二〇〇万円の各損害の発生を主張し,療養費,慰藉料の各全額と逸失利益の内金一五〇万円との支払を求めるものであるとして,合計三七九万六二六六円の支払を請求したところ,第一審判決は,療養費,慰藉料については右主張の全額,逸失利益については九一六万〇六一四円の各損害の発生を認定し,合計一一四五万六八八〇円につき過失相殺により三割を減じ,さらに支払済の保険金一〇万円を差し引いて,上告人の支払うべき債務総額を七九一万九八一六円と認め,その金額の範囲内である同被上告人の請求の全額を認定した。上告人の控訴に対し,原審において,被上告人乙は,第一審判決の右認定のとおり,逸失利益の額を九一六万〇六一四円,損害額の総計を一一四五万六八八〇円と主張をあらためたうえ,みずから過失相殺として三割を減じて,上告人の賠償すべき額を八〇一万九八一六円と主張し,附帯控訴により請求を拡張して,第一審の認容額との差額四二二万三五五〇円の支払を新たに請求した(弁護士費用の賠償請求を除く。以下同じ。)ところ,これに対し,上告人は右請求拡張部分につき消滅時効の抗弁を提出した。原判決は,療養費および逸失利益の損害額を右主張のとおり認定したうえ,その合計九四五万六八八〇円から過失相殺により七割を減じた二八三万七〇六四円について上告人が支払の責を負うべきものであるとし,また,慰藉料の額は被上告人乙の過失をも斟酌したうえ七〇万円を相当とするとし,支払済の保険金一〇万円を控除して,結局上告人の支払うべき債務総額を三四三万七〇六四円と認め,第一審判決を変更して,右金額の支払を命じ,その余の請求を棄却し,さらに,附帯控訴にかかる請求拡張部分は,右損害額をこえるものであるから,右消滅時効の抗弁について判断するまでもなく失当であるとして,その部分の請求を全部棄却したものである。
右の経過において,第一審判決がその認定した損害の各項目につき同一の割合で過失相殺をしたものだとすると,その認定額のうち慰藉料を除き財産上の損害(療養費および逸失利益。以下同じ。)の部分は,(保険金をいずれから差し引いたかはしばらく措くとして。)少なくとも二三九万六二六六円であって,被上告人Bの当初の請求中財産上の損害として示された金額をこえるものであり,また,原判決が認容した金額のうち財産上の損害に関する部分は,少なくとも(保険金について右と同じ。)二七三万七〇六四円であって,右のいずれの額をもこえていることが明らかである。しかし,本件のような同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする財産上の損害と精神上の損害とは,原因事実および被侵害利益を共通にするものであるから,その賠償の請求権は一個であり,その両者の賠償を訴訟上あわせて請求する場合にも,訴訟物は一個であると解すべきである。したがって,第一審判決は,被上告人乙の一個の請求のうちでその求める全額を認容したものであって,同被上告人の申し立てない事項について判決をしたものではなく,また,原判決も,右請求のうち,第一審判決の審判および上告人の控訴の対象となった範囲内において,その一部を認容したものというべきである。そして,原審における請求拡張部分に対して主張された消滅時効の抗弁については,判断を要しなかったことも,明らかである。
次に,一個の損害賠償請求権のうちの一部が訴訟上請求されている場合に,過失相殺をするにあたっては,損害の全額から過失割合による減額をし,その残額が請求額をこえないときは右残額を認容し,残額が請求額をこえるときは請求の全額を認容することができるものと解すべきである。このように解することが一部請求をする当事者の通常の意思にもそうものというべきであって,所論のように,請求額を基礎とし,これから過失割合による減額をした残額のみを認容すべきものと解するのは,相当でない。したがって,右と同趣旨において前示のような過失相殺をし,被上告人乙の第一審における請求の範囲内において前示金額の請求を認容した原審の判断は,正当として是認できる。
以上の点に関する原審の判断の過程に所論の違法はなく,論旨は採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官下田武三 裁判官大隅健一郎,同藤林益三,同岸 盛一,同岸上康夫
一部請求の既判力(最判昭和37年8月10日民集16巻8号1720頁)
一個の債権の数量的な一部請求についての判決の既判力
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人信正義雄の上告理由について。
一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合は,訴訟物となるのは右債権の一部の存否のみであって,全部の存否ではなく,従って右一部の請求についての確定判決の既判力は残部の請求に及ばないと解するのが相当である。
右と同趣旨の原判決の判断は正当であって,所論は採用するをえない。よって,民訴四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官池田克,裁判官河村大助,同奥野健一,同山田作之助
一時金請求に対する定期金支払の可否(最判昭和62年2月6日裁判集民事150号75頁)
一,公立学校における教師の教育活動と国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」
二,損害賠償請求権者が一時金による支払を訴求している場合と定期金による支払を命ずる判決の許否
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
一 上告代理人猪狩庸祐の上告理由第一及び上告代理人小川善吉,同瀬沼忠夫の上告理由第四点一,二について
国家賠償法一条一項にいう「公権力の行使」には,公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解するのが相当であり,これと同旨の原審の判断は,正当として是認できる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用できない。
二 上告代理人堀家嘉郎の上告理由第二点,上告代理人猪狩庸祐の上告理由第二並びに上告代理人小川善吉,同瀬沼忠夫の上告理由第一点,第二点及び第四点三,四について
学校の教師は,学校における教育活動により生ずるおそれのある危険から生徒を保護すべき義務を負っており,危険を伴う技術を指導する場合には,事故の発生を防止するために十分な措置を講じるべき注意義務があることはいうまでもない。本件についてこれをみるに,所論の点に関する原審の事実認定は,原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができ,右の事実関係によれば,松浦教諭は,中学校三年生の体育の授業として,プールにおいて飛び込みの指導をしていた際,スタート台上に静止した状態で頭から飛び込む方法の練習では,水中深く入ってしまう者,空中での姿勢が整わない者など未熟な生徒が多く,その原因は足のけりが弱いことにあると判断し,次の段階として,生徒に対し,二,三歩助走をしてスタート台脇のプールの縁から飛び込む方法を一,二回させたのち,更に二,三歩助走をしてスタート台に上がってから飛び込む方法を指導したものであり,被上告人今野良彦は,右指導に従い最後の方法を練習中にプールの底に頭部を激突させる事故に遭遇したものであるところ,助走して飛び込む方法,ことに助走してスタート台に上がってから行う方法は,踏み切りに際してのタイミングの取り方及び踏み切る位置の設定が難しく,踏み切る角度を誤った場合には,極端に高く上がって身体の平衡を失い,空中での身体の制御が不可能となり,水中深く進入しやすくなるのであって,このことは,飛び込みの指導にあたる松浦教諭にとって十分予見しうるところであったというのであるから,スタート台上に静止した状態で飛び込む方法についてさえ未熟な者の多い生徒に対して右の飛び込み方法をさせることは,極めて危険であるから,原判示のような措置,配慮をすべきであったのに,それをしなかった点において,松浦教諭には注意義務違反があった。もっとも,同教諭は,生徒に対して,自信のない者はスタート台を使う必要はない旨を告げているが,生徒が新しい技術を習得する過程にある中学校三年生であり,右の飛び込み方法に伴う危険性を十分理解していたとは考えられないので,右のように告げたからといって,注意義務を尽くしたことにはならない。従って,右と同旨に帰する原審の判断は,正当として是認できる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用できない。
三 上告代理人堀家嘉郎の上告理由第一点一について
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて,原審の付添看護費用に関する損害額の算定方法は,正当として是認できる。また,損害賠償請求権者が訴訟上一時金による賠償の支払を求める旨の申立をしている場合に,定期金による支払を命ずる判決をすることはできないものと解するのが相当であるから,定期金による支払を命じなかった原判決は正当である。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用できない。
四 その余の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は,原判決挙示の証拠関係に照らし,正当として是認することができ,その過程に所論の違法はない。論旨は,畢竟,原審の専権に属する事実の認定を非難するか,又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず,採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官林 藤之輔 裁判官牧 圭次,同島谷六郎,同藤島 昭,同香川保一)
一定金額をこえる債務の不存在確認請求の訴訟物(最判昭和40年9月17日民集19巻6号1533頁)
一定金額をこえる債務の不存在確認請求の訴訟物
主 文
原判決を破棄し,本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人中谷鉄也の上告理由第一点について。
所論の点についての原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の認定した事実は,その挙示の証拠関係によって,これを肯認しうる。
原判決には,所論のような違法はなく,所論は,結局,原審の専権に属する証拠の取捨・選択,事実の認定を非難するに帰し,採用しがたい。
同第二点について。
論旨は,利息制限法所定の制限をこえる利息,損害金は,債務者が任意に支払ったときでも,右制限をこえる部分は貸金元本に充当さるべきにもかかわらず,これを否定した原判決は法令の解釈をあやまり,右違法は上告人らの債務不存在確認訴訟の判決に影響を及ぼすことは明らかであるという。
よって,案ずるに,原判決の事実摘示によると,上告人らの被上告人に対する請求の趣旨として,「上告人甲の被上告人に対する債務の残存元本は金一四万六,四六五円を超えて存在しないことを確認する。その余の上告人らの被上告人に対する債務の不存在を確認する」の記載があり,その請求の原因の要旨としては,(1)訴外乙は昭和三二年四月二三日被上告人から金一一〇万円を弁済期同三三年三月末日などの約で借り受けたが,同訴外人は,同年九月三日死亡し,上告人ら一一名が相続し,右債務を承継したが,上告人甲において単独で右全債務を引き受けることとし,被上告人も,これを承諾し,その余の上告人らに対する債務わ免除した。(2)そして,上告人甲は,右貸金債務に対し(イ)同三二年一二月二四日金八三万三,五三五円を,(ロ)同三三年四月七日金五万円を,(ハ)同年一二月二八日金七万円を,それぞれ弁済したから,右貸金債務の残元金は金一四万六,四六五円になった。(3)よって,上告人らは請求の趣旨記載の判決を求める。というにある。
上告人らの右請求に対し,原判決は,上告人甲において本件貸金の元本債権に弁済したと主張する(イ)同三二年一二月の金八三万三,五三五円の支払について,その内金五〇万円のみが右元本債権に弁済されたが,その余の三三万三,五三五円は本件貸金債権の利息などに弁済されたにすぎず,かりに,(ロ)同三三年四月の金五万円,(ハ)同年一二月の金七万円の弁済が上告人ら主張のとおり本件貸金債権の元本債権に弁済されたとしても,本件貸金の残金元本債権が上告人甲において自認する金一四万六,四五六円をこえることは明らかであり,しかも,上告人らが主張する債務引受の事実は認めがたい旨判示して,上告人らの本所請求を全部排斥していることが認められる。
しかし,本件請求の趣旨及び請求の原因ならびに本件一件記録によると,上告人らが本件訴訟において本件貸金債務について不存在の確認を求めている申立の範囲(訴訟)は,上告人甲については,その元金として残存することを自認する金一四万六四六五円を本件貸代金債権金一一〇万から控除した残額九五万三,五三五円の債務額の不存在の確認であり,その余の上告人らにおいては,右残額金九五万三五三五円の債務額について相続分に応じて分割われたそれぞれの債務額の不存在の確認であると認られる。
従って,原審としては,右の各請求の当否をきめるためには,単に,前記(イ)の弁済の主張事実の存否のみならず,(ロ)および(ハ)の弁済の各主張事実について審理をして本件申立の範囲(訴訟)である前記貸金残額の存否ないしその限度を明確に判断しなければならないのに,ただ単に,前記(イ)の弁済の主張事実が全部認められない以上,本件貸金の残債務として金一四万六,四六五円以上存在することが明らかである旨説示したのめで,前記(ロ)および(ハ)の弁済の主張事実について判断を加えることなく,残存額の不存在の限度を明確にしなかったことは,上告人らの本件訴訟の申立の範囲(訴訟物)についての解釈をあやまり,ひいては審理不尽の違法をおかしたものというべく,論旨は,結局,理由あるに帰する(なお,債務者が利息制限法所定の制限こえる金銭貸借上の利息,損害を任意に支払ったときのは,右制限をこえる部分は,元本債権に充当されるものと解すべきことは,当裁判所大法廷判決昭和三九年一一月一八日(民集一八巻九号一八六八頁)の説示するところである。)
よって,民訴法四〇七条に基づき原判決を破棄し,原審をして右の点についてさらに審理を尽くさせるため,本件を大阪高等裁判所に差し戻し,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官奥野健一,裁判官山田作之助,同草鹿浅之介,同石田和外
同一事故の損害賠償間の相殺の可否(最判昭和49年6月28日民集28巻5号666頁)
同一交通事故によって生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間における相殺の許否
主 文
原判決中上告人甲敗訴部分のうち五万八一〇四円及びこれに対する昭和四五年六月一日以降完済まで年五分の割合による金員の請求を棄却した部分を破棄する。
右破棄部分に関する被上告人らの各控訴を棄却する。
上告人甲のその余の上告を棄却する。
上告人乙,上告人丙及び上告人丁の各上告を棄却する。
前項の部分に関する上告費用は上告人乙,上告人丙及び上告人丁の負担とし,上告人甲と被上告人らとの間に生じた訴訟費用は一・二・三審を通じてこれを二分し,その一を上告人甲の,その余を被上告人らの各負担とする。
理 由
上告代理人荒井尚男,同浜田正義の上告理由第一点について。
所論の点に関する原審の認定判断は,原判決の挙示する証拠とその説示に照らし,正当として是認することができ,その過程に所論の違法は認められない。論旨は,採用できない。
同第二点について。
原判決は,昭和四三年九月二九日午後一〇時ころ長岡市甲丁目の交差点において,被上告会社の被用者たる被上告人戊の運転するQ車(マイクロバス)が,上告人乙の運転する,同甲所有のP車(普通乗用車)と衝突し,その結果P車,Q車ともに破損するという本件事故が発生したこと,本件事故は,被上告人戊が被上告会社の業務であるQ車を陸送中その過失が主たる原因となって発生したものであるが,P車を運転していた上告人乙の過失もその一因となっていたこと,本件事故によりP車の所有者であった同甲は,P車の代車購入費二五万円及びP車の使用不能による喪失利益九万一〇〇〇円以上合計三四万一〇〇〇円の損害を被ったが,同乙に右過失があり,同人の過失はいわゆる被害者側の過失として同甲の被った損害額の算定について斟酌すれば,その損害額は二七万二八〇〇円となり,同人は被上告人らに対し同額の損害賠償請求権を有すること,一方,本件事故により被上告会社はQ車の修理代金二九万〇五二〇円相当の損害を被ったが,これは上告人甲の被用者の立場にある同乙が同甲の事業の一環としてP車を運転中,その過失によって惹起したものであるから,同人は同乙の使用者として被上告会社が本件事故により被った損害を賠償する義務があること,しかし,被上告会社の被用者たる被上告人戊に前記のような過失があり,同人の過失を被上告会社の被った損害額の算定について斟酌すれば,その損害額は五万八一〇四円となり,被上告会社は上告人甲に対し同額の損害賠償債権を有すること,をそれぞれ認定したうえ,本件のように双方の債権が双方の過失による一個の衝突事故によって生じた物損に基づく損害賠償債権である場合には,民法五〇九条の適用がなく,損害賠償債権を受働債権とする相殺が許されるから,上告人甲の二七万二八〇〇円の損害賠償債権は五万八一〇四円の限度において相殺により消滅したと判示し,被上告会社の相殺の抗弁を是認しているのである。
しかしながら,民法五〇九条の趣旨は,不法行為の被害者に現実の弁済によって損害の填補を受けさせること等にあるから,およそ不法行為による損害賠償債務を負担している者は,被害者に対する不法行為による損害賠償債権を有している場合であっても,被害者に対しその債権をもって対当額につき相殺により右債務を免れることは許されないものと解するのが,相当である(最高裁昭和三〇年(オ)第一九九号同三二年四月三〇日第三小法廷判決・民集一一巻四号六四六頁参照。)。したがって,本件のように双方の被用者の過失に基因する同一交通事故によって生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間においても,民法五〇九条の規定により相殺が許されないというべきである。
それ故,原判決の前記判断には,民法五〇九条の解釈,適用を誤った違法があるものというべく,この点の論旨は理由があり,原判決中被上告会社の相殺の抗弁を是認し上告人甲の請求の一部を棄却した部分は,破棄を免れない。
本件において,原判決の確定したところによれば,上告人甲は被上告人各自に対し二七万二八〇〇円の損害賠償請求権を有することは明らかであるから,上告人甲の本訴請求は二七万二八〇〇円とこれに対する昭和四五年六月一日以降完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容すべきである。
次に,原判決中,上告人甲のその余の上告並びに上告人乙,同丙及び同丁の各上告は,上告理由第一点につき判示したとおり理由がないから,棄却すべきものとする。
よって,民訴法四〇八条,三九六条,三八四条,九六条,九五条,九二条,八九条,九三条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官江里口清雄 裁判官関根小郷,同天野武一,同坂本吉勝,同高辻正己
弁護士費用の賠償債務の履行遅滞時期(最判昭和58年9月6日民集37巻7号901頁)
弁護士費用の賠償債務が履行遅滞となる時期
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人田中登の上告理由一について
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては,上告人は本件事故当時において本件自動車につき運行支配及び運行利益を有していたものというべきであるから,上告人に本件事故に関する運行供用者責任があるとした原審の判断は,結論において正当として是認することができ,原判決に所論の違法はない。論旨は,採用することができない。
同二について
不法行為の被害者が自己の権利擁護のため訴えを提起することを余儀なくされ,訴訟追行を弁護士に委任した場合には,その弁護士費用は,事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り,右不法行為と相当因果関係に立つ損害であり,被害者が加害者に対しその賠償を求めることができると解すべきことは,当裁判所の判例(最高裁昭和四一年(オ)第二八〇号同四四年二月二七日第一小法廷判決・民集二三巻二号四四一頁)とするところである。しかして,不法行為に基づく損害賠償債務は,なんらの催告を要することなく,損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきところ(最高裁昭和三四年(オ)第一一七号同三七年九月四日第三小法廷判決・民集一六巻九号一八三四頁参照),弁護士費用に関する前記損害は,被害者が当該不法行為に基づくその余の費目の損害の賠償を求めるについて弁護士に訴訟の追行を委任し,かつ,相手方に対して勝訴した場合に限って,弁護士費用の全部又は一部が損害と認められるという性質のものであるが,その余の費目の損害と同一の不法行為による身体傷害など同一利益の侵害に基づいて生じたものである場合には一個の損害賠償債務の一部を構成するものというべきであるから(最高裁昭和四三年(オ)第九四三号同四八年四月五日第一小法廷判決・民集二七巻三号四一九頁参照),右弁護士費用につき不法行為の加害者が負担すべき損害賠償債務も,当該不法行為の時に発生し,かつ,遅滞に陥るものと解するのが相当である。なお,右損害の額については,被害者が弁護士費用につき不法行為時からその支払時までの間に生ずることのありうべき中間利息を不当に利得することのないように算定すべきものであることは,いうまでもない。
本件についてこれをみると,記録及び原判文に照らせば,原審が,被上告人の本件訴訟追行のための弁護士費用につき本件事故と相当因果関係のある損害を八万円と認めるにあたって,被上告人が右事故時から当該弁護士費用の支払時までの中間利息を不当に利得することのないように算定したことが窺いえないものではないから,上告人が所論の弁護士費用に係る損害八万円について本件事故後である昭和五二年七月一九日から完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払義務を負うとした原審の判断は,是認するに足り,原判決に所論の違法はない。論旨は,採用することができない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官安岡滿彦,裁判官横井大三,同伊藤正己,同木戸口久治
不法行為と民法416条2項<特別損害>の類推(最判昭和48年6月7日民集27巻6号681頁)
不法行為による損害賠償と民法416条2項
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人松田道夫,同松田節子の上告理由第一点について。
不法行為による損害賠償についても,民法四一六条が類推適用され,特別の事情によって生じた損害については,加害者において,右事情を予見しまたは予見することを得べかりしときにかぎり,これを賠償する責を負うものと解すべきであることは,判例の趣旨とするところであり(大審院大正一二年(オ)第三九八号・第五二一号同一五年五月二二日判決民集五巻三八六頁,最高裁昭和二八年(オ)第八四九号同三二年一月三一日第一小法廷判決民集一一巻一号一七〇頁,同昭和三七年(オ)第四四四号同三九年六月二三日第三小法廷判決民集一八巻五号八四二頁参照),今直ちにこれを変更する要をみない。本件において,上告人の主張する財産上および精神上の損害は,すべて,被上告人の本件仮処分の執行によって通常生ずべき損害にあたらず,特別の事情によって生じたものと解すべきであり,そして,被上告人において,本件仮処分の申請およびその執行の当時,右事情の存在を予見しまたは予見することを得べかりし状況にあったものとは認められないとした原審の認定判断は,原判決(その引用する第一審判決を含む。)挙示の証拠関係に照らして,正当として肯認することができる。したがって,原審の認定判断に所論の違法はなく,論旨は採用できない。
同第二点について。
本件仮処分の被保全権利の不存在が,本案訴訟において確定されていないとしても,原審における上告人主張のように,被上告人が起訴命令を受けながら本案訴訟を提起せず,かえってみずから仮処分の執行取消申請をしたという事実があるとすれば,本件仮処分は被保全権利を欠く違法なものであったと推認するのが相当である。しかし,上告人主張の損害が被上告人において予見せずかつ予見することのできない特別の事情によって生じたものであって,被上告人がその賠償の責に任じないものであるとした原審の判断を是認することができることは,前述のとおりであるから,被保全権利の存否に関する原審の認定判断の当否は,上告人の請求を棄却すべきものとした結論に影響を及ぼすものではない。したがって,論旨は採用することができない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官大隅健一郎の反対意見があるほか裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
<裁判官大隅健一郎の反対意見は略>
最高裁裁判長裁判官藤林益三,裁判官大隅健一郎,同下田武三,同岸 盛一,同岸上康夫
国道管理の瑕疵による通行人死亡(最判昭和37年9月4日民集16巻9号1834頁)
通行人死亡が国道管理の瑕疵のため生じたものと認められた事例
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人工藤日出男の上告理由第一,二点について。
原審が,本訴請求について控訴人(上告人)に対し第一審判決よりも不利益な判決をしたことは明らかであり,控訴審は,当事者の一方から控訴の申立があった場合には,相手方から附帯控訴の申立がないかぎり,控訴人に対し,第一審判決よりも不利益な判決をしえないことは,所論のとおりである。
しかし,記録によれば,被控訴人ら代理人は原審に昭和三三年一〇月二七日付「被控訴人の準備書面」と題する書面を提出し,右書面には請求の趣旨として「控訴人は被控訴人甲に対し金二〇万円,他の被控訴人に対しそれぞれ金一〇万円ならびにこれに対する昭和三一年一月二二日から完済まで年五分の割合の金員をも併せ文払せよ」との記載があり右準備書面は昭和三三年一〇月三〇日の原審第三回口頭弁論期日に陳述されており,右書面はその内容上,附帯控訴及び請求の拡張の申立書と解するのが相当である。してみれば,右の拡張された申立の範囲内で被控訴人らの請求を認容した原判決には所論の違法はない。論旨は理由がない。
同第三点について。
原審が,控訴人大分県は本件国道管理の瑕疵に基づき発生した本件事故の損害を賠償する責に任じなければならないとし,なお,控訴人の過失相殺の主張は採用できないとした判断は,挙示の証拠関係に照らし相当である。慰謝料額の算定に被害者の過失をしんしやくするかどうかについては,前示の如くすでに被控訴人らから附帯控訴の申立があった以上,原審が第一審判決に覊束されるいわれはない。所論は,畢竟,原審の裁量に任された事項についての判断を非難するにすぎず,採用できない。
同第四点について。
本件は,被上告人らが上告人の不法行為により被った損害の賠償債務の履行及びこの債務の履行遅滞による損害金として昭和三一年一月二二日以降年五分の割合による金員の支払を求める訴訟であることが記録上明らかである。そして,右賠償債務は,損害の発生と同時に,なんらの催告を要することなく,遅滞に陥るものと解するのが相当である。従って,これと同趣旨に出でた原判決は正当であるから,所論違憲の主張は前提を欠き,その他の論旨は,右と異る見解に立って原判決を攻撃するにすぎず,論旨はすべて採用できない。
よって,民訴四〇一条,九五粂,八九条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官垂水克己,裁判官河村又介,同石坂修一,同五鬼上堅磐,同横田正俊
交差点直進車における予見義務(最判平成3年11月19日裁判集民事163号487頁)
交差点を直進予定の自動車運転者に,交差点内における右折予定の停止車両の後続車がその側方を通過して右折することまでの予見義務がないとされた事例
上告代理人河田英正の上告理由第二の四について
一 原審の適法に確定した事実関係は,次のとおりである。
1 上告人は,昭和六一年一月七日午後七時一二分ころ,普通貨物自動車(以下「上告人車」という。)を運転し,岡山県玉野市宇野二丁目一七番二六号先道路を西方から東方に向かって直進し,本件交差点手前に差し掛かったが,対面信号が青色であること及び本件交差点を一台の自動車が東方から北方へ右折したものの,後続の郵便車が右折のため本件交差点内で停止し,上告人車の通過を待機する態勢にあることを確認し,本件交差点を安全に通過できるものと考えてそのまま進行した。
2 被上告人らの子である亡Xは,右の日時ころ,原動機付自転車を運転して,右道路を東方から西方に向かって進行し,右折するため青色信号に従って本件交差点内に進入し,上告人車の通過を待っために停止中の郵便車の左横を通過し,直進車の有無,状況の確認を怠り右折進行を続けたところ,折からの降雨によりぬれていた路面を横滑りするような状態で上告人車の右側ドア外側下部付近及び後部車輪を支えるバネ付近に接触,転倒し,脳挫傷等の傷害を負い,同日午後一一時五分に死亡した。
二 原審は,右の事実関係の下において,郵便車が右折するため直進車の通過を待ち一時停止の態勢にあったとしても,郵便車の物陰になって見通しのできないところから郵便車を追い越して右折する車両があることも十分に予測されるところであるから,上告人には,郵便車ばかりでなくその後続車の動静に注意し,前方の安全を確認して本件交差点内を通行すべき注意義務があるのに,これを怠った過失があると判断して,被上告人らからの上告人に対する本件各損害賠償請求を一部認容した。
三 しかし,原審の右判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
道路交通法三七条は,交差点で右折する車両等は,当該交差点において直進しようとする車両等の進行妨害をしてはならない旨を規定しており,車両の運転者は,他の車両の運転者も右規定の趣旨に従って行動するものと想定して自車を運転するのが通常であるから,右折しようとする車両が交差点内で停止している場合に,当該右折車の後続車の運転者が右停止車両の側方から前方に出て右折進行を続けるという違法かつ危険な運転行為をすることなど車両の運転者にとって通常予想することができないところである。前記事実関係によれば,上告人は,青色信号に従って交差点を直進しようとしたのであり,右折車である郵便車が交差点内に停止して上告人車の通過を待っていたというのであるから,上告人には,他に特別の事情のない限り,郵便車の後続車がその側方を通過して自車の進路前方に進入して来ることまでも予想して,そのような後続車の有無,動静に注意して交差点を進行すべき注意義務はなかったものといわなければならない。そして,前記確定事実によれば,本件においては,何ら右特別の事情の存在することをうかがわせるものはないのであるから,上告人には本件事故について過失はないものというべきである。
そうすると,上告人に過失があるとした原審の判断は,運転者の注意義務についての法令の解釈を誤ったものであり,この違法が原判決に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理由があり,他の上告理由について判断するまでもなく原判決中上告人の敗訴部分は破棄を免れない。そして,右に説示したところによれば,被上告人らの請求は理由がないことに帰し,これと結論を同じくする第一審判決は正当であるから,右部分に対する被上告人らの控訴は理由がなくこれを棄却すべきものである。
よって,民訴法四〇八条,三九六条,三八四条,九六条,八九条,九三条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官佐藤庄市郎,裁判官坂上壽夫,同貞家克己,同園部逸夫,同可部恒雄
交差点で追抜態勢中の運転手の並進車に対する注意義務(最判昭和43年9月24日裁判集民事92号369頁)
交差点で追抜態勢にある自動車運転手の並進車に対する注意義務
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人桜川玄陽の上告理由第一点について。
上告人は昭和四〇年九月二〇日午後五時五〇分頃第二種原動機付二輪車(上告車)を運転して名古屋市中川区中京通を時速三〇㎞で南進し,同通二丁目七四番地先にさしかかったところ,東の方から東西に通ずる道路を西進して中京通へ出てきた一台の乗用車が上告人の前方約一五米地点で一時停車したので,それをかわすため,別段の合図もせず,ハンドルを右に切り,抛物線状に中京通の中央近くへ出て前進しようとしたが,その際上告人の背後方向から南に向って時速約四五㎞で進行してきた被上告人四郎運転の軽四輪貨物自動車(被上告車)の左側後部に自己の車の前部フォーク右側を接触させて転倒した旨の原審の認定は,原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。そして,右接触の前において,被上告車が上告車と並行する同一方向の進路を先行する乗用車に続いて直進していたことは原判文自体からうかがえるところであるから,上告人は前記一台の乗用車が中京通に進入しようとして一時停車しているのに注意を奪われ,右方および後方の安全を確認することなく,別段の合図もせず,ハンドルを右に切ったため,折しも後方から先行する乗用車に続いて上告車の右側を走行していわゆる追抜態勢にはいっていた被上告車に上告車の車体を接触させたものといわなければならない。ところで,このように既に先行車に続いて追抜態勢にある車は,特別の事情のないかぎり,並進する車が交通法規に違反して進路を変えて突然自車の進路に近寄ってくることまでも予想して,それによって生ずる事故の発生を未然に防止するため徐行その他避譲措置をとるべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当である。したがって,本件事故はいつに上告人の過失によって生じたもので,被上告人四郎の過失によって生じたものではないといわなければならない。これと同一結論をとる原判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。
同第二点について。
被上告人甲は同乙の父親で,同乙から前記自動車を借り受けて自己の営業に常時使用していたもので,同英司は右自動車の運行自体について直接の支配力を及ぼしえない関係にあったものである旨の原審の認定は,原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。
ところで,自賠法三条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは,自動車の使用についての支配権を有し,かつ,その使用により享受する利益が自己に帰属する者を意味するから,被上告人乙は右にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」にあたらないものといわなければならず,この点に関する原審の判断は相当である。所論は独自の見解を述べるものであり,論旨は採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁判所裁判長裁判官横田正俊 裁判官田中二郎,同下村三郎,同松本正雄,同飯村義美
非接触事故と因果関係(最判昭和47年5月30日民集26巻4号939頁)
加害車両が被害者の歩行者に接触なくても歩行者の受傷との間に相当因果関係があるとされた事例
主 文
原判決を破棄し,本件を仙台高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人鈴木直二郎,同鈴木欽也の上告理由について。
一,原審は,上告人の本件傷害は被上告人の運転していた本件軽二輪車(総排気量二五〇立方cm,以下単に軽二輪車という。)が上告人に衝突したことによって生じた旨の上告人の主張に対し,上告人の転倒位置と軽二輪車の停車位置とは離れすぎており,上告人に軽二輪車が衝突した傷跡はなく,同人の受傷はひとりで転倒しても起る等の事情から,軽二輪車が上告人に衝突したものとは認め難いとして,右主張を排斥したうえ,上告人の本訴請求を棄却している。
なるほど,原審の取り調べた証拠によれば,被上告人の運転していた軽二輪車が上告人に衝突したものとは認め難いとする原審の右認定判断は,これを肯認しえないものではない。
二,ところで,不法行為において,車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係があるとされる場合は,車両が被害者に直接接触したり,または車両が衝突した物体等がさらに被害者に接触したりするときが普通であるが,これに限られるものではなく,このような接触がないときであっても,車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであって,歩行者がこれによって危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど,衝突にも比すべき事態によって傷害が生じた場合には,その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認めるのが相当である。
本件についてこれをみるに,原審の認定した事実によれば,上告人は,訴外甲,同乙外二名と連れ立って,暗夜の市道(幅員約三メートル,非舗装)を歩行中,前方からは被上告人が運転する軽二輪車が,後方からは訴外丙が運転する原動機付自転車が,それぞれ,接近して来るのを認めたため,右原動機付自転車の方を振り返りながら,右甲乙両名に続いて,前方右側の道路端にある仮橋のたもとに避難したところ,前方から右軽二輪車が運転を誤り,上告人がまさに避けようとしている仮橋上に向って突進して来て仮橋に乗り上げたうえ後退して停車し,その際運転者である被上告人の肩が右乙に触れて同人を転倒させ,他方上告人は右仮橋の西北端付近で転倒し,原判示の傷害を受けたというのである。右事実関係のもとにおいては,上告人は,同人の予測に反し,右軽二輪車が突進して来たため,驚きのあまり危難を避けるべき方法を見失い,もし,現場の足場が悪かったとすれば,これも加わって,その場に転倒したとみる余地もないわけではない。そうだとすれば,上告人の右受傷は,被上告人の軽二輪車の運行によって生じたものというべきである。
三,上告人の原審における前掲主張の趣旨は,このような態様による被上告人の不法行為責任の追及をも含むものと解されるから,軽二輪車が上告人に直接衝突した事実が認められないとの理由のみから,本件について被上告人になんらの責任もないとした原審の判断は,民法七〇九条の解釈適用を誤り,ひいて審理不尽の違法を犯したものである。論旨はこの点において理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,本件については,さらに被上告人の責任について審理を尽くす必要があるから,これを原審に差し戻すのが相当である。
よって,民訴法四〇七条を適用して,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官関根小郷,裁判官田中二郎,同下村三郎,同天野武一,同坂本吉勝
自殺との因果関係(最判平成5年9月9日裁判集民事169号603頁)
交通事故と被害者の自殺との間に相当因果関係があるとされた事例
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告補助参加人代理人高崎尚志の上告理由について
一 本件は,交通事故により受傷した被害者がその後自殺し,被害者の相続人らが,加害車の運転者及び加害車を運行の用に供していた者に対し,死亡による損害を含む損害の賠償を請求するものである。
二 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
1 X(昭和一五年九月生)は,昭和五九年七月二八日午後一時四〇分ころ,静岡県賀茂郡東伊豆町の国道一三五号線を普通乗用自動車を運転して走行中,前方不注視の過失により反対車線から中央線を越えて進入してきた上告人青木の運転に係る普通乗用自動車に衝突され,頭部打撲,右額部両膝部打撲擦過傷,左膝蓋骨骨折・右肩右眼囲打撲皮下出血,腹部打撲,右上膊部打撲,頸部捻挫の傷害を受け,被害車に同乗していたXの妻である被上告人Y及び子である被上告人Zも負傷した(以下,この交通事故を「本件事故」という。)。上告人甲は,本件事故当時加害車を運行の用に供していた者である。
2 Xは,静岡県賀茂郡東伊豆町の医院に昭和五九年七月から同年八月まで入院して,1記載の傷害につき頸部牽引等の治療や頸椎用軟性コルセット着用等の措置を受け,同日東京都足立区西新井の病院に転院し,同日から同年九月八日まで入院し,翌九日から通院して治療を受けたところ,昭和六〇年四月一二日には首の動きも正常に戻るなど身体の運動機能は順調に回復し,同六一年一〇月八日に症状固定の診断がされ,頭痛,頭重,項部痛,めまい,眼精疲労などの後遺症は,自賠法施行令二条別表等級第一四級一〇号と認定された。
3 Xは,本件事故前には,精神的疾患もなく,通常の社会生活を送っていたが,本件事故後は口数が減り,次第に家庭生活においても明るさを失い,2記載の病院における治療期間中,医師に対し,頭痛,めまい,眼精疲労などの愁訴を繰り返し,本件事故の態様についてしばしば口にし,医師による就労の勧めをもかたくなに拒絶した。
4 自らに責任のない事故で傷害を受けた者は,自らにも責任のある事故で傷害を受けた者に比較して,加害者によって完全に被害を回復されたいとの欲求が強くなり,また事故時の精神的衝撃が長い年月にわたって残りがちであり,性格傾向や生活上の他の要因等と相まって災害神経症状態に陥りやすい。本件事故の態様が上告人青木の一方的過失によるものであり,しかも家族連れでの行楽途中の開放的心理状態の下で突然遭遇したものであるなど,Xに大きな精神的衝撃を与えるものであったこと,補償交渉が納得のいく進展をみていなかったこと,意思に反する就労の勧めがされたことなどに起因して,Xは,昭和六一年三月ころには災害神経症状態となって勤労意欲が減退していた。Xは,同年五月ころから,勤務先であるN工業株式会社の人事担当者から復職のめどを打診されるとともに,従前勤務していたK工場の閉鎖移転に伴い,群馬工場に配転になることを告げられ,同年六月末ころ,復職願を提出したものの,同会社からこれを受け入れられなかったため,K工場の移転に伴う退職金優遇制度があることや復職しても転居等の生活上の負担が避けられないことなどを勘案した結果,同年九月三〇日付けで退職した。
5 右のように災害神経症状態に陥ると,その状態から抜け出せないままうつ病に発展しやすいものであるところ,Xは,退職後も再就職が思うに任せなかったことや,本件事故により同様に負傷した被上告人Yらとの家庭生活が以前に比較して暗くなったことなどの原因が重なってうつ病になり,精神科医による治療を受けることもなく悶々とした生活を続け,昭和六三年二月ころには被上告人Yに不眠・食欲不振等を訴えていたが,同月一〇日,自殺した。うつ病にり患した者の自殺率を全人口の自殺率と比較すると約三〇倍から五八倍にも上るとされている。
三 本件事故によりXが被った傷害は,身体に重大な器質的傷害を伴う後遺症を残すようなものでなかったとはいうものの,本件事故の態様がXに大きな精神的衝撃を与え,しかもその衝撃か長い年月にわたって残るようなものであったこと,その後の補償交渉が円滑に進行しなかったことなどが原因となって,Xが災害神経症状態に陥り,更にその状態から抜け出せないままうつ病になり,その改善をみないまま自殺に至ったこと,自らに責任のない事故で傷害を受けた場合には災害神経症状態を経てうつ病に発展しやすく,うつ病にり患した者の自殺率は全人口の自殺率と比較してはるかに高いなど原審の適法に確定した事実関係を総合すると,本件事故とXの自殺との間に相当因果関係があるとした上,自殺には同人の心因的要因も寄与しているとして相応の減額をして死亡による損害額を定めた原審の判断は,正当として是認することができ,原判決に所論の違法はない。所論引用の判例は,いずれも事案を異にし本件に適切でない。論旨は採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条,九三条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官三好達 裁判官大堀誠一,同味村治,同小野幹雄,同大白勝
自賠責保険金支払日までの遅延損害金(最判平成12年9月8日金融法務事情1595号63頁)
交通事故の被害者が事故による損害金の支払義務に対する事故日から自賠責保険金支払日までの遅延損害金を請求できるとされた事例
主 文
一 原判決中上告人らに関する部分を次のとおり変更する。
第一審判決中上告人らに関する部分を次のとおり変更する。
1被上告人らは、上告人井手渉に対し、連帯して、一二八六万八三九一円及びうち一二〇〇万七三三七円に対する平成二年一一月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2被上告人らは、上告人井手政子に対し、連帯して、一一七一万二三七一円及びうち一〇八五万一三一七円に対する平成二年一一月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
3上告人らのその余の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟の総費用はこれを四分し、その三を上告人らの、その余を被上告人らの負担とする。
判決理由
上告代理人金子宰慶、同野崎綾子の上告受理申立て理由(ただし、排除されたものを除く。)について
一 本件は、平成二年一一月一〇日に発生した交通事故で死亡した陽子の相続人(両親)である上告人らが、加害車両の運転者である被上告人安藤に対し民法七〇九条に基づき、同車両の保有車である同尾花に対し自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)三条又は民法七一五条一項に基づき、損害賠償を請求する訴訟である。上告人らの請求の趣旨は、被上告人らに対し、連帯して、上告人渉に対し五六二四万三二七〇円、同政子に対し四四九七万一八七八円及びこれらに対する平成二年一一月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員の支払を求めるものである。
上告人らは、自賠法に基づく保険金として合計二五一〇万六二四五円の支払を既に受けているところ、上告人らが右保険金によりてん補された損害額に対する本件事故発生日である平成二年一一月一〇日から右保険金支払日である同四年三月二五日までの年五分の割合による遅延損害金のうち一七二万二一〇九円(各その半額)の支払を本件において請求していることは、記録上明らかである。
二 原審は、被上告人らの損害賠償義務を認め、上告人渉及び同政子の損害額(陽子の損害を相続した分と上告人ら固有の損害の合計)をそれぞれ二三五六万〇四五九円、二二四〇万四四三九円と認定し、上告人らの右各損害額から右保険金によるてん補額の半額である一二五五万三一二二円を控除し、これに弁護士費用各一〇〇万円を加え、被上告人らに対し、連帯して、上告人渉に対し一二〇〇万七三三七円、同政子に対し一〇八五万一三一七円及びこれらに対する平成二年一一月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員の支払を命じ、上告人らのその余の請求を棄却した。
三 しかしながら、原審の右判断のうち、自賠法に基づく保険金によりてん補された損害額に対する本件事故発生日から保険金支払日までの遅延損害金請求を棄却した部分は、是認することができない。その理由は、次のとおりである。
不法行為に基づく損害賠償債務は、損害の発生と同時に、何らの催告を要することなく、遅滞に陥るものであって(最高裁昭和三四年(オ)第一一七号同三七年九月四日第三小法廷判決・民集一六巻九号一八三四頁)、後に自賠法に基づく保険金の支払によって元本債務に相当する損害がてん補されたとしても、右てん補された損害金の支払債務に対する損害発生日である事故の日から右支払日までの遅延損害金は既に発生しているのであるから、右遅延損害金の請求が制限される理由はない。
したがって、本件においては、自賠法に基づく保険金によりてん補された損害額に対する本件事故発生日から右保険金支払日までの遅延損害金請求は当然に認容されるべきであり、これを棄却した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決は右請求に係る部分につき破棄を免れない。
そうすると、上告人らの請求は、原審が認容したところに加えて、右保険金によりてん補された損害額各一二五五万三一二二円に対する本件事故発生日である平成二年一一月一〇日から右保険金支払日である同四年三月二五日までの民法所定の年五分の割合による遅延損害金のうち上告人らが請求する各八六万一〇五四円(円未満切り捨て)の支払を求める限度で認容すべきである。したがって、原判決中上告人らに関する部分を主文第一項のとおり変更するのが相当である。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官福田博 裁判官河合伸一,同北川弘治,同亀山継夫,同梶谷玄
被用者の私用運転と事業執行性(最判昭和39年2月4日民集18巻2号252頁)
会社被用者が私用のため会社の自動車を運転中他人に加えた損害が民法715条の「事業ノ執行ニ付キ」生じたものとされた事例
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理 由
上告代理人谷沢政二の上告理由第一及び第二の七について。論旨は,要するに,原審の認定した事実に添わない事実を主張し,これに拠って原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断,事実の認定を非難するものであって,採るを得ない。
同第二の一乃至五について。
原判決及びその引用にかかる第一審判決において認定せられた事実によれば,上告会社は,自動車,その部品及び附属品の販売,車体の製作並びにその取付を営業目的とする会社であり,上告人Aは,上告会社の被用者でその販売課に勤務していたこと,右上告人Aは,本件事故当日の午後五時頃上告会社の勤務を終えて退社し,和歌山市内で映画見物をした後帰宅すべく国鉄和歌山市駅に赴いたが,最終列車に乗り遅れたため一旦上告会社に引き返し,上告会社所有の本件ウィルスジープ普通自動車を引き出して,これを運転しつつ帰宅する途中で本件追突事故を惹起たものであること,上告人Aは,平素上告会社に通勤するには国鉄を利用して居り,販売契約係として自動車購入の勧誘並びに販売契約締結の業務を担当し,右業務執行のため他の同係員八名と共に前記ジープを運転してこれに当っていたこと,上告会社においては,ジープは会社業務の為に使用する場合であっても上司の許可を得なければならず,私用に使うことは禁止されていたことが,いずれも,認められるというのである。このような事実関係の下においては,上告人Aの本件事故当夜における右ジープの運行は,会社業務の適正な執行行為ではなく,主観的には同上告人の私用を弁ずる為であったというべきであるから,上告会社の内規に違反してなされた行為ではあるが,民法七一五条に規定する「事業ノ執行ニ付キ」というのは,必ずしも被用者がその担当する業務を適正に執行する場合だけを指すのでなく,広く被用者の行為の外形を捉えて客観的に観察したとき,使用者の事業の態様,規模等からしてそれが被用者の職務行為の範囲内に属するものと認められる場合で足りるものと解すべきであるとし,この見地よりすれば,上告人Aの前記行為は,結局,その職務の範囲内の行為と認められ,その結果惹起された本件事故による損害は上告人の事業の執行について生じたものと解するのが相当であるから,被用者である上告人Aの本件不法行為につき使用者である上告会社がその責任を負担すべきものであるとした原審の判断は,正当である。
論旨は,要するに,原判示に添わない事実或は独自の法律的見解を主張し,これに拠って原判決を非難するものであって,採るを得ない。
同第二の六について。
上告会社は,被用者である上告人Aの選任及びその事業の監督について相当の注意をなしたことにつき,原審において主張するところがないのみならず,原審は,原判決においてこの点につき,上告会社の全立証に徴しても,同会社が上告人Aの監督につき相当の注意をなしたものとは認められない旨説示して居るのであるから,原判決に所論の違法はない。
論旨は,理由がない。よって,民訴四〇一条,九五条,八九条,九三条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官石坂修一,裁判官五鬼上堅磐,同横田正俊
法人の代表者と民法第715条第2項の責任(最判昭和42年5月30日民集21巻4号961頁)
法人代表者と民法第715条第2項の責任
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人安藤一二夫の上告理由第一点について。
本件事故発生の主たる原因は,自動車運転者甲の運転七の過失にあるが,上告人乙が,判示のように,すぐ近くにある横断歩道によらないで,危険な状況のもとに道路の横断を企て,しかも,道路中央附近に佇立したまま,接近して来る自動車に対する適切な避譲行為をとらなかった点において,同上告人にも過失のあることは否定できないとし,その過失を,本件損害賠償額の決定にあたり,判示の程度斟酌した原審の判断は,原審の確定した事実関係のもとにおいては,相当と認められ,その問に,所論のような違法は存しない。それ故,論旨は採用できない。
同第二点について。
民法七一五条二項にいう「使用者ニ代ハリテ事業ヲ監督スル者」とは,客観的に見て,使用者に代り現実に事業を監督する地位にある者を指称するものと解すべきであり(昭和三二年(オ)第九二二号,同三五年四月一四日判決,民集一四巻五号八六三頁),使用者が法人である場合において,その代表者が現実に被用者の選任,監督を担当しているときは,右代表者は同条項にいう代理監督者に該当し,当該被用者が事業の執行につきなした行為について,代理監督者として責任を負わなければならないが,代表者が,単に法人の代表機関として一般的業務執行権限を有することから,ただちに,同条項を適用してその個人責任を問うことはできないものと解するを相当とする。
従って,被上告人丙をもって同条項にいう代理監督者であるとするためには,同被上告人が前記甲の使用者たる被上告会社の代表取締役であったというだけでは足りず,同被上告人が現実に右被用者の選任または監督をなす地位にあった事実を,その責任を問う上告人らにおいて主張立証しなければならない。ところが,かかる具体的事実については,原審において上告人らから何らの主張もなされていないのみでなく,原判示によれば,右甲の所属する被上告会社中野営業所の営業については,被上告人丙がこれを具体的に監督する関係にあったとは認めがたいというのであって,この認定は,挙示の証拠関係に徴し肯認しうるところであるから,右甲の行為につき同被上告人に対して代理監督者としての責めを問うことはできないとした原審の判断は正当というべく,右判断ないしその前提たる事実認定に関し,原判決に,所論のような,法の解釈や立証責任の分配を誤った違法があるものとは認められない。それ故,論旨は採用できない。
同第三点について。
原審が,その認定した上告人乙の負傷及び後遺症の程度その他諸般の事情に鑑みると,本件事故により被害者の妻である上告人丁の被った精神的苦痛は,未だ同上告人自身の権利として慰謝料請求権を認めなければならない程重大なものとはいえないとして同上告人の請求を排斥した判断は,正当として首肯できる。原判決に所論の法令解釈の違背があるものとはなしえず,論旨も採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条,九三条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁 裁判長裁判官横田正俊,同柏原語六,同田中二郎,同下村三郎,同松本正雄
従業員出張中の自家用車の事故と使用者責任(最判昭和52年9月22日民集31巻5号767頁)
会社の従業員が自家用車を用いて出張中に惹起した交通事故につき会社の使用者責任が否定された事例
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人油木巌の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は,原判決の挙示する証拠関係に照らし,正当として是認できる。右事実関係のもとで,被上告人が森谷利夫に対し同人の本件出張につき自家用車の利用を許容していたことを認めるべき事情のない本件においては,同人らが米子市に向うために自家用車を運転したことをもって,行為の外形から客観的にみても,被上告人の業務の執行にあたるということはできず,したがって,右出張からの帰途に惹起された本件事故当時における同人の運転行為もまた被上告人の業務の執行にあたらない旨の原審の判断は,正当というべきである。原判決に所論の違法はない。論旨は,畢竟,原審の専権に属する証拠の取捨判断,事実の認定を非難するか,又は独自の見解に立って原審の判断を論難するものにすぎず,採用することができない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官団藤重光,裁判官岸上康夫,同藤崎萬里
下請負人の被用者の不法行為と元請負人の使用者責任(最判昭和37年12月14日民集16巻12号2368頁)
ア下請負人の被用者の不法行為につき元請負人が民法715条の責任を負うための要件
イ将来において得べき全利益を損害賠償として一時に支払を受ける場合とホフマン式計算法
主 文
原判決中上告人甲,同乙に関する部分を破棄し,右部分につき本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
上告人丙の本件上告を却する。
前項の部分に関する上告費用は,上告人丙の負担とする。
理 由
上告代理人真田重二の上告理由第一点,第二点について。
上告人甲は,小池組なる商号を使用して土木建筑請求負業を営んでいる者であるが,昭和二八年から病気のため自から営業をすることができなかったため,息子の上告人乙をして右請負業の監督をさせており,上告人丙は,土木建築下請負業を営む者であること,上告人甲は,和歌山県から水害復旧道路工事等を請負い,昭和二九年三月頃より数回上告人丙と下請負契約を締結し,本件事故発生当時は,上告人甲が和歌山県から請負った同県有田郡X村(現在清水町)久野原地内の昭和二八年度及び同二九年度県道高野湯浅港線道路復旧工事の下請工事をさせており,上告人丙は,右下請工事に要する砂利,セメントその他の材料等の運搬,右下請工事に関する連絡などに本件小型四輪貨物自動車を使用していたこと,右自動車は,上告人丙において昭和二九年三月一〇日前所有者たる上告人甲より買い受けたものであるが,登録名義の変更手続をせず,本件事故が発生した同年八月一三日当時においても,登録上は上告人乙の名義となっていたばかりでなく,右自動車に金文字で小池組の表示のあるままで前記用途に使用することを上告人丁両名において黙認していたこと,本件下請負契約においては,上告人丙の施行する下請工事につき,上告人甲は和歌山県の設計書に基づいて,コンクリートの配合状況,道路の中心の確認,道路ののりの勾配,床堀の状況等の監督をすることになっており,上告人丙は右監督のもとに工事を施行する約束で,実際においても,上告人甲の方から,毎日のように工事現場に施行の監督に来ていたこと,本件事故当日は盆休みであって,上告人丙は神戸市の自宅に居住する妻が手術をすることになっており,右自宅に帰る必要が生じたので帰宅することになったが,たまたま右下請負業に使用する本件自動車の雇運転手が盆休みで帰郷していたため右自動車を運転する者がいなかったので,前日の一二日息子の戊をして自動三輪車の運転免許しか受けていないPに本件自動車の運転を依頼させてその承諾をえ,事故当日まず運転免許を受けていない戊に本件自動車を運転させて前記清水町大字久野原の飯場事務所を出発し,同町大字清水でPを同乗させたところ,途中Pは同人の元雇主Qからその所有する自動三輪車の故障の修理方法を和歌山市所在の宮本モータース店に問い合せてくれるよう依頼を受けてこれを承諾し,ついで戊と交代してPが本件自動車を運転して海南市海南駅に至り,上告人丙はここで降りるとともに,その後はP及び戊の両名が和歌山市を経て前記飯場事務所まで右自動車を運転することを許容し,Pは右自動車を運転して和歌山市に至り,宮本モータース店に立ち寄りQから依頼を受けた用件をすませ,戊の運転により帰途につき,和歌山県紀三井寺附近からPが交代して運転しているときに,海南市日方和歌山電気軌道株式会社日方停留所附近の道路上で,同人の運転上の過失により本件事故を惹起したことは,いずれも原判決が確定した事実である。
右事実関係からすれば,Pの本件自動車の運転は,上告人丙の下請負業自体の執行ではないけれども,自動車を使用する同人の前記下請負業と密接な関係にあり,客観的にみて同人の支配の範囲内にあるものであるから,その事業の執行についてなされたものというべきであるとした原判決は,正当としてこれを是認しうる。第一点の論旨は,独自の見解に立脚するもので採用できない。
つぎに,元請負人が下請負人に対し,工事上の指図をしもしくはその監督のもとに工事を施行させ,その関係が使用者と被用者との関係またはこれと同視しうる場合において,下請負人がさらに第三者を使用しているとき,その第三者が他人に加えた損害につき元請負人が民法七一五条の責任を負うべき範囲については,下請工事の附随的行為またはその延長もしくは外形上下請負人の事業の範囲内に含まれるとされるすべての行為につき元請負人が右責任を負うものと解すべきではなく,右第三者に直接間接に元請負人の指揮監督関係が及んでいる場合になされた右第三者の行為のみが元請負人の事業の執行についてなされたものというべきであり,その限度で元請負人は右第三者の不法行為につき責に任ずるものと解するのを相当とする。そして,前示原判決の確定した事実関係からすれば,本件Pの行為は,原判決のとおり,上告人丙の本件下請負業自体の執行ではなくただそれと密接な関係にあるため外形上同人の事業の執行の範囲内に含まれるといえるにすぎないのであるから,このような場合のPの行為が元請負人たる上告人甲の事業の執行についてなされたものとするための前記要件をみたすものとは到底認めることができない。したがって,上告人Aと上告人Cとの関係が使用者と被用者との関係と同視しうること,上告人Cが本件自動車を使用してその事業を営むことについて上告人Aの指揮監督を受けていたことおよびPの本件行為が上告人丙の事業の執行についてなされたものと認めうるとのことから,たやすく右Pの本件不法行為が上告人Aの指揮監督権の及ぶ事業の範囲内において発生したものであるとした原判決には,法律の解釈を誤ったかもしくは理由不備の違法があるというべきである。されば,論旨第二点は理由あるに帰し,原判決は上告人甲及び同乙に関する部分については破棄を免れない。そして,本件は右部分について,なお前示上告人甲の指揮監督関係の点をさらに審理判断すべき要があるものと認められるから,右部分について本件を原裁判所に差し戻すことを相当とする。
同第三点について。
原判決が,亡Rの得べかりし利得は,死亡当時の三二年六月からその後満六〇年まで二七年六月間,年間七四,○○○円の割合による合計二,〇三五,○○○円となるが,これを死亡時において一時に支払を受けるものとし,ホフマン式計算法により年五分の割合の中間利息を控除して計算すると一,三〇一,七一五円(円以下切捨)となることは計算上明らかであると説示していることは所論のとおりである。ところで,論旨がホフマン式計算法として挙示する算式は,推定余命年間の全利得をその最終時に利得するものとの仮定に立ってその金額から中間利息を控除して算出する方法であるが(これをかりに単式と名づける。),同じくホフマン式計算法といっても,推定余命年間を数期に分ち,各期末ごとに利得するものとの仮定に立ってその各金額から各中間利息を控除してそれらの合算額を算出する方法もある(これをかりに複式と名づける。)そして,前記のように,原判決は元年ごとの得べかりし利得を七四,○○○円と確定しているのであるから,このような本件の場合においては,一年ごとの期間に分ち前記複式により算出するのが相当である。よって,この方法により前記数字をあてはめて計算してみると,少なくとも,原判決が最終的に第一審判決の限度において被上告人X,同Y,同Zの三名に対して認容した損害賠償請求額の合計九七八,三〇五円以上になることは計算上明らかであるから,論旨は,なんら原判決に影響を及ぼすべき法令違反の主張とはならない。論旨は採用できない。
よって,民訴四〇七条,三九六条,三八四条,九五条,八九条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
よって,民訴四〇七条,三九六条,三八四条,九五条,八九条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官池田克 裁判官河村大助,同奥野健一,同山田作之助
個人会社の代表者の負傷と会社の損害賠償(最判昭和43年11月15日民集22巻12号2614頁)
個人会社の代表者の負傷と加害者に対する会社の損害賠償の請求
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由第一点について。
論旨は,要するに,上告人はスクーターを運転中に甲と衝突して負傷させたのであるから,同人の被った損害を賠償すれば足り,同人以外の者である被上告会社に対し損害賠償義務を負うべきいわれはない,何故なら,上告人の同人に対する加害行為とこれによって被上告会社の被った損害との間には相当因果関係がないからである,と主張する。
よって検討するのに,本件において,上告人の過失により惹起された加害行為の直接の被害者となったのは甲であり,同人の負傷により得べかりし利益を喪失したと主張してその損害の賠償を求めるのは,同人を代表者とする被上告会社であって,法律上,両者が人格を異にすることは所論のとおりである。
しかし,原判決の確定するところによれば,甲は,もと個人で飯田薬局という商号のもとに薬種業を営んでいたのを,いったん合資会社組織に改めた後これを解散し,その後ふたたび個人で真明堂という商号のもとに営業を続けたが,納税上個人企業による経営は不利であるということから,昭和三三年一〇月一日有限会社形態の被上告会社を設立し,以後これを経営したものであるが,社員は甲とその妻乙の両名だけで,甲が唯一の取締役であると同時に,法律上当然に被上告会社を代表する取締役であって,乙は名目上の社員であるにとどまり,取締役ではなく,被上告会社には甲以外に薬剤師はおらず,被上告会社は,いわば形式上有限会社という法形態をとったにとどまる,実質上甲個人の営業であって,甲を離れて被上告会社の存続は考えることができず,被上告会社にとって,同人は余人をもって代えることのできない不可欠の存在である,というのである。
すなわち,これを約言すれば,被上告会社は法人とは名ばかりの,俗にいう個人会社であり,その実権は従前同様甲個人に集中して,同人には被上告会社の機関としての代替性がなく,経済的に同人と被上告会社とは一体をなす関係にあるものと認められるのであって,かかる原審認定の事実関係のもとにおいては,原審が,上告人の甲に対する加害行為と同人の受傷による被上告会社の利益の逸失との間に相当因果関係の存することを認め,形式上間接の被害者たる被上告会社の本訴請求を認容しうべきものとした判断は,正当である。
原判決に所論の違法はなく,論旨は採用できない。
原審挙示の証拠によれば,所論の点に関する原審の認定は肯認しえないものではない。論旨は,ひつきよう,原審の専権に属する証拠の取捨判断,事実の認定を非難するに帰し,採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官奥野健一,裁判官草鹿浅之介,同城戸芳彦,同石田和外,同色川幸太郎
道路運送法四条一項の免許のない事業者の営業利益(最判昭和39年10月29日民集18巻8号1823頁)
道路運送法四条一項の免許のない自動車運送事業の経営により得べかりし営業利益の喪失を理由とする損害賠償請求を認容した事例
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人三木大一郎の上告理由について。
被上告人の所論事業の経営が,所論のように道路運送法四条一項に違反しても,その事業経営の過程において,被上告人が他人と締結するそれぞれの運送契約が私法上当然無効となるべき筋台のものではなく,被上告人は右契約に基づき相手方に対し運送賃の支払を請求し得る権利を取得し,右権利に基づき運送賃を受領することを妨げないものといわなければならない。しからば,原判示の,得べかりし利益の喪失は,民法四一六条により賠償を受け得る通常生ずべき損害に該ると解するのが正当である。所論は,右と異なる法律解釈を前提として原判決を非難するものであり,前提を欠く主張であって,原判決は結局正当である。それ故,所論は採るを得ない。
よって,民訴四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官入江俊郎の補足意見,裁判官松田二郎の少数意見あるほか,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
裁判官入江俊郎の補足意見(略) 裁判官松田二郎の少数意見(略)
最高裁裁判長裁判官入江俊郎,裁判官長部謹吾,同松田二郎 裁判官斎藤朔郎は死亡につき,署名押印することができない。 裁判長裁判官 入江俊郎
慰謝料の相続と固有の慰謝料(最判昭和42年11月30日判例時報501号70頁)
死亡した子の慰藉料の相続と親固有の慰藉料の双方を認容した事例(反対意見がある)
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人松本才喜,同荻野弘明,同木下達郎の上告坪山第一点ないし第六点について。
所論の諸点に関する原審の事実認定は,原判決挙示の証拠関係に照らして肯認できないものではなく,その過程に所論の違法は認められない。論旨は,ひっきょう,原審の専権に属する証拠の取捨判断,事実の認定か非難するに帰し,採ることができない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官松田二郎,同岩田誠の反対意見があるほか,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
裁判官松田二郎の反対意見は,次のとおりである。
原判決(引用の第一審判決を含む。以下同じ)は,慰謝料請求権の相続に関し,本件の被害者光一において,慰謝料請求権行使の意思表小をしたと否とにかかわらず,右慰謝料請求権は相続の対象となるものと解するを相当とする旨判したうえ,右光一が生前に慰謝料請求の意思を表明した等これが通常の金銭債権に転化したと認められる事情について何らの主張及び立証のない本件において,同人の両親である被上告人らに対し,慰謝料請求権の相続を肯定している。しかし,慰謝料請求権は,その本質上被害者に専属する権利であって,加害者が被害者の慰謝料請求に対し,契約または債務名義により一定額の金員を支払うべきものとされた場合等,それが通常の金銭債権と多く択ぶところなく,従ってこれに転化したものと認められるに至った場合にのみ,相続の対象となるものと解すべきである。(その理由は,当裁判所昭和三八年(オ)第一四〇八号,昭和四二年一一月一日言渡大法廷判決における私の反対意見と同一であるから,それをここに引用する。)そうであれば,右光一の慰謝料請求権が通常の金銭債権に転化したことについて何ら判示することなく,右慰謝料請求権が当然相続の対象となるとした原判決は,その部分に限り,本件上告理由の判断に立ち入るまでもなく,違法であって破棄を免れず,右請求に関する部分は,さらに右の点を審理するため,これを原審に差し戻すべきものである。
裁判官岩田誠は,裁判官松田二郎の右反対意見に同調する。
最高裁裁判長裁判官大隅健一郎,裁判官入江俊郎,同長部謹吾,同松田二郎,同岩田誠
名義使用許諾を受けた者の示談と商法23条(最判昭和52年12月23日民集31巻7号1570頁)
営業上の名義使用許諾を受けた者が営業活動上惹起された交通事故に基づく損害賠償義務者として示談をした場合と商法23条(否定)
主 文
原判決を破棄し,第一審判決を取り消す。
被上告人らの請求を棄却する。
訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人阿部長,同阿部泰雄の上告理由第一点について
原審は,商法二三条所定の名義貸与者の責任について,右の責任はその者を営業主と誤認して営業に関する取引をした者に対してのみ認められるものであって,交通事故のような事実行為たる不法行為を理由とする損害賠償の請求は,右営業に関する取引とはいえないから,名義貸与者がこれについて責任を負うことはありえないとしながらも,すすんで,名義貸与者と同種の営業活動上惹起した交通事故につき不法行為に関する責任のあることを前提として,名義貸与を受けた者が名義貸与者の商号を用いて被害者と示談契約を締結することは,右にいう営業に関する取引にあたり,名義貸与者は,その者を営業主と誤認して右契約を締結した者に対し,名義貸与を受けた者と連帯して弁済の責に任ずべきものであると判示したうえ,(1) 訴外甲は,上告会社からその名義(商号)を使用することの許諾を受け,上告会社の商号である大宝商事株式会社の大東町出張所名義で事務所を開設し,同出張所長の肩書を用いて営業を行っていたこと,(2) 本件交通事故は右甲が営業活動を行うについて惹起されたものであること,(3) 被上告人らは,甲から上告会社大東町出張所長である旨を告げられ,上告会社の住所,電話番号を付記した右肩書つきの名刺を受領したこと等から甲を上告会社の出張所長と信じ,甲との間で,背後に本社としての上告会社の存在を前提とし,右出張所を相手方として,昭和四九年五月二四日,右出張所が,被上告人乙に対し医療費,慰謝料等九二万四一七〇円を,同寛に対し休業補償費等九万一五六〇円を同年一二月三一日までにそれぞれ支払う旨の本件示談契約を締結したこと等の事実を確定し,右事実関係のもとにおいては,上告会社は甲が締結した右示談契約に基づいて被上告人らに対し弁済の責に任ずべきものとして,被上告人らの上告会社に対する本訴請求を認容している。
しかしながら,商法二三条の規定の趣旨は,第三者が名義貸与者を真実の営業主であると誤認して名義貸与を受けた者との間で取引をした場合に,名義貸与者が営業主であるとの外観を信頼した第三者の受けるべき不測の損害を防止するため,第三者を保護し取引の安全を期するということにあるというべきであるから,同条にいう「其ノ取引ニ因リテ生ジタル債務」とは,第三者において右の外観を信じて取引関係に入ったため,名義貸与を受けた者がその取引をしたことによって負担することとなった債務を指称するものと解するのが相当である。それ故,名義貸与を受けた者が交通事故その他の事実行為たる不法行為に起因して負担するに至った損害賠償債務は,右交通事故その他の不法行為が名義貸与者と同種の営業活動を行うにつき惹起されたものであっても右にいう債務にあたらないのはもとより,かようにしてすでに負担するに至った本来同条の規定の適用のない債務について,名義貸与を受けた者と被害者との間で,単にその支払金額と支払方法を定めるにすぎない示談契約が締結された場合に,右契約の締結にあたり,被害者が名義貸与者をもって営業主すなわち損害賠償債務の終局的な負担者であると誤認した事実があったとしても,右契約に基づいて支払うべきものとされた損害賠償債務をもって,前記法条にいう「其ノ取引ニ因リテ生ジタル債務」にあたると解するのは相当でないというべきである。
してみれば,原審の確定した右事実関係のもとにおいて,名義貸与者である上告会社もまたAと連帯して本件示談契約上の債務を弁済する責任があるとした原判決には商法二三条の解釈適用を誤った違法があるものというべく,右違法はその結論に影響を及ぼすことが明らかであるから,論旨は理由がある。したがって,原判決は,その余の上告理由につき判断を加えるまでもなく破棄を免れず,これと同旨の第一審判決もまた取消を免れない。
そして,右説示したところによれば,他に特段の主張・立証をしたことの認められない本件においては,被上告人らの本訴請求はいずれも理由がないものといわざるをえないから,これを棄却すべきである。
よって,民訴法四〇八条,三九六条,三八六条,九六条,八九条,九三条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官大塚喜一郎,裁判官本林 讓,同服部高顯
被害者看護のための近親者の旅費(最判昭和49年4月25日民集28巻3号447頁)
交通事故の被害者の近親者が看護等のため被害者の許に往復した旅費と通常損害
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人田中登,同藤原寛治,同二宮充子,同大内猛彦,同成見幸子の上告理由について。
おもうに,交通事故等の不法行為によって被害者が重傷を負ったため,被害者の現在地から遠隔の地に居住又は滞在している被害者の近親者が,被害者の看護等のために被害者の許に赴くことを余儀なくされ,それに要する旅費を出捐した場合,当該近親者において看護等のため被害者の許に赴くことが,被害者の傷害の程度,当該近親者が看護に当たることの必要性等の諸般の事情からみて社会通念上相当であり,被害者が近親者に対し右旅費を返還又は償還すべきものと認められるときには,右旅費は,近親者が被害者の許に往復するために通常利用される交通機関の普通運賃の限度内においては,当該不法行為により通常生ずべき損害に該当するものと解すべきである。そして,国際交流が発達した今日,家族の一員が外国に赴いていることはしばしば見られる事態であり,また,日本にいるその家族の他の構成員が傷病のため看護を要する状態となった場合,外国に滞在する者が,右の者の看護等のために一時帰国し,再び外国に赴くことも容易であるといえるから,前示の解釈は,被害者の近親者が外国に居住又は滞在している場合であっても妥当するものというべきである。
本件において,原審が適法に確定したところによれば,被上告人は,昭和四三年八月二六日本件交通事故により脳挫傷,左大腿挫創,腰部打撲傷の傷害を受け,直ちに外科病院に入院したが,当時は危篤状態で一週間にわたり意識が混濁した状況にあり,その後精神障害治療のため,同年一〇月五日から同年一一月二九日まで五六日間他の病院に転入院し,その後さらに同月三〇日から昭和四五年一〇月二一日までの間二七回にわたり病院に通院して治療を受けたというのであり,他方,被上告人の娘である訴外甲は,ウイーンに留学すべく昭和四三年八月二四日横浜からナホトカ経由で出発したが,途中モスクワに到着した際,本件交通事故の通知を受けたため同年九月六日急遽帰国し,翌七日から入院中の被上告人に付添って看護し,昭和四四年四月改めてウイーンに赴いたが,その結果,被上告人が甲のために調達した留学のための諸費用のうち横浜からナホトカ経由ウイーンまでの旅費一三万二二四四円が無駄となったのみならず,被上告人は甲が帰国のために要したモスクワからナホトカ経由横浜までの旅費八万四〇三四円(以下,両者を合わせて本件旅費という。)の支出を余儀なくされ,右合計二一万六二七八円の損害を被ったというのである。右事実関係のもとにおいては,甲が被上告人の看護のため一時帰国したことは社会通念上相当というべきであり,本件旅費は,被上告人が甲に代って又は同人に対して支払うべきものであるから,被上告人が被った損害と認めるべきものであり(原審はこの趣旨を判示したものと解される。),その額もウイーンに赴き又はモスクワから帰国するために通常利用される交通機関の普通運賃額を上廻るものでないことが明らかであるから,本件旅費は被上告人が本件交通事故により被った通常生ずべき損害であるといわなければならない。従って,これと同旨の原審の判断は,正当として是認できる。
原判決に所論の違法はなく,論旨は採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官大隅健一郎の意見があるほか裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
裁判官大隅健一郎の意見(略)
最高裁裁判長裁判官大隅健一郎,裁判官藤林益三,同下田武三,同岸 盛一,同岸上康夫
近親者の看護費用(最判昭和46年6月29日民集25巻4号650頁)
付添看護を必要とする被害者が近親者の無償の付添看護を受けた場合と付添看護料相当額の賠償請求の許否
主 文
原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人坂根徳博の上告理由第一について。
原判決(その引用にかかる第一審判決を含む。以下同じ。)は,上告人が昭和四〇年一月一日から同四一年一二月三一日までにその三人の娘より受けた看護を一日分五〇〇円と評価し,これを財産的損害としてその賠償の請求をしたのに対し,次のように判示する。すなわち,親に身体の故障があるときに子がその身のまわりの世話をすることは,経済的な対価を求めない肉親の情誼に出た行為であって,子の付添看護労働を金銭的に評価し,現実の支出はないのにかかわらず,家政婦や付添人を雇ったときと同視してこれを財産的損害とみることはできない。したがって,上告人がその娘に対し右金員を現実に支払ったものでも,支払いを求められているものでもない本件においては,右金員を損害としてその賠償を請求することは許されない,としているのである。
しかし,被害者が受傷により付添看護を必要とし,親子,配偶者などの近親者の付添看護を受けた場合には,現実に付添看護料の支払いをせずまたはその支払請求を受けていなくても,被害者は近親者の付添看護料相当額の損害を蒙ったものとして,加害者に対しその賠償請求をすることができるものと解するを相当とする。けだし,親子,配偶者などの近親者に身体の故障があるときに近親者がその身のまわりの世話をすることは肉親の情誼に出ることが多いことはもとよりであるが,それらの者の提供した労働はこれを金銭的に評価しえないものではなく,ただ,実際には両者の身分関係上その出捐を免れていることが多いだけで,このような場合には肉親たるの身分関係に基因する恩恵の効果を加害者にまで及ぼすべきものではなく,被害者は,近親者の付添看護料相当額の損害を蒙ったものとして,加害者に対してその賠償を請求することができるものと解すべきだからである。
したがって,これと異なる見解のもとに,上告人の娘らの付添看護料相当額についてはこれを財産的損害と解することができないとした原審の判断は,民法709条,715条一項,自動車損害賠償保障法三条にいう損害の解釈適用を誤るものであり,この点に関する論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。
同第二,第三について。
原判決は,上告人が保護実施機関に対して生活保護法六三条による費用返還義務を負うものではないとし,その根拠として次のように判示する。すなわち,同条は要保護者が同法四条一項にいう「利用し得る資産」があるにかかわらず,同条三項にいう「急迫した事由がある場合」にあたるとして,例外的に開始された保護受給の場合の受給者の費用返還義務を定めた規定であるところ,右にいう「利用し得る資産」の中には債権をも含ましめうるとしても,本件のように交通事故にあった被害者が加害者から直ちに賠償を得ることができず訴訟にまで至っているような場合においては,責任の範囲数額に関する争いがやみ現実に賠償金を取得するまでは,右の損害賠償債権をもって「利用し得る資産」にあたるとすることはできず,右被害者は,他に需要を満たすに足りるだけの資産等がないかぎり本来的に保護受給資格を有するものであって,同法四条三項により例外的に保護を与えられているものではない。したがって,上告人は,同法六三条による費用返還義務を負うものではない,としているのである。
しかし,原判示によれば,上告人に対しては,東京都江東区福祉事務所長から昭和四〇年一一月二〇日付をもって,上告人に対する本件医療扶助は生活保護法四条三項により開始されたものである旨および賠償の責任程度等について争いがやみ,賠償を受けることができるに至った場合には,同法六三条により医療扶助の費用の返還義務があるので,賠償が支払われたときはその額を申告されたい旨の指示があったというのである。したがって,上告人に対する本件医療扶助が同法四条三項により開始されたものである事実をうかがいうるのみならず,同法六三条は,同法四条一項にいう要保護者に利用しうる資産等の資力があるにかかわらず,保護の必要が急迫しているため,その資力を現実に活用することができない等の理由で同条三項により保護を受けた保護受給者がその資力を現実に活用することができる状態になった場合の費用返還義務を定めたものであるから,交通事故による被害者は,加害者に対して損害賠償請求権を有するとしても,加害者との間において損害賠償の責任や範囲等について争いがあり,賠償を直ちに受けることができない場合には,他に現実に利用しうる資力かないかぎり,傷病の治療等の保護の必要があるときは,同法四条三項により,利用し得る資産はあるが急迫した事由がある場合に該当するとして,例外的に保護を受けることができるのであり,必ずしも本来的な保護受給資格を有するものではない。それゆえ,このような保護受給者は,のちに損害賠償の責任範囲等について争いがやみ賠償を受けることができるに至ったときは,その資力を現実に活用することができる状態になったのであるから,同法六三条により費用返還義務が課せられるべきものと解するを相当とする。
したがって,これと異なる見解のもとに,上告人に費用返還義務なしとし,これを前提に上告人の損害賠償請求を理由のないものとした原審の判断は,生活保護法四条,六三条の解釈適用を誤るものである。
よって,民訴法四〇七条一項により,原判決を破棄し,さらに審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととし,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官関根小郷,裁判官田中二郎,同下村三郎,同松本正雄
法人の名誉権侵害と民法710条(最判昭和39年1月28日民集18巻1号136頁)
民法第710条は法人の名誉権侵害による無形の損害に適用があるか
主 文
原判決中被控訴人その余の請求を棄却すとの部分及び訴訟費用に関する部分を破棄する。
右破棄にかかる部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人高木右門,同馬場正夫,同芦田直衛,同青柳盛雄,同松本才喜,同谷村直雄の上告理由一ないし七,及び同馬場正夫の上告理由第一点,第二点について。
上告人は医療を目的とする法人であるが,被上告人の判示行為により名誉を毀損され,因って,財産上の損害ではないが,いわゆる,無形の損害を蒙ったから,これが賠償を求めるものであると主張する。しかし,わが民法においては,不法行為に基づく責任として,名誉毀損の場合につき裁判所において名誉を回復するに適当な処分を命ずることを得べき旨定めた外,原則として金銭賠償主義を採り,被害者が不法行為により蒙った損害を不法行為者をして金銭をもって賠償させることとしたのである。ところで,不法行為に因って侵害される権利ないし利益は財産権の外,身体,自由,名誉等いろいろあるが,その侵害の結果生ずべき損害は物質的のものか,精神的のものか二者その一を出でない。物質的なものは金銭に見積ることができ,容易に金銭賠償の対象とすることができるが,精神的なものは金銭に見積ることができない。しかし,そのままこれを放置すべきでないから,加害者から被害者に相当な金銭の支払をなさしめて,せめてその精神上の苦痛を和らげてやるのが相当である。これ慰藉料と唱えられるところのものである。民法七一〇条が不法行為者に財産以外の損害に対しても,その賠償を命ずることができるとしたのは,その意味をうたっているのである。法人にはもとより,精神上の苦痛というものを考えることができないから,これに金銭でもって賠償させるということはナンセンスである。法人が名誉を毀損された場合金銭賠償の対象としては,物質上の損害,すなわち財産上の損害しか考えることができないのである。すなわち法人は名誉毀損による無形の損害に対しては金銭賠償の請求をなし得ないものと解するを相当とする。
以上が所論の点に関する原判決の判断である。
しかし,民法710条は,財産以外の損害に対しても,その賠償をなすことを要すと規定するだけで,その損害の内容を限定してはいない。すなわち,その文面は判示のようにいわゆる慰藉料を支払うことによって,和らげられる精神上の苦痛だけを意味するものとは受けとり得ず,むしろすべての無形の損害を意味するものと読みとるべきである。従って右法条を根拠として判示のように無形の損害即精神上の苦痛と解し,延いて法人には精神がないから,無形の損害はあり得ず,有形の損害すなわち財産上の損害に対する賠償以外に法人の名誉侵害の場合において民法七二三条による特別な方法が認められている外,何等の救済手段も認められていないものと論詰するのは全くの謬見だと云わなければならない。
思うに,民法上のいわゆる損害とは,一口に云えば,侵害行為がなかったならば惹起しなかったであろう状態(原状)を(a)とし,侵害行為によって惹起されているところの現実の状態(現状)を(b)としa-b=xそのxを金銭で評価したものが損害である。そのうち,数理的に算定できるものが,有形の損害すなわち財産上の損害であり,その然らざるものが無形の損害である。しかしその無形の損害といえども法律の上では金銭評価の途が全くとざされているわけのものではない。侵害行為の程度,加害者,被害者の年令資産その社会的環境等各般の情況を斟酌して右金銭の評価は可能である。その顕著な事例は判示にいうところの精神上の苦痛を和らげるであろうところの慰藉料支払の場合である。しかし,無形の損害に対する賠償はその場合以外にないものと考うべきではない。そもそも,民事責任の眼目とするところは損害の填補である。すなわち前段で示したa-b=xの方式におけるxを金銭でカヴアーするのが,損害賠償のねらいなのである。かく観ずるならば,被害者が自然人であろうと,いわゆる無形の損害が精神上の苦痛であろうと,何んであろうとかかわりないわけであり,判示のような法人の名誉権に対する侵害の場合たると否とを問うところではないのである。尤も法人の名誉侵害の場合には民法七二三条により特別の手段が講じられている。しかし,それは被害者救済の一応の手段であり,それが,損害填補のすべてではないのである。このことは民法七二三条の文理解釈からも容易に推論し得るところである。そこで,判示にいわゆる慰藉料の支払をもって,和らげられるという無形の損害以外に,いったい,どのような無形の損害があるかという難問に逢着するのであるが,それはあくまで純法律的観念であって,前示のように金銭評価が可能であり,しかもその評価だけの金銭を支払うことが社会観念上至当と認められるところの損害の意味に帰するのである。それは恰も民法709条の解釈に当って侵害の対象となるものは有名権利でなくとも,侵害されることが社会通念上違法と認められる利益であれば足るという考え方と志向を同じうする。
以上を要約すれば,法人の名誉権侵害の場合は金銭評価の可能な無形の損害の発生すること必ずしも絶無ではなく,そのような損害は加害者をして金銭でもって賠償させるのを社会観念上至当とすべきであり,この場合は民法723条に被害者救済の格段な方法が規定されているとの故をもって,金銭賠償を否定することはできないということに帰結する。
そうだとすれば,原判決は判示の事実関係のもとで,被上告人の侵害行為により上告人の名誉を毀損されたと云いながら,上告人には法人であるの故を以て無形の損害の発生するの余地がないものとし,上告人の本訴金員の請求を一蹴したのは,原判決に影響を及ぼすこと明らかな重要な法律に違背した違法ある。
よって,民訴407条一項に従い裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官下飯坂潤夫,裁判官入江俊郎,同斎藤朔郎,同長部謹吾
被害者の夫の妹と民法711条の類推(最判昭和49年12月17日民集28巻10号2040頁)
民法711条の類推適用により被害者の夫の妹に慰藉料請求権が認められた事例
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人長塚安幸の上告理由第一点一ないし三について。
原審が,本件事故発生についての訴外亡甲の過失の有無及びその程度についての判断において,所論の点を斟酌していることは,原判文上明らかである。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用できない。
同第一点四ないし六及び第二点第一並びに上告代理人中野智明の上告理由第一及び第二について。
所論の点に関する原審の事実認定は,原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ,その過程に所論の違法はない。そして,原審が確定した事実関係のもとにおいては,本件事故が上告人の減速徐行義務及び警笛吹鳴義務違反の過失に起因するものであるとした原審の判断は,正当として是認できる。論旨は,原審の専権に属する証拠の取捨判断,事実認定を非難するか,原判決の認定にそわない事実を前提にその違法をいうものにすぎない。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用できない。
上告代理人中野智明の上告理由第三(一)について。
第一審判決及び原判決を対照すれば,原判決が被上告人乙を除くその余の被上告人らの請求のうち甲の逸失利益の相続分として認容した額は,第一審判決のそれを超えるものではないことが明らかであるから,原判決に所論の違法はない。論旨は,原判決を正解しないでその違法をいうものにすぎず,採用できない。
同第三(四)について。
原判決は,甲が本件事故により重傷を受け入院した事実を判示しているのであるから,所論看病等の必要のあったことについても判示しているものと認められる。
従って,原判決に所論の違法はなく,論旨は採用できない。
上告代理人長塚安幸の上告理由第二点第二並びに同中野智明の上告理由第三(二)及び(三)について。
不法行為による生命侵害があった場合,被害者の父母,配偶者及び子が加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうることは,民法七一一条が明文をもって認めるところであるが,右規定はこれを限定的に解すべきものでなく,文言上同条に該当しない者であっても,被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し,被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は,同条の類推適用により,加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうるものと解するのが,相当である。本件において,原審が適法に確定したところによれば,被上告人乙は,甲の夫である被上告人丙の実妹であり,原審の口頭弁論終結当時四六年に達していたが,幼児期に罹患した脊髄等カリエスの後遺症により跛行顕著な身体障害等級二号の身体障害者であるため,長年にわたり甲と同居し,同女の庇護のもとに生活を維持し,将来もその継続が期待されていたところ,同女の突然の死亡により甚大な精神的苦痛を受けたというのであるから,被上告人乙は,民法七一一条の類推適用により,上告人に対し慰藉料を請求しうるものと解するのが,相当である。これと同趣旨の原審の判断は,正当として是認できる。論旨はこれと異なる見解に立脚して原判決を非難するものにすぎない。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官関根小郷,裁判官天野武一,同坂本吉勝,同江里口清雄,同高辻正己
不法行為により身体を害された被害者の母の慰藉料請求(最判昭和33年8月5日民集12巻12号1901頁)
不法行為により身体を害された被害者の母の慰藉料請求
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人池留三の上告理由第一点について。
所論は,民法七一一条の法意は生命を害された者の近親者以外の者に慰籍料の請求を認めないことにあると主張し,身体傷害を受けたにとゞまる被上告人甲の母被上告人乙の慰籍料請求を認容した原判決の違法をいうのである。
しかし,原審の認定するところによれば,被上告人甲は,上告人の本件不法行為により顔面に傷害を受けた結果,判示のような外傷後遺症の症状となり果ては医療によって除去しえない著明な瘢痕を遺すにいたり,ために同女の容貌は著しい影響を受け,他面その母親である被上告人乙は,夫を戦争で失い,爾来自らの内職のみによって右甲外一児を養育しているのであり,右不法行為により精神上多大の苦痛を受けたというのである。ところで,民法七〇九条,七一〇条の各規定と対比してみると,所論民法七一一条が生命を害された者の近親者の慰籍料請求につき明文をもって規定しているとの一事をもって,直ちに生命侵害以外の場合はいかなる事情があってもその近親者の慰籍料請求権がすべて否定されていると解しなければならないものではなく,むしろ,前記のような原審認定の事実関係によれば,被上告人乙はその子の死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛を受けたと認められるのであって,かゝる民法七一一条所定の場合に類する本件においては,同被上告人は,同法七〇九条,七一〇条に基いて,自己の権利として慰籍料を請求しうるものと解するのが相当である。されば,結局において右と趣旨を同じうする原審の判断は正当であり,所論は採用できない。
同第二点及び第三点について。
原審は,本件事故発生当時の情況に関する認定事実と挙示の証拠とを綜合し,被害者である被上告人甲の当時の年令をも斟酌して,同女の過失を認めなかったのであり,同女が責任能力を欠いていることを理由にその過失を否定したものではないから,その責任能力の有無につき判示する必要はないものというべきである。右原審の判示に経験則違背の違法は認められないし,また,右の判示により,同女の監督義務者である被上告人乙の過失を肯定する余地のないことも明らかであるから,原審が被害者の過失を斟酌しなかったのはもとより当然であり,所論はすべて採用できない。同第四点について。所論は,上告人に対する原判決を攻撃するものではなく,上告適法の理由とはなし得ないから,採用に値しない。よって,民訴四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官河村又介,同島 保,同垂水克己
車両損の評価(最判昭和49年4月15日民集28巻3号385頁)
ア交通事故による自動車の損傷につき事故当時の価格と売却代金の差額を損害として請求しうる場合
イ交通事故により損傷を受けた中古車の事故当時における価額評価の基準
主 文
原判決中上告人敗訴部分を破棄し,右部分につき本件を札幌高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人猪股貞雄の上告理由について。
思うに,交通事故により自動車が損傷を被った場合において,被害車輛の所有者が,これを売却し,事故当時におけるその価格と売却代金との差額を事故と相当因果関係のある損害として加害者に対し請求しうるのは,被害車輛が事故によって,物理的又は経済的に修理不能と認められる状態になったときのほか,被害車輛の所有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むものと解すべきであるが,被害車輛を買替えたことを社会通念上相当と認めうるがためには,フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められることを要するものというべきである。
また,いわゆる中古車が損傷を受けた場合,当該自動車の事故当時における取引価格は,原則として,これと同一の車種・年式・型,同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべきであり,右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によって定めることは,加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のないかぎり,許されないものというべきである。
しかるに,原判決は,
(一) 本件事故によって被害車輛が修理不能な状態になったとはいえない事実を確定したに止まり,客観的に被害車輛のいかなる部分にどのような損傷が生じたかを何ら具体的に確定することなく,被上告人が被害車輛を買替えたことによって被った損害は,本件事故と相当因果関係があると解するのが相当である,とし,
(二) また,被害車輛の事故当時の取引価格については,前示の特段の事情につき何ら判断することなく,これを定率法によって算定したに止まらず,自動車は登録されるとそれだけで約二〇パーセント価額が減額されるとの経験則の存在を認定し,しかも,被害車輛が新車として購入されたのち,本件事故当時まで三カ月半使用され走行距離も三九七二キロメートルに達している事実,すなわち,被害車輛は事故当時すでに中古車と認めるべき状態にあったことを認めながら,何ら首肯するに足りる理由を付することなく,右経験則を適用しないで,被害車輛の事故当時の取引価格を,新車購入代金五九万二〇〇〇円から定率法による減価償却額六万二五五五円等を控除した残額五二万四四四五円相当である,と判断している。
しかしながら,右各判断は,不法行為に基づく損害賠償額算定に関する法の解釈を誤り,ひいては審理不尽,理由不備又は理由そごの違法をおかしたものというべく,この違法をいう論旨は理由があり,原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして本件は,叙上の点についてさらに審理を尽す必要があるから,これを原審に差し戻す。
よって,民訴法四〇七条一項に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官大塚喜一郎,裁判官,同原昌男,同小川信雄,同吉田 豊
示談当時予想しなかった後遺症(最判昭和43年3月15日民集22巻3号587頁)
示談当時予想しなかった後遺症等が発生した場合と示談における賠償請求権放棄約款の効力
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人信正義雄の上告理由について。
一般に,不法行為による損害賠償の示談において,被害者が一定額の支払をうけることで満足し,その余の賠償請求権を放棄したときは,被害者は,示談当時にそれ以上の損害が存在したとしても,あるいは,それ以上の損害が事後に生じたとしても,示談額を上廻る損害については,事後に請求しえない趣旨と解するのが相当である。
しかし,本件において原判決の確定した事実によれば,被害者甲は昭和三二年四月一六日左前腕骨複雑骨折の傷害をうけ,事故直後における医師の診断は全治一五週間の見込みであったので,甲自身も,右傷は比較的軽微なものであり,治療費等は自動車損害賠償保険金で賄えると考えていたので,事故後一〇日を出でず,未だ入院中の同月二五日に,甲と上告会社間において,上告会社が自賠責保険金(一〇万円)を甲に支払い,甲は今後本件事故による治療費その他慰藉料等の一切の要求を申し立てない旨の示談契約が成立し,甲は右一〇万円を受領したところ,事故後一か月以上経ってから右傷は予期に反する重傷であることが判明し,甲は再手術を余儀なくされ,手術後も左前腕関節の用を廃する程度の機能障害が残り,よって七七万余円の損害を受けたというのである。
このように,全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて,早急に小額の賠償金をもって満足する旨の示談がされた場合においては,示談によって被害者が放棄した損害賠償請求権は,示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべきであって,その当時予想できなかった不測の再手術や後遺症がその後発生した場合その損害についてまで,賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは,当事者の合理的意思に合致するものとはいえない。これと結局同趣旨に帰する原判決の本件示談契約の解釈は相当であって,これに所論の違法はない。 論旨は採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官奥野健一,裁判官草鹿浅之介,同城戸芳彦,同石田和外,同色川幸太郎
代車料(最判昭和33年7月17日民集12巻12号1751頁)
特別の事情によって生じた損害ではない
原判決は,その理由において,被控訴会社(上告会社)代理人主張の本件自動車の休車による得べかりし利益の喪失即ち消極的損害は,所謂特別の事情により生ずべき損害と解すべきものであるとし,そして,本件自動車に電車を追突せしめた控訴会社(被上告会社)の使用人たる電車運転手甲が,右衝突当時,右の特別事情を予見しまたは予見することができた筈であることを推認または肯認することはできないと判断して,被控訴会社(上告会社)代理人が右消極的損害につき主張するところは,その他の点を判断するまでもなく失当である旨を判示している。
しかし,原審の確定したところによれば,右消極的損害は,昭和23年9月10日午后8時前後頃,控訴会社(被上告会社)の使用人である電車運転手甲が控訴会社(被上告会社)所有の電車を運転し,福井新駅を発車して次の藤島神社前停留場に向う途中,通称「木田4辻の線路のカーブ」の部分を通過してから後,右甲の過失によって,その電車を被控訴会社(上告会社)所有の貨物自動車に追突するに至らしめ,その結果右自動車が損傷を蒙むるに至ったものであって,前記消極的損害は,右のごとく,被控訴会社(上告会社)の自動車が右衝突により損傷を蒙ったため,これを休車としたことによる得べかりし利益の喪失であり,そして原審が引用した第1審判決事実摘示によれば,被控訴会社(上告会社)代理人は,本件自動車は,右衝突の日の翌日たる昭和23年9月11日より同24年1月10日迄休車し,翌1月11日より同年3月1日までの間において修繕したのであるが,当時貨物自動車を使用すれば少くとも1日金2,000円の純益があり,被控訴会社(上告会社)は,右衝突がなかったとすれば,同年9月11日から同年12月31日までの間の中70日以上は右自動車を使用し得た筈であって,これによれば合計14万円の得べかりし利益を喪失しているのであるから,その中金92,850円の損害賠償を求めると主張するのである。
しからば,右本件自動車の休車による得べかりし利益の喪失即ち消極的損害は,これにつき被控訴会社(上告会社)代理人が原審において主張した請求の中には,特段の事情の認められない限り,少くともその一部に,通常生ずべき損害を包含しているものと解するを相当とする。しかるに,原審は右消極的損害のすべてにつき,漫然これを特別の事情により生ずべき損害と解すべきものであると判示したことは,経験則に反し,審理不尽,理由不備のそしりを免れない。この点において論旨は理由があり,原判決はこれを破棄し,本件を原審に差し戻す。
よつて,その他の論旨に対する判断を省略し,民訴407条により,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官入江俊郎 裁判官下飯坂潤夫 裁判官斎藤悠輔は出張につき署名押印することができない。 裁判長裁判官 入江俊郎
逸失利益
交通事故損害賠償における逸失利益に関する重要裁判例(最高裁判所判決等)を実装しました。
労働能力減少と実害不発生(最判昭和42年11月10日民集21巻9号2352頁)
労働能力が減少しても具体的に損害が発生していないとされた事例
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人上田明信,同中村盛雄,同高橋正の上告理由について。
交通事故による傷害のため,労働力の喪失・減退を来たしたことた理由として,将来得べかりし利益喪失による損害を算定するにあたって,上告人の援用する労働能力喪失率が有力な資料となることは否定できない。しかし,損害賠償制度は,被害者に生じた現実の損害を填補することを目的とするものであるから,労働能力の喪失・減退にもかかわらず損害が発生しなかった場合には,それを理由とする賠償請求ができないことはいうまでもない。原判決の確定した事実によれば,甲は本件交通事故により左太腿複雑骨折の傷害をうけたが,その後従来どおり会社に勤務し,従来の作業に従事し,本件事故による労働能力の減少によって格別の収入減を生じていないというのであるから,労働能力減少による損害賠償を認めなかった原判決の判断は正当であって,所論の判例に反するところもない。論旨は採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁 裁判長裁判官 奥野健一,裁判官草鹿浅之介,同城戸芳彦 ,同石田和外,同色川幸太郎
労働能力減少と実害不発生(最判昭和56年12月22日民集35巻9号1350頁)
身体的機能の一部喪失と労働能力喪失を理由とする財産上の損害の有無
主 文
原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人佐々木鉄也,同大友秀夫の上告理由について
原審は,(1) 被上告人は,昭和四七年三月一一日,本件交通事故によって右手,右臀部に加療五日間を要する挫傷を受け,昭和五〇年一月一〇日までの約二年一〇か月にわたる通院治療の結果,身体障害等級一四級に該当する腰部挫傷後遺症を残して症状が固定し,右下肢に局部神経症状があるものの,上,下肢の機能障害及び運動障害はないとの診断を受けたこと,(2) 右後遺症は多分に心因性のものであると考えられること,(3) 被上告人は,通産省工業技術院繊維高分子材料研究所に技官として勤務し,本件事故前はかなり力を要するプラスチック成型加工業務に従事していたが,本件事故後は腰部痛及び下肢のしびれ感があって従前の仕事がやりづらいため,坐ったままでできる測定解析業務に従事するようになったこと,(4) しかし,本件事故後も給与面については格別不利益な取扱は受けていないこと,などの事実関係を確定したうえ,事故による労働能力の減少を理由とする損害を認定するにあたっては,事故によって生じた労働能力喪失そのものを損害と観念すべきものであり,被害者に労働能力の一部喪失の事実が認められる以上,たとえ収入に格別の減少がみられないとしても,その職業の種類,後遺症の部位程度等を総合的に勘案してその損害額を評価算定するのが相当であるとの見解に基づいて,右事実関係及び労働省労働基準局長通牒(昭和三二年七月二日付基発五五一号)による労働能力喪失率表を参酌のうえ,被上告人は,本件交通事故に基づく前記後遺症のため労働能力の二%を喪失したものであり,その喪失期間は右事故後七年間と認めるのが相当であるとして,被上告人の年収を基準とする右割合及び期間による三四万一二一六円の財産上の損害を認定している。
しかし,仮に交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても,その後遺症の程度が比較的軽微であって,しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては,特段の事情のない限り,労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はない。
ところで,被上告人は,研究所に勤務する技官であり,その後遺症は身体障害等級一四級程度のものであって右下肢に局部神経症状を伴うものの,機能障害・運動障害はなく,事故後においても給与面で格別不利益な取扱も受けていないというのであるから,現状において財産上特段の不利益を蒙っているものとは認め難いというべきであり,それにもかかわらずなお後遺症に起因する労働能力低下に基づく財産上の損害があるというためには,たとえば,事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであって,かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合とか,労働能力喪失の程度が軽微であっても,本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし,特に昇給,昇任,転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合など,後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情の存在を必要とするというべきである。原審が以上の点について何ら審理を遂げることなく,右後遺症の存在のみを理由にこれによる財産上の損害を認めている点で,原判決には損害認定に関する法令の解釈,適用の誤り,ひいては審理不尽,理由不備の違法があるといわざるをえず,論旨は理由がある。そして,被上告人の本訴請求は,同一の交通事故によって生じた身体障害に基づく損害の賠償を請求するものであって,各費目別の損害額は相互に密接に関連し,上告人の本件上告も右の趣旨で原判決全部の破棄を求めるものと解しえないではないから,原判決中,上告人敗訴部分は,結局,その全部の破棄を免れない。そして,叙上の点を含め,さらに本件損害賠償額について審理を尽くす必要があるから,右破棄部分につき本件を原審に差し戻すのが相当である。
よって,民訴法四〇七条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官 横井大三 ,裁判官同環 昌一,同伊藤正己,同寺田治郎
幼児の逸失利益の算定(最判昭和39年6月24日民集18巻5号874頁)
事故により死亡した幼児の得べかりし利益の算定は可能か
上告代理人三宅厚三の上告理由第1点について。
(1) 上告人らは,論旨1,において,総論的に,本件のごとく被害者が満8才の少年の場合には,将来何年生存し,何時からどのような職業につき,どの位の収入を得,何才で妻を迎え,子供を何人もち,どのような生活を営むかは全然予想することができず,従って「将来得べかりし収入」も,「失うべかりし支出」も予想できないから,結局,「得べかりし利益」は算定不可能であると主張する。なるほど,不法行為により死亡した年少者につき,その者が将来得べかりし利益を喪失したことによる損害の額を算定することがきわめて困難であることは,これを認めなければならないが,算定困難の故をもって,たやすくその賠償請求を否定し去ることは妥当なことではない。何故なら,これを否定する場合における被害者側の救済は,主として,精神的損害の賠償請求,すなわち被害者本人の慰謝料(その相続性を肯定するとして)又は被害者の遺族の慰謝料(民法711条)の請求にこれを求めるほかはないこととなるが,慰謝料の額の算定については,諸般の事情が斟酌されるとはいえ,これらの精神的損害の賠償のうちに被害者本人の財産的損害の賠償の趣旨をも含ませること自体に無理があるばかりでなく,その額の算定は,結局において,裁判所の自由な裁量にこれを委ねるほかはないのであるから,その額が低きに過ぎて被害者測の救済に不十分となり,高きに失して不法行為者に酷となるおそれをはらんでいることは否定しえないところである。従って,年少者死亡の場合における右消極的損害の賠償請求については,一般の場合に比し不正確さが伴うにしても,裁判所は,被害者側が提出するあらゆる証拠資料に基づき,経験則とその良識を十分に活用して,できうるかぎり蓋然性のある額を算出するよう努め,ことに右蓋然性に疑がもたれるときは,被害者側にとって控え目な算定方法(たとえば,収入額につき疑があるときはその額を少な目に,支出額につき疑があるときはその額を多めに計算し,また遠い将来の収支の額に懸念があるときは算出の基礎たる期間を短縮する等の方法)を採用することにすれば,慰謝料制度に依存する場合に比較してより客観性のある額を算出することができ,被害者側の救済に資する反面,不法行為者に過当な責任を負わせることともならず,損失の公平な分担を窮極の目的とする損害賠償制度の理念にも副うのではないかと考えられる。要するに,問題は,事案毎に,その具体的事情に即応して解決されるべきであり,所論のごとく算定不可能として一概にその請求を排斥し去るべきではない。
(2) よって,以上の観点に立ちながら,進んで,上告人らが,論旨2,以下において各論的に,原判決の算定方法の違法を主張する諸点につき判断することとする。
(い) 上告人らは,まず,原審が,統計表に基づいて余命年数を求め,20才から55才まで35年間を稼働可能期間とし,国民の収入及び支出の平均又は標準を示すものとは認められない判示諸表によって「得べかりし収入」と「失うべかりし支出」を想定して「得べかりし利益」を算出しているのは不合理であると主張する。
(イ) 稼働可能期間について。
しかしながら,原審は,本件被害者らは,本件事故当時満8才余の普通健康体を有する男子であること,判示統計表により同人らの通常の余命は57年6月余であり,20才から少くとも55才まで35年間は稼働可能であることを認定しているのであり,右認定は,平均年令の一般的伸長,医学の進歩,衛生思想の普及という顕著な事実をも合せ考えれば,相当としてこれを肯認することができ,この点に所論のごとき不合理は認められない。
(ロ) 収入額について。
つぎに,原審は,本件被害者らは,右稼働可能期間中,毎年,判示証拠資料により認めうる昭和33年4月から9月までの間のわが国における通常男子の1ヵ月の平均労働賃金2万648円,元年分にして24万7776円の金額を下らない収入を得べきものと推認し,その年収額から後出の支出年額を控除した額を基準としてホフマン式計算方法による1時払いの損害額を算出しているのであるが,被害者らがいかなる職業につくか予測しえない本件のごとき場合においては,通常男子の平均労賃を算定の基準とすることは,将来の賃金ベースが現在より下らないということを前提にすれば,1応これを肯認しえないではないが,収入も1応安定した者につき,将来の昇給を度外視した控え目な計算方法を採用する場合とは異なり,本件のごとき年少者の場合においては,初任給は平均労賃よりも低い反面,次第に昇給するものであることを考えれば,35年間を通じてその年収額を右平均労賃と同額とし,これを基準にホフマン式計算方法により一時払いの額を求めている原審の算出方法は,これを肯認するに足る別段の理由が明らかにされないかぎり,不合理というほかはないところ,原判決はこの点につきなんら説明するところがないので,少くとも右の点において原判決には理由不備の違法があるものといわなければならない。
(ハ) 支出額について。
(甲) 原審は,本件被害者らの稼働可能期間中における毎年の生活費は,判示証拠資料により認めうる昭和33年度における勤労者の平均世帯(世帯員数4・46人)の実支出額1カ月3万638円,1人平均6869円,その元年分である8万2428円と同額と認めるのを相当としているところ,上告人らは,本件被害者らは何時結婚し,何人の子供をもち,いかなる生活を営むか不明であるばかりでなく,世帯主の生活費は他の世帯員のそれより多いことは経験則上顕著であるから,世帯の支出額を均分したものを世帯主と認められる被害者らの生活費とすることは不合理であると主張する。ところで,被害者らが独身で生活するという特別の事情が認められない本件のごとき場合においては,平均世帯を基準として被害者ら各自の生活費を算出すること自体は,一応これを肯認しえないではないが,原判決が,首肯するに足る理由をなんら示すことなく,右35年間を通じて被害者らの生活費が昭和33年度の前示生活費と同額であるとしていること,及び前示世帯の支出額を世帯員数で均分したものが被害者ら(男子であり,世帯主となるものと推認される)の生活費であるとしているのは,理由不備の違法があるものといわなければならない。
(乙) 上告人らは,さらに,論旨2の後段において,被害者らの収入からは,被害者本人の生活費のみならず,被害者らの負担すべき扶養家族の生活費をも控除すべきであると主張するが,収入から被害者本人の生活費を控除するのは,本人の生活費は,1応,収入を得るために必要な支出と認められるからであるが(収入を失うことによる損失と支出を免れたことによる利益の間には直接の関係がある),扶養家族の生活費の支出と被害者本人の収入の間には右のごとき関係はなんら認められないのであるから,扶養家族の生活費の額は,収入額からこれを控除すべきではなく,この点に関する原判旨は,簡に失しているが,結論において正当であり,所論は採用し難い。
(丙) 上告人らは,また,論旨3において,被害者らの得べかりし収入額から,稼働可能期間経過後(55才より後)に被害者らが支出すべかりし生活費を控除すべきであると主張するが,右支出も前記収入と前述のごとき直接の関係に立つものでないばかりでなく,55才を超えても無収入であるとはかぎらず,また,第3者による扶養もありうることであるから,その間の生活費を前記収入から当然に控除しなければならない理由はない(20才までの期間における生活費についても同様であり,上告人らも右生活費を右の意味において控除すべしとは主張していない)。この点に関する原判旨もまた簡に失しているが,結局において正当であり,所論は採用しえない。
(丁) 上告人らは,さらに20才ないし55才を基準として損害額を算定すれば,1才の幼児が死亡した場合と18・9才の青年が死亡した場合とでは,その「得べかりし利益」は同額となり,25・6才以上の成年が死亡した場合のそれは,1才の幼児が死亡した場合のそれより少額となって不合理であると主張するが,所論は,ホフマン式計算方法を度外視し,かつ,稼働可能期間の長短を忘れた議論であり,採用のかぎりでない。
(戊) 上告人らは,また,論旨3において,本件損害賠償請求権を相続した被上告人らは,他面において,被害者らの死亡により,その扶養義務者として当然に支出すべかりし20才までの扶養費の支出を免れて利得をしているから,損益相殺の理により,賠償額から右扶養費の額を控除すべきであると主張するが,損益相殺により差引かれるべき利得は,被害者本人に生じたものでなければならないと解されるところ,本件賠償請求権は被害者ら本人について発生したものであり,所論のごとき利得は被害者本人に生じたものでないことが明らかであるから,本件賠償額からこれを控除すべきいわれはない。所論は,採用に価しない。
(ろ) なお,上告人らは,論旨4において,原判決のホフマン式計算方法の適用の誤りを主張するが,不法行為による損害賠償の額は,不法行為時を基準として算定するのを本則とするのであるから,原審が,ホフマン式計算方法を適用するについて本件事故の時を基準とし,その時における一時払いの額を算出したのは正当である。所論は,畢竟,独自の見解の下に原判決を非難するものであり,採用のかぎりでない。
(3) 以上,要するに,本訴請求中,得べかりし利益の喪失による損害の賠償を求める部分については,原判決に少くとも前示のごとき諸点につき理由不備の違法があることが明らかであり,所論は,結局において理由があるので,原判決は,右限度において破棄を免れない。
同第2点について。
上告人らは,原判決が損害額を算定するにつき,被上告人らの監督義務者としての過失を斟酌しなかったのは違法であると主張するが,原審認定の事実関係の下においては,被上告人らに監督上の過失が認められないとした原審の判断は,これを肯認しえないではない。所論は,畢竟,原審の認定しない事実に基づき又は独自の見解の下に,原判決を論難するに過ぎないものであり,採用し難い。
よって,民訴407条,396条,384条,95条,93条,89条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官横田正俊,裁判官同石坂修一,同五鬼上堅磐,同柏原語六,同田中二郎
将来の昇給見込みと逸失利益(最判昭和43年8月27日民集22巻8号1704頁)
死者の得べかりし利益の喪失による損害額の認定にあたり,将来の昇給の見込を斟酌することが許される事例
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人山口伸六の上告理由について。
不法行為によって死亡した者の得べかりし利益を喪失したことによる損害の額を認定するにあたっては,裁判所は,あらゆる証拠資料を総合し,経験則を活用して,でき得るかぎり蓋然性のある額を算出するよう努めるべきであり,蓋然性に疑いがある場合には被害者側にとって控え目な算定方法を採用すべきであるが,ことがらの性質上将来取得すべき収益の額を完全な正確さをもって定めることは不可能であり,そうかといって,そのために損害の証明が不可能なものとして軽々に損害賠償請求を排斥し去るべきではないのであるから,客観的に相当程度の蓋然性をもって予測される収益の額を算出することができる場合には,その限度で損害の発生を認めなければならないものというべきである。そして,死亡当時安定した収入を得ていた被害者において,生存していたならば将来昇給等による収入の増加を得たであろうことが,証拠に基づいて相当の確かさをもって推定できる場合には,右昇給等の回数,金額等を予測し得る範囲で控え目に見積って,これを基礎として将来の得べかりし収入額を算出することも許される。
本件において,原判決は,亡甲が勤務先の訴外会社から死亡当時受けていた給与は,基本給のほか,その額を基礎として一定比率で定められる第一加給,第二加給,時間外勤務手当,割増賃金ならびに定額である地域手当から成っていたことを認定し,将来における右の内容の給与と同会社から受けるべき賞与及び退職金の金額を推算して,損害を認定しているのであるから,各項目についてその算定方法の当否を検討する。
まず,基本給については,右会社に勤務する右甲と同程度の学歴,能力を有する者について昭和二九年度から同三二年度まで四年間の毎年の現実の昇給率を認定し,甲が死亡の前月に受けた基本給の額三〇八〇円を基準として,右各年度において右と同一の率をもって逐次昇給し得たものとして同人のその間の得べかりし基本給の額を算定し,昭和三三年度以後同人が満四四才に達する同五〇年度までは右四年間の昇給率の平均値である七・七七五パーセントの割合をもって毎年昇給を続けるものとしてその間の基本給の額を算出し,さらにそれ以後満五五才に達するまではこれを下廻る毎年五パーセントの昇給率をもって昇給するものとしているのであって,甲が生存していた場合にこのようにして昇給することは,確実であるとはいえないにしても,相当程度の蓋然性があるものと認められないことはなく,このような平均値的な昇給率によって予測された昇給をしんしやくして将来の収入を定めることは,なお控え目な算定方法にとどまるものとして是認できる。
次に,右のように算定した基本給の額を基準にし,一か月につき二五日出勤した場合に基本給の八〇パーセントが支給される第一加給を将来の収入の基礎としているのであるが,一か月に二五日ずつの勤務を長期間継続することは,確実であるとはいえないにしても,将来の収入を予測する一つの基準として採ることができないものではなく,この点の原判決の判断に違法があるとはいえない。
従って,基本給の額またはこれと右第一加給の額とを基準にして一定比率で定められる第二加給,時間外勤務手当及び割増賃金の算定方法も,正当なものとして是認することができ,なお定額である地域手当についてはその取得の蓋然性を疑う余地はない。
次に,賞与については,前示基本給と同様,前示会社に勤務する甲と同程度の学歴,能力を有する者に対し昭和二九年から同三一年までの間六回に現実に支給された賞与の額の基本給に対する比率に基づき,甲にも右期間同一の比率による賞与が支給されるはずであったものとしてその額を算定し,昭和三二年から甲が満五五才に達するまでは,右六回の比率の平均値の二回分である基本給の六二三パーセントずつの賞与が毎年支給されるものとして計算し,このようにして算出された金額は昭和三二年度以後において甲と同程度の者に実際に支給されている賞与の額に比較してもはるかに少額である旨を認定しているのであり,なお,基本給は給与の一部にすぎない前示のような金額であるため,右に算出された賞与の額は,社会通念上も不相当に高額に失することにはならないものと認められるのであるから,以上のような算定方法も控え目なものということができる。
さらに,退職金については,前示会社における従業員退職規程に基づき基本給に対する所定比率をもってその額を算定しているのであって,基本給の額が前記のように正当に認定されている以上,この算定方法には十分な客観性が認められるところである。
最後に,甲が満五五才で前示会社を停年退職したのち統計上の就労可能年令である満六〇才に達するまでは,右停年時に得ていた収入の半額の収入が得られるものとしているのであって,その程度の収入が得られる蓋然性があることは経験則上肯定することができる。
以上にみたとおり,原判決が算定した甲の将来の収入の額は控え目な金額であって,これを得べかりし蓋然性があるものということができる。従って,原判決の判断に所論の違法はなく,論旨は採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官 横田正俊,裁判官田中二郎,同下村三郎,同松本正雄 ,同飯村義美
妻の家事労働(最判昭和50年7月8日裁判集民事115号257頁)
妻の家事労働が財産上の利益を生ずるものであり,これを金銭的に評価することが不可能といえない
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人千葉保男,同上野伊知郎の上告理由第一,一について。
所論の点に関する原審の認定判断は,原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠関係に照らし,正当として是認することができ,その過程に所論の違法はない。論旨は,結局,独自の見解又は原審の認定にそわない事実に基づき原判決を非難するにすぎず,採用することができない。
同二について。
妻の家事労働が財産上の利益を生ずるものであり,これを金銭的に評価することが不可能といえないことは,当裁判所判例(昭和四四年(オ)第五九四号同四九年七月一九日第二小法廷判決・民集二八巻五号八七二頁)の示すとおりである。これと同旨の見解に立って,被上告人が本件事故による負傷のため家事労働に従事することができなかった期間について財産上の損害を被ったものとした原審の判断は,正当として是認することができ,原判決に所論の違法はない。論旨は,結局,独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず,採用することができない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官 天野武一 裁判官 関根小郷 裁判官 坂本吉勝 裁判官 江里口清雄 裁判官 高辻正己
家事専念期間の損害と逸失利益(最判昭和49年7月19日民集28巻5号872頁)
ア妻として家事専念期間における財産上の損害
イ同家事専念期間における逸失利益の算定基準
主 文
原判決中上告人らの敗訴部分を破棄する。
右部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人小林勇の上告理由第一点について。
所論の点に関する原審の認定判断は,原判決挙示の証拠に照らし,正当として是認することができ,その過程に所論の違法はない。論旨は,採用することができない。
同第二点について。
原判決は,亡甲が本件事故に因り死亡しなかったとすれば,同人は高等学校を卒業して就職し,二五歳に達したときに結婚して離職するものと推定したうえ,同人の死亡に因る財産的損害の額を認定するにあたり,結婚後の損害額を全く算定していない。したがって,原審は,結婚して家事に専念する女子が死亡した場合には,財産的損害を生じないものと解したことは,所論のとおりである。
おもうに,結婚して家事に専念する妻は,その従事する家事労働によって現実に金銭収入を得ることはないが,家事労働に属する多くの労働は,労働社会において金銭的に評価されうるものであり,これを他人に依頼すれば当然相当の対価を支払わなければならないのであるから,妻は,自ら家事労働に従事することにより,財産上の利益を挙げているのである。一般に,妻がその家事労働につき現実に対価の支払を受けないのは,妻の家事労働が夫婦の相互扶助義務の履行の一環としてなされ,また,家庭内においては家族の労働に対して対価の授受が行われないという特殊な事情によるものというべきであるから,対価が支払われないことを理由として,妻の家事労働が財産上の利益を生じないということはできない。のみならず,法律上も,妻の家計支出の節減等によって蓄積された財産は,離婚の際の財産分与又は夫の死亡の際の相続によって,妻に還元されるのである。
かように,妻の家事労働は財産上の利益を生ずるものというべきであり,これを金銭的に評価することも不可能ということはできない。ただ,具体的事案において金銭的に評価することが困難な場合が少くないことは予想されうるところであるが,かかる場合には,現在の社会情勢等にかんがみ,家事労働に専念する妻は,平均的労働不能年令に達するまで,女子雇傭労働者の平均的賃金に相当する財産上の収益を挙げるものと推定するのが適当である。
してみると,原判決には右の点において民法七〇九条の解釈,適用を誤った違法があり,その違法は結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由があるから,原判決中上告人らの敗訴部分は破棄を免れず,更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻す必要がある。
よって,民訴法四〇七条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官 吉田 豊,裁判官岡原昌男,同小川信雄,同大塚喜一郎
逸失利益と生活費割合(最判昭和43年12月17日裁判集民事93号677頁)
逸失利益の算定にあたり生活費が全稼動期間を通じて収入の5割を超えないものとされた事例
上告代理人近藤新の上告理由一,1及び3について。
本件の被害者Xの学歴等原審の認定した諸般の事情に徴し,かつ被害者の得べかりし利益を算定するにあたり控除すべき被害者の生活費とは,被害者自身が将来収入を得るに必要な再生産の費用を意味するものであって,家族のそれを含むものではないことに鑑みれば,被害者Xの得べかりし利益を算定するにあたり控除すべき同人の生活費が,その全稼働期間を通じ,収入の五割を越えないとする原審の判断は不当とはいえない。従って,論旨は採用できない。
同一,2について。
原審の確定するところによれば,被害者Xは本件事故当時郷里を離れ,名古屋市の大学に在学中であったというのであり,その父親である被上告人夫婦は大分県下で醤油,茶の小売販売を営む傍ら農業に従事していたというのであるから,同人が大学卒業後特に郷里に戻ることを認めるに足りる特段の事情のない本件においては,同人の将来得べかりし収入を算定するにあたって,特に大分県下の平均収入を基礎とする必要はなく,労働大臣官房統計調査部編さんの「昭和四一年賃金構造基本統計調査報告」による新制大学卒業者の給与の統計によって,その収入を算定した原審の判断に所論の違法はない。また,右収入が勤続年数によって異なるのも右統計の示すところであるから,原審が右Xの将来得べかりし収入を算定するにあたり,各年令層別の給与額を基礎としたことは相当である。なお,Xの大学卒業年度の収入の計算については,被上告人の本訴請求が原審の認定する得べかりし利益の総額に比して少ない一部請求であることに鑑み,所論の点がなんら原審の結論に影響を及ぼさないことは計数上明らかであるから,この点についての所論は採用に値しない。
以上,原判決に所論の違法はなく,論旨はすべて採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官横田正俊,同田中二郎,同下村三郎,同松本正雄,同飯村義美
就労前の年少女子の逸失利益(最判昭和62年1月19日民集41巻1号1頁)
就労前の年少女子の得べかりし利益の喪失による損害賠償額を女子労働者の平均給与額によって算定する場合と家事労働分の加算の可否
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人小笠原稔の上告理由について
所論は,要するに,亡X(本件事故当時満一四歳の女子で中学二年生。以下「X」という。)の将来の得べかりし利益の算定に当たっては,女子労働者の平均賃金と男子労働者の平均賃金との間には著しい格差があるので,これを是正するため,女子労働者の平均賃金を基準として算定された収入額に家事労働分を加算すべきであるというものである。
Xのような死亡時に現実収入のない就労前の年少女子の場合には,当該女子の将来の就労の時期,内容,程度及び結婚後の職業継続の有無等将来につき不確定な要因が多いのであるが,原審が,Xの将来の得べかりし利益の喪失による損害賠償額を算定するに当たり,賃金センサス昭和五六年第一巻第一表中の女子労働者,旧中・新高卒,企業規模計(パートタイム労働者を除いたもの)の表による平均給与額を基準として収入額を算定したことは,交通事故により死亡した女子の将来の得べかりし利益の算定として不合理なものとはいえず(最高裁昭和五四年(オ)第二一四号同年六月二六日判決・裁判集民事一二七号一二九頁,同昭和五六年(オ)第四九八号同年一〇月八日判決裁判集民事一三四号三九頁参照),Xが専業として職業に就いて受けるべき給与額を基準として将来の得べかりし利益を算定するときには,Xが将来労働によって取得しうる利益は右の算定によって評価し尽くされることになると解するのが相当であり,従って,これに家事労働分を加算することは,将来労働によって取得しうる利益を二重に評価計算することに帰するから相当ではない。そして,賃金センサスに示されている男女間の平均賃金の格差は現実の労働市場における実態を反映していると解されるところ,女子の将来の得べかりし利益を算定するに当たって,予測困難な右格差の解消ないし縮少という事態が確実に生じるものとして現時点において損害賠償額に反映させ,これを不法行為者に負担させることは,損害賠償額の算定方法として必ずしも合理的なものであるとはいえない。従って,Xの得べかりし利益を算定するにつき,Xの受けるべき給与額に更に家事労働分を加算すべきではないとした原審の認定判断は,正当として是認できる。
また,所論は,原審のした慰謝料額の算定をも非難するが,原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて原審の算定した慰謝料の額が不当なものであるということはできない。原判決に所論の違法はなく,右の判断は所論引用の判例に抵触するものでもない。論旨は,違憲の主張を含め,独自の見解に基づいて,原判決の損害賠償額算定の違法をいうものにすぎず,採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条,九三条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官島谷六郎,裁判官牧 圭次,同藤島 昭,同香川保一,同林 藤之輔
逸失利益の不確定は不許(最判昭和44年12月23日裁判集民事97号921頁)
事故死の被害者の喪失する将来得べかりし利益を確定することができないとした判断と経験則違背の有無
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人木原鉄之助の上告理由第一点について。
原審の適法に確定した原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ)判示の事実関係のもとにおいて,訴外Xの本件事故死については同人自身にも過失があった,とした原審の認定判断は,肯認することができないわけではない。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用できない。
同第二点について。
原審の確定した原判示の事実関係,とくに,訴外X本件事故死の当時同人自身の生活費として一か月に少なくとも金八,二五〇円を要したものであるところ,同人は病弱にして勤労意欲に乏しく,かつ,昼間から飲酒にふけることもあって,同人の右事故死の当時の収入額は右生活費の金額にも満たなかった,という事実関係は,挙示の証拠関係に照らして,首肯することがでないきわけではない。そして,右事実関係のもとにおいて,右Xが右事故死の結果喪失した将来得べかりし利益の存在ないし金額はたやすく認定することができない,とした原審の判断は,正当として是認できないわけではない。原判決に所論の違法はなく,論旨は,畢竟,原審の適法にした証拠の取捨判断及び事実の認定を争い,または,原審の認定にそわない事実関係を前提として原判決を非難するものにすぎず,採用できない。
同第三点及び第五点について。
訴外Xの本件事故死による上告人甲及び上告人乙の右訴外人に対する扶養請求権の喪失,または,右事故死による上告人丙のその余の上告人両名に対する扶養責任の加重は,いずれも右訴外人が右事故死の当時将来上告人甲及び上告人乙を現実に扶養しうる能力を有していたことを前提とすると解すべきところ,右訴外人が右事故死の当時そのような能力を有していた事実ないしその能力の程度を確定することができない,とした原審の認定判断は,挙示の証拠関係に照らし,首肯することができないわけではない。従って,原判決に所論の違法はなく,論旨は,畢竟,原審の適法にした証拠の取捨判断及び事実の認定を非難するものにすぎず,採用できない。
同第四点について。
原審の適法に確定した原判示の事実関係のもとにおいて,訴外Xと上告人丙との間の内縁関係は,右訴外人の本件事故死よりも以前である昭和四〇年九月ごろすでに解消されていた,とした原審の判断は,肯認することができないわけではない。原判決に所論の違法はなく,論旨は,原審の適法にした事実の認定を争い,または,独自の見解を主張するものにすぎず,採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条,九三条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁,裁判長裁判官松本正雄 裁判官田中二郎 同下村三郎 同飯村義美 同関根小郷
逸失利益の計算方法(最判昭和62年12月17日裁判集民事152号281頁)
逸失利益の計算過程・方法
主 文
一1 原判決の上告人ら敗訴部分のうち,(一) 上告人らの本訴請求中,八一万二一九六円及びこれに対する昭和六〇年一月二六日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員の債務不存在確認請求を棄却した部分,(二) 被上告人の反訴請求中,右金員の支払請求を認容した部分について,原判決を破棄し,右各部分に関する被上告人の控訴を棄却する。
2 その余の本件上告を棄却する。
二 本件附帯上告を棄却する。
三1 被上告人は,上告人らに対し,八八万〇九五四円及びこれに対する昭和六一年一〇月九日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
2 上告人らのその余の民訴法一九八条二項の規定による裁判を求める申立を棄却する。
四 訴訟の総費用及び上告人らの民訴法一九八条二項の裁判を求める申立に関して生じた費用は,これを三分し,その二を被上告人,その余を上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人中嶋邦明,同長谷川彰,同若松陽子,同柳村幸宏,同増田勝久の上告理由第二点,第三点について所論の点に関する原審の認定判断は,原判決挙示の証拠関係に照らし,正当として是認することができ,その過程に所論の違法はない。論旨は,畢竟,原審の専権に属する証拠の取捨判断,事実の認定を非難するものにすぎず,採用することができない。
同第一点について
所論の点に関し,原審は,被上告人は第一審判決別紙交通事故による後遺障害のため,同後遺障害が固定した日の翌日である昭和五九年五月一六日から少なくとも三年間はその労働能力を二〇パーセント,その後六年間は同能力を七パーセントそれぞれ喪失するものであることを適法に認定したうえ,右六年間の逸失利益を年別のホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して算定するに当たり,期間六年のホフマン係数五・一三三を使用し(原判決別紙計算表(3)),右逸失利益を七一一万四三三八円であるとした。しかし,前記労働能力を七パーセント喪失する六年間は三年後を始期とするものであるから,右六年間の逸失利益を算定するについて使用するホフマン係数としては,期間九年のホフマン係数七・二七八から期間三年のホフマン係数二・七三一を差し引いた四・五四七の数値を使用すべきであったのであり,同数値を用いて計算すれば,前記逸失利益は六三〇万二一四二円となる。そうすると,原判決には,右逸失利益の算定に関し,七一一万四三三八円から六三〇万二一四二円を控除した差額八一万二一九六円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である昭和六〇年一月二六日から支払ずみまで年五分の割合による金員部分につき,損害賠償額算定に関する法の解釈適用を誤った違法があり,この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由があり,原判決はこの点において破棄を免れない。従って,原判決の上告人ら敗訴部分のうち,(一) 上告人らの本訴請求中,八一万二一九六円及びこれに対する昭和六〇年一月二六日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員の債務不存在確認請求を棄却した部分,(二) 被上告人の反訴請求中,右金員の支払請求を認容した部分に関する被上告人の控訴は,いずれも失当として棄却されるべきものである。
附帯上告代理人中山厳雄の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は,原判決挙示の証拠関係に照らし,正当として是認することができ,その過程に所論の違法はない。論旨は,畢竟,原審の専権に属する証拠の取捨判断,事実の認定を非難するものにすぎず,採用できない。
上告人らの民訴法一九八条二項の規定による裁判を求める申立について
上告人らは,本判決末尾添付の申立書記載のとおり民訴法一九八条二項の裁判を求める申立をし,その理由として陳述した同申立書記載の事実関係は被上告人の争わないところである。そして,原判決中上告人らの敗訴部分のうち八一万二一九六円及びこれに対する昭和六〇年一月二六日から支払ずみまで年五分の割台に上る金員の支払を命じた部分が破棄を免れないことは前記説示のとおりであるから,原判決に付された仮執行宣言が右限度で効力を失うことは論をまたない。従って,右仮執行宣言に基づいて給付した八一万二一九六円とこれに対する昭和六〇年一月二六日以降の遅延損害金六万八七五八円の合計金額八八万〇九五四円及びこれに対する支払の日の翌日である昭和六一年一〇月九日から支払ずみに至るまで民法所定の年五分の割合による損害金の支払を求める上告人らの申立は正当として認容すべきであり,その余の部分の申立は理由がないからこれを棄却すべきである。
よって,民訴法四〇八条,三九六条,三八四条一項,一九八条二項,八九条,九六条,九二条,九三条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官 大内恒夫,裁判官角田禮次郎,同高島益郎,同佐藤哲郎 ,同四ツ谷 巖
扶養者死亡の場合における被扶養者の将来の扶養利益(最判平成12年9月7日裁判集民事199号477頁)
不法行為によって扶養者が死亡した場合における被扶養者の将来の扶養利益喪失による損害額の算定方法
主 文
原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人樋渡俊一の上告受理申立て理由第二点について
一 原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
1 被上告人Pは,昭和五五年一二月九日,Q(昭和三六年二月生)と婚姻し,同人との間に,被上告人R(昭和五八年一月生)及び同S(昭和五九年一一月生)をもうけた。被上告人らは,平成四年当時,その生活をQに依存していたところ,Qは,同年九月八日に殺害されたが,上告人は,右殺害行為の実行前に,その正犯から依頼を受けて偽装工作をすることを約束し,これにより,右殺害行為を容易にした。
2 Qは,平成三年度には七八〇万円の収入を得ていたが,他方,約四八億円の負債を抱えていた。Qの相続人である被上告人らは,相続の放棄をした。
二 本件は,被上告人らが,上告人に対し,Qから受けることができた将来の扶養利益の喪失等の損害についてその賠償を求めるものであるところ,原判決は,前記事実関係の下において,上告人はQの殺害行為の幇助者として不法行為責任を負うとした上で,次のとおり判示して,被上告人らの請求をいずれも認容した。
Qが殺害されることがなければ,被上告人らは,Qの収入の一部を扶養料として享受することができたといえるが,Qの約四八億円にものぼる債務がQ及びその家族である被上告人らの生活に影響を及ぼしたであろうことも否定できないから,扶養権侵害による損害額の算定の基礎としては,死亡時前年度の年収七八〇万円をそのまま用いるのは相当でなく,賃金センサス平成四年第一巻第一表・産業計・企業規模計・学歴計・男子労働者の平均年収額五四四万一四〇〇円を用いるのが相当である。Qは,満六七歳に達するまでの三六年間は就労可能であったものであり,その間は少なくとも右金額程度の収入を得ることができたはずであり,その間の同人の生活費として,同人が世帯主であることを考慮して右収入額の三割を控除し,ライプニッツ方式により中間利息を控除して計算すると,Qの死亡による逸失利益は,六三〇二万六四三〇円となる。そして,被上告人Pは,Qの妻として,その二分の一の三一五一万三二一五円について,また,被上告人R及び同Sは,Qの長女及び二女として,右逸失利益の各四分の一の各一五七五万六六〇七円について,それぞれ扶養利益を喪失したものと認めることができる。
三 しかしながら,原審の扶養利益の喪失による損害額の算定についての右判断は是認できない。その理由は,次のとおりである。
1 不法行為によって死亡した者の配偶者及び子が右死亡者から扶養を受けていた場合に,加害者は右配偶者等の固有の利益である扶養請求権を侵害したものであるから,右配偶者等は,相続放棄をしたときであっても,加害者に対し,扶養利益の喪失による損害賠償を請求することができるというべきである。しかし,その扶養利益喪失による損害額は,相続により取得すべき死亡者の逸失利益の額と当然に同じ額となるものではなく,個々の事案において,扶養者の生前の収入,そのうち被扶養者の生計の維持に充てるべき部分,被扶養者各人につき扶養利益として認められるべき比率割合,扶養を要する状態が存続する期間などの具体的事情に応じて適正に算定すべきものである。
2 これを本件についてみるに,原審は,Qの前記債務の負担状況にかんがみ,扶養利益喪失による損害額の算定に当たり,同人の死亡時前年度の年収七八〇万円をそのまま用いることなく,前記賃金センサスによる平均年収額五四四万一四〇〇円を用いるべきであると判断しているが,Qの債務負担額が約四八億円にも達していることに鑑みると,なおこれを是認することはできない。また,Qの逸失利益全額をそのまま被上告人らの扶養利益の総額とし,これを被上告人らの相続分と同じ割合で分割して,各人の扶養利益の喪失分とした点,並びに被上告人R及び同Sについては,特段の事情がない限り,Qの就労可能期間が終了する前に成長して扶養を要する状態が消滅すると考えられるにもかかわらず,右扶養を要する状態の消滅につき適切に考慮することなく,扶養利益喪失額を認定した点は,前記1に判示した事項を適正に考慮していないといわざるを得ず,扶養利益喪失による損害額の算定につき,法令の解釈適用を誤ったものというべきである。
四 以上のとおり,右に述べた各点について,原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,以上の説示に従い,被上告人らの喪失した扶養利益の額について更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官遠藤光男,裁判官井嶋一友,同藤井正雄,同大出峻郎,同町田 顯
幼児の逸失利益と養育費控除(最判昭和53年10月20日民集32巻7号1500頁)
1,死亡した幼児の財産上の損害賠償額の算定と将来得べかりし収入額から養育費を控除することの可否(消極)
イ将来の逸失利益を事故当時の現在価額に換算するための中間利息控除方法
主 文
一 上告人らの本訴請求中上告人らが被上告人ら各自に対し各金三八万七七九二円及びこれに対する昭和四六年七月三一日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員の支払を求める請求を棄却した部分につき,原判決を破棄し,第一審判決を取り消す。
二 被上告人らは各自上告人らに対し各金三八万七七九二円及びこれに対する昭和四六年七月三一日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
三 上告人らのその余の上告を棄却する。
四 訴訟の総費用はこれを二分し,その一を被上告人らの負担とし,その余を上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人古屋倍雄の上告理由第一の一について
交通事故により死亡した幼児の損害賠償債権を相続した者が一方で幼児の養育費の支出を必要としなくなった場合においても,右養育費と幼児の将来得べかりし収入との間には前者を後者から損益相殺の法理又はその類推適用により控除すべき損失と利得との同質性がなく,したがって,幼児の財産上の損害賠償額の算定にあたりその将来得べかりし収入額から養育費を控除すべきものではないと解するのが相当である(当裁判所昭和三六年(オ)第四一三号同三九年六月二四日第三小法廷判決・民集一八巻五号八七四頁参照)。
従って,交通事故により死亡した亡甲(当時満一〇歳)の両親である上告人らの被上告人らに対する損害賠償請求について,亡甲の財産上の損害額の算定にあたり,その将来得べかりし収入額から養育費に相当する七七万五五八四円を控除した原判決には,法令の解釈適用を誤った違法があるといわなければならず,右の違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。それゆえ,上告人らの本訴請求中上告人らが被上告人ら各自に対し右七七万五五八四円の二分一にあたる各三八万七七九二円及びこれに対する昭和四六年七月三一日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員の支払を求める請求を棄却した部分につき,原判決を破棄し,第一審判決を取り消したうえ,上告人らの右請求を認容すべきである。
同第一の二について
原審が亡甲の将来得べかりし利益の喪失による損害賠償につき,本件事故発生時において一時にその支払を受けるものとし,年五分の中間利息を控除するために採用した所論ライプニツツ式計算法は,交通事故の被害者の将来得べかりし利益を事故当時の現在価額に換算するための中間利息控除の方法として不合理なものとはいえず,所論引用の判例(当裁判所昭和三四年(オ)第二一三号同三七年一二月一四日判決・民集一六巻一二号二三六八頁)は複式ホフマン式計算法によらなければならない旨を判示するものではないから,右判断と抵触するものではない。原判決に所論の違法はなく,論旨は,採用できない。
同第一の三及び第二について
所論の点に関する原審の認定判断は,原判決挙示の証拠関係に照らし,正当として是認することができ,その過程に所論の違法はなく,所論引用の判例に抵触するものではない。所論違憲の主張は,畢竟,原審の事実の認定を非難するものにすぎず失当である。論旨は,採用できない。
よって,民訴法四〇八条一号,三九六条,三八六条,三八四条,九六条,九二条,九三条に従い,裁判官大塚喜一郎,同吉田豊の各補足意見,裁判官本林讓の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
裁判官大塚喜一郎,裁判官吉田豊の補足意見(略)
最高裁裁判長裁判官 大塚喜一郎 ,裁判官吉田 豊,同本林 讓,同 栗本一夫
逸失利益と租税額控除,一部請求と時効(最判昭和45年7月24日民集24巻7号1177頁)
ア逸失利益の喪失による損害額の算定と租税額控除の要否
イ一部請求の趣旨が明示されていない場合の訴提起による時効中断の範囲
上告代理人佐野正秋,同香川文雄の上告理由一,二について。
上告人甲による加害自動車の運転状況と被害者たる被上告人の行動および現場の交通事情等,本件事故発生当時における事実関係について原審(第一審判決引用部分を含む。以下同じ。)の認定するところは,挙示の証拠関係に照らし,首肯することができ,右事実関係によるときは,本件事故は同上告人が自動車運転者としての注意義務を守らなかった過失に基因するものというべく,被上告人にも歩行者としての注意義務違反があるにせよ,いわゆる信頼の原則を適用して同上告人に過失の責がないということはできないとした原審の判断は,正当であって,右認定判断に関し,原判決に,所論のような理由不備,審理不尽等の違法は認められない。論旨は,その実質において,原審の専権に属する証拠の取捨判断,事実の認定を非難するものか,その認定にそわない事実を前提として原判決の違法をいうものにすぎず,採用できない。
同三について
被上告人が本件事故による負傷のためたばこ小売業を廃業するのやむなきに至り,右営業上得べかりし利益を喪失したことによって被った損害額を算定するにあたって,営業収益に対して課せられるべき所得税その他の租税額を控除すべきではないとした原審の判断は正当であり,税法上損害賠償金が非課税所得とされているからといって,損害額の算定にあたり租税額を控除すべきものと解するのは相当でない。したがって,原判決に所論の違法はなく,論旨は採用できない。
同四について。
一個の債権の一部についてのみ判決を求める趣旨を明らかにして訴を提起した場合,訴提起による消滅時効中断の効力は,その一部についてのみ生じ,残部には及ばないが,右趣旨が明示されていないときは,請求額を訴訟物たる債権の全部として訴求したものと解すべく,この場合には,訴の提起により,右債権の同一性の範囲内において,その全部につき時効中断の効力を生ずるものと解するのが相当である。
これを本件訴状の記載について見るに,被上告人の本訴損害賠償請求をもって,本件事故によって被った損害のうちの一部についてのみ判決を求める趣旨であることを明示したものとはなし難いから,所論の治療費金五万〇一九八円の支出額相当分は,当初の請求にかかる損害額算定根拠とされた治療費中には包含されておらず,昭和四一年一〇月五日の第一審口頭弁論期日においてされた請求の拡張によってはじめて具体的に損害額算定の根拠とされたものであるとはいえ,本訴提起による時効中断の効力は,右損害部分をも含めて生じているものというべきである。
従って,これと同旨の見解に立って,上告人らの時効の抗弁を排斥すべきものとした原審の判断は正当であって,原判決に所論の違法はなく,論旨は採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条,九三条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁 裁判長裁判官 草鹿浅之介,裁判官城戸芳彦 ,同 色川幸太郎 ,同村上朝一
事故後の死亡と逸失利益(最判平成8年4月25日民集50巻5号1221頁 )
後遺障害による逸失利益の算定に当たり事故後の別の原因による被害者の死亡を考慮することの許否
上告代理人樋渡源藏,同樋渡俊一の上告理由第二点について
一 原審の確定したところによれば,(1) 昭和六三年一月一〇日,新潟県内の国道上において,被上告人青森定期自動車株式会社が保有し,被上告人甲の運転する大型貨物自動車が,戊の同乗する普通貨物自動車と衝突し,戊は,右交通事故により脳挫傷,頭蓋骨骨折等の傷害を負った(以下「本件交通事故」という。),(2) 戊は,本件交通事故の後,山形県鶴岡市内の病院において入通院による治療を受けた結果,平成元年六月二八日には,知能低下,左腓骨神経麻痺,複視等の後遺障害(以下「本件後遺障害」という。)を残して症状が固定した,(3) 戊は,本件交通事故当時,大工として工務店に勤務していたものであるが,右の症状固定の後も就労が可能な状態になかったことから,毎日のように山形県西田川郡甲町内の自宅付近の海で貝を探るなどしていたところ,同年七月四日,海中で貝を採っている際に心臓麻痺を起こして死亡した(以下「本件死亡事故」という。),というのである。
二 戊の相続人である上告人らは,本件において,戊の本件後遺障害による労働能力の一部喪失を理由として,戊の症状固定時である四四歳から就労可能年齢六七歳までの間の逸失利益の損害を主張している。原審は,戊の本件後遺障害による逸失利益があるとはしたものの,戊は本件交通事故と因果関係のない本件死亡率故により死亡したものであるところ,事実審の口頭弁論終結前に被害者の死亡の事実が発生し,その生存期間が確定して,その後に逸失利益の生ずる余地のないことが判明した場合には,後遺障害による逸失利益の算定に当たり右死亡の事実を斟酌すべきものであるとして,戊の死亡後の期間についての逸失利益を認めなかった。
三 しかし,原審の右判断は是認できない。その理由は,次のとおりである。
交通事故の被害者が事故に起因する傷害のために身体的機能の一部を喪失し,労働能力の一部を喪失した場合において,いわゆる逸失利益の算定に当たっては,その後に被害者が死亡したとしても,右交通事故の時点で,その死亡の原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,右死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではないと解するのが相当である。何故なら,労働能力の一部喪失による損害は,交通事故の時に一定の内容のものとして発生しているのであるから,交通事故の後に生じた事由によってその内容に消長を来すものではなく,その逸失利益の額は,交通事故当時における被害者の年齢,職業,健康状態等の個別要素と平均稼働年数,平均余命等に関する統計資料から導かれる就労可能期間に基づいて算定すべきものであって,交通事故の後に被害者が死亡したことは,前記の特段の事情のない限り,就労可能期間の認定に当たって考慮すべきものとはいえないからである。また,交通事故の被害者が事故後にたまたま別の原因で死亡したことにより,賠償義務を負担する者がその義務の全部又は一部を免れ,他方被害者ないしその遺族が事故により生じた損害のてん補を受けることができなくなるというのでは,衡平の理念に反することになる。
四 これを本件についてみるに,前記事実関係によれば,戊は本件交通事故に起因する本件後遺障害により労働能力の一部を喪失し,これによる損害を生じていたところ,本件死亡事故による戊の死亡について前記の特段の事情があるとは認められないから,就労可能年齢六七歳までの就労可能期間の全部について逸失利益を算定すべきである。
従って,これと異なる判断の下に,戊の死亡後の期間について本件後遺障害による逸失利益を認めなかった原判決には,法令の解釈適用を誤った違法があり,その違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由があり,その余の論旨について判断するまでもなく,原判決は上告人らの敗訴部分のうち平成五年二月二三日付け上告状補充書による不服申立て部分につき破棄を免れない。そして,本件については,損害額全般について更に審理を尽くさせる必要があるから,右破棄部分につきこれを原審に差し戻すのが相当である。
よって,民訴法四〇七条一項に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁 裁判長裁判官 小野幹雄 ,裁判官高橋久子,同 遠藤光男,同井嶋一友,同藤井正雄
逸失利益算定後の死亡(最判平成11年12月20日民集53巻9号2038頁)
交通事故被害者が事故のため要介護状態となった後,別の原因で死亡した場合に死亡後の期間に係る介護費用を事故の損害として請求できるか。
上告代理人高崎尚志,同赤松範夫の上告理由について
一 亡丙は,上告人運転の普通乗用自動車に衝突されて傷害を負い,その後遺障害のため他人の介護を要する状態にあったが,本件訴訟の係属中に胃がんにより死亡した。亡丙の相続人である被上告人らは,主位的に,損害額の算定に当たり亡丙が胃がんにより死亡した事実を考慮すべきではないとして,亡丙の傷害による損害の賠償を求め,その死亡後の逸失利益及び介護費用を右交通事故による損害として主張している。また,被上告人らは,予備的に,亡丙の死亡と右交通事故との間に因果関係があるとして,その死亡による損害の賠償を求めている。
原審の確定したところによれば,(一) 平成三年九月一八日午後七時ころ,兵庫県揖保郡甲町内の信号機の設置されている交差点において,上告人運転の普通乗用自動車が右交差点を自転車を引いて横断歩行中の亡丙に衝突し,亡丙は,脳挫傷,外傷性くも膜下出血等の傷害を負った(以下「本件事故」という。),(二) 亡丙の症状は,平成六年八月三一日,自賠法施行令別表(後遺障害等級表)一級三号に該当する後遺障害を残して固定した,(三) 亡丙は,その後も,脳挫傷による知能障害,四肢痙性麻痺等により,いわゆる寝たきりで,食事,用便等日常生活のすべての面で他人の介護を要する状態にあった,(四) 亡丙は,本件訴訟が原審に係属中である平成八年七月八日,胃がんにより死亡し,妻である被上告人乙並びに子である同丁及び同戊が相続により亡丙の損害賠償請求権を取得した,(五) 亡丙は,昭和六三年一二月に肝臓の手術を受けたものの,ふだんの生活には支障がなく,本件事故前には,普通に生活をしていて,体の不調を訴えることもなかった,というのである。
二 原審は,右事実関係の下において,大要,次のように判示して,亡丙の死亡後の逸失利益及び介護費用を本件事故による損害と認め,被上告人らの主位的請求の一部を認容した。
1 亡丙については,本件事故の時点で,その死亡の原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたとはいえないから,右死亡の事実を就労可能期間の認定上考慮すべきではない。亡丙が得たであろう年間収入を二八七万四一三〇円とし,労働能力喪失期間を症状固定時から六年間として算定すると,その逸失利益は一三〇六万九二四三円となる。
2 交通事故により傷害を負ったことに基づいて被害者に生じた損害の賠償請求権は一個であり,加害者が負うべき損害賠償債務は,交通事故時に発生し,かつ,遅滞に陥るものである。また,判決に基づいて金員が支払われた後に被害者が死亡した場合には,加害者が既払金につき不当利得として返還を求めることはできないと解すべきであるから,事実審の口頭弁論終結時までに被害者が死亡したことにより現実に被害者側が負担を免れた損害について,交通事故時において既に発生した損害額から控除するとすれば,右口頭弁論終結後に被害者が死亡した場合に比して,被害者側にとって衡平を失することになる。亡丙は,平均余命までの間,職業付添人の介護を必要とするところ,入院費を含む介護費用を一日当たり一万七二六〇円とし,介護を要する期間を症状固定時から一二年間として算定すると,亡丙の介護に要する費用は五一九七万二九一五円となる。
三 しかし,原審の判断のうち,亡丙の死亡後の逸失利益を損害と認めた部分は是認できるが,その死亡後の介護費用を損害と認めた部分は是認できない。その理由は,次のとおりである。
1 交通事故の被害者が事故に起因する傷害のために身体的機能の一部を喪失し,労働能力の一部を喪失した場合において,逸失利益の算定に当たっては,その後に被害者が別の原因により死亡したとしても,右交通事故の時点で,その死亡の原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,右死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではないと解するのが相当である(最高裁平成五年(オ)第五二七号同八年四月二五日判決・民集五〇巻五号一二二一頁,最高裁平成五年(オ)第一九五八号同八年五月三一日判決・民集五〇巻六号一三二三頁参照)。これを本件について見ると,前記一の事実によれば,亡丙が本件事故に遭ってから胃がんにより死亡するまで約四年一〇か月が経過しているところ,本件事故前,亡丙は普通に生活をしていて,胃がんの兆候はうかがわれなかったのであるから,本件において,右の特段の事情があるということはできず,亡丙の就労可能期間の認定上,その死亡の事実を考慮すべきではない。
2 しかし,介護費用の賠償については,逸失利益の賠償とはおのずから別個の考慮を必要とする。すなわち,(一) 介護費用の賠償は,被害者において現実に支出すべき費用を補てんするものであり,判決において将来の介護費用の支払を命ずるのは,引き続き被害者の介護を必要とする蓋然性が認められるからにほかならない。ところが,被害者が死亡すれば,その時点以降の介護は不要となるのであるから,もはや介護費用の賠償を命ずべき理由はなく,その費用をなお加害者に負担させることは,被害者ないしその遺族に根拠のない利得を与える結果となり,かえって衡平の理念に反することになる。(二) 交通事故による損害賠償請求訴訟において一時金賠償方式を採る場合には,損害は交通事故の時に一定の内容のものとして発生したと観念され,交通事故後に生じた事由によって損害の内容に消長を来さないものとされるのであるが,右のように衡平性の裏付けが欠ける場合にまで,このような法的な擬制を及ぼすことは相当ではない。(三) 被害者死亡後の介護費用が損害に当たらないとすると,被害者が事実審の口頭弁論終結前に死亡した場合とその後に死亡した場合とで賠償すべき損害額が異なることがあり得るが,このことは被害者死亡後の介護費用を損害として認める理由になるものではない。以上によれば,【要旨】交通事故の被害者が事故後に別原因により死亡した場合には,死亡後に要したであろう介護費用を同交通事故による損害として請求はできない。
そして,前記一の事実によれば,亡丙は原審口頭弁論終結前である平成八年七月八日に胃がんにより死亡し,死亡後は同人の介護は不要となったものであるから,被上告人らは,死亡後の介護費用を本件事故による損害として請求することはできない。
四 従って,これと異なる判断の下に,亡丙の介護費用につき,同人の死亡の事実を考慮することなくその額を算定した原判決には,法令の解釈適用を誤った違法があり,この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由があり,原判決中上告人の敗訴部分のうち,介護費用及びこれを前提とする弁護士費用の請求に関する部分は破棄を免れない。そして,右の部分については更に審理を尽くさせる必要があるから,これを原審に差し戻すこととし,原判決中その余の部分は正当であるから,上告人のその余の上告を棄却することとする。
よって,裁判官井嶋一友の補足意見(略)があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官井嶋一友,裁判官小野幹雄,同遠藤光男,同藤井正雄,同大出峻郎
事業取得者の逸失利益(最判昭和43年8月2日民集22巻8号1525頁)
企業主が生命身体を侵害されたため企業に従事てきずに生じた財産損害額は、特段の事情のないかぎり、企業収益中に占める企業主の労務その他企業に対する個人的寄与に基づく収益部分の割合により算定する。
上告代理人小谷勝重名義,同小坂重吉の上告理由第1点について。
企業主が生命もしくは身体を侵害されたため,その企業に従事することができなくなつたことによつて生ずる財産上の損害額は,原則として,企業収益中に占める企業主の労務その他企業に対する個人的寄与に基づく収益部分の割合によつて算定すべきであり,企業主の死亡により廃業のやむなきに至つた場合等特段の事情の存しないかぎり,企業主生存中の従前の収益の全部が企業主の右労務等によってのみ取得されていたと見ることはできない。したがつて,企業主の死亡にかかわらず企業そのものが存続し,収益をあげているときは,従前の収益の全部が企業主の右労務等によってのみ取得されたものではないと推定するのが相当である。
ところで,原審の確定した事実によれば,甲の営業収益額は昭和27年から同31年までの5年間の平均で年間978,044円であり,同人死亡後その営業を承継した被上告人らがあげた同33年度の営業収益は208,318円であるというのである。従って,被上告人らのあげた同34年度以降の営業収益が右同33年度の営業収益と同額であるとすれば,特段の事情のないかぎり,右説示に照らして,甲が生命を侵害されて企業に従事することができなくなったことによって生ずる昭和33年度以降の1年あたりの財産上の損害額は右978,044円から208,318円を差し引いた額であると推定するのが相当である。しかるに,原判決は右損害額の算定の基準として,なんら特段の事情を示すことなく,甲が従前取得していた収益全額をもってすべきものとしているのである。しからば,原判決には,判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背および被上告人らの同34年度以降の営業収益について審理を尽さない違法があるものというべく,論旨はこの点において理由があるに帰する。原判決はこの点に関して破棄を免れない。
同上告理由第2点について。
原判決は,甲の余命年数,出生年月日,職業等の事情を総合し,その稼働年数は本件事故の時より起算して22年間であると判断したのであり,右判断は是認できる。原判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。
同第3点について。
不法行為による慰藉料請求権は,被害者が生前に請求の意思を表明しなくても,相続の対象となることは当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和42年11月1日大法廷判決,民集21巻9号2249頁)。ところで,原審は,被上告人らの固有の慰藉料請求につき各20万円づつ認めたほかに,被害者の慰藉料も同人が生前に放棄したと認むべき格別の事情も認められない本件においては,当然相続の対象となりうるものと解するのを相当とするとして,甲の精神的損害20万円の賠償請求権が被上告人らに相続されたと判断したものであることは,原判文上明らかである。従って,これと異なる見解に立つ所論は採用のかぎりでない。
同第4点について。
本件事故の状況について原判決およびその引用する第1審判決が確定した事実関係のもとにおいて,乙の過失が重要な原因となって本件事故が発生した旨の原審の認定は首肯することができ,右認定を前提として,被害者たる甲の過失は判示の割合において斟酌すべきものとした原審の判断は相当であり,原判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。
附帯上告について。
本件附帯上告状によっては,附帯上告が上告理由と同1の理由に基づくものであるかどうか明らかでないが,かりに同1の理由に基づくとしても,附帯上告は当審の口頭弁論終結時までに提起されるべきところ,右附帯上告状が当裁判所に提出されたのは,口頭弁論終結後の昭和43年6月26日であること記録上明らかである。そうとすれば,本件附帯上告は不適法であり,却下を免れない。
よって,原判決の被上告人ら勝訴部分中得べかりし利益の損害賠償請求に関する部分を破棄し,この点につき更に審理を尽させるため,右の点に関する本件を原審に差し戻すこととし,民訴法407条1項,396条,384条,399条の3,95条,89条,93条に従い右上告理由書の上告理由第3点に対する慰藉料請求権の相続についての裁判官色川幸太郎の反対意見(略)があるほか,裁判官全員1致で,主文のとおり判決する。
最高裁 裁判長裁判官 奥野健一 ,裁判官草鹿浅之介,同城戸芳彦,同石田和外,同 色川幸太郎
生命保険金の控除の要否(最判昭和39年9月25日民集18巻7号1528頁)
不法行為による死亡に基づく損害賠償額から生命保険金を控除することの適否
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人高岡次郎の上告理由第一点について。
不法行為における過失相殺については,裁判所は,具体的な事案につき公平の観念に基づき諸般の事情を考慮し,自由なる裁量によって被害者の過失を斟酌して損害額を定めればよく,所論のごとく斟酌すべき過失の度合につき一々その理由を記載する必要がないと解するのが相当である。
そして,原判決は,その認定した事実のもとにおいて,被害者Aに過失がある旨を判示したうえ,過失相殺により損害額を約三分の二に減じたのであって,原判決には,所論のごとき違法のかどは見当らない。
所論は独自の見解として排斥を免れない。
同第二点について。
生命保険契約に基づいて給付される保険金は,すでに払い込んだ保険料の対価の性質を有し,もともと不法行為の原因と関係なく支払わるべきものであるから,たまたま本件事故のように不法行為により被保険者が死亡したためにその相続人たる被上告人両名に保険金の給付がされたとしても,これを不法行為による損害賠償額から控除すべきいわれはないと解するのが相当である。
したがって,損害額の算定に当ってこれを控除しなかった原判決の判断は正当であって,これと異なる所論は,独自の見解として排斥を免れない。
よって,民訴四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外
逸失利益と中間利息控の除率(最判平成17年6月14日民集59巻5号983頁)
損害賠償額の算定に当たり被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合
主 文
原判決中上告人の敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき、本件を札幌高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人田中登,同小黒芳朗の上告受理申立て理由(ただし,排除された部分を除く。)について
1 原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)被上告人らの子である甲(平成4年1月生。当時9歳)は,平成13年8月18日,上告人の過失によって発生した交通事故(以下「本件事故」という。)により死亡した。
(2)被上告人らは,本件事故による甲の上告人に対する損害賠償請求権を法定相続分である各2分の1の割合で相続により取得した。
2 被上告人らは,不法行為等による損害賠償請求権に基づき,上告人に対し,本件事故による損害賠償を請求している。
3 原審は,甲の将来の逸失利益の算定における中間利息の控除割合につき,次のとおり判示して,被上告人らの請求を一部認容した。
交通事故による逸失利益を現在価額に換算する上で中間利息を控除することが許されるのは,将来にわたる分割払と比べて不足を生じないだけの経済的利益が一般的に肯定されるからにほかならないのであるから,基礎収入を被害者の死亡又は症状固定の時点でのそれに固定した上で逸失利益を現在価額に換算する場合には,中間利息の控除割合は裁判時の実質金利(名目金利と賃金上昇率又は物価上昇率との差)とすべきである。民法404条は,利息を生ずべき債権の利率についての補充規定であり,実質金利とは異なる名目金利を定める規定であるので,これを実質金利の基準とすることの合理性を見いだすことはできない。また,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)46条5号ほかの倒産法の規定や民事執行法88条2項の規定が弁済期未到来の債権を現在価額に換算するに際して民事法定利率による中間利息の控除を認めていることについては,いずれも利息の定めがなく,かつ,弁済期の到来していない債権を対象としており,弁済期が到来し,かつ,不法行為時から遅延損害金が発生している逸失利益の賠償請求権とは,その対象とする債権の性質を異にしているのであって,中間利息の控除割合についてこれらの規定を類推又はその趣旨を援用する前提を欠くものというべきである。
我が国の昭和31年から平成14年までの47年間における定期預金(1年物)の金利(税引き後)と賃金上昇率との差がプラスとなった年は16年で,マイナスとなった年は31年であること,そのうちプラス2%を超えたのは3年(最大値はプラス2.3%)であり,マイナス5%を下回った年は16年(最小値はマイナス21.4%)であり,全期間の平均値はマイナス3.32%であり,平成8年から平成14年までの期間の平均値は0.25%であることによれば,甲の将来の逸失利益を現在価額に換算するための中間利息の控除割合としての実質金利は,多くとも年3%を超えることはなく,中間利息の控除割合を年3%とすることが将来における実質金利の変動を考慮しても十分に控え目なものというべきである。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認できない。その理由は,次のとおりである。
我が国では実際の金利が近時低い状況にあることや原審のいう実質金利の動向からすれば,被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は民事法定利率である年5%より引き下げるべきであるとの主張も理解できないではない。
しかし、民法404条において民事法定利率が年5%と定められたのは、民法の制定に当たって参考とされたヨーロッパ諸国の一般的な貸付金利や法定利率、我が国の一般的な貸付金利を踏まえ、金銭は、通常の利用方法によれば年5%の利息を生ずべきものと考えられたからである。そして、現行法は、将来の請求権を現在価額に換算するに際し、法的安定及び統一的処理が必要とされる場合には、法定利率により中間利息を控除する考え方を採用している。例えば、民事執行法88条2項、破産法99条1項2号(旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)46条5号も同様)、民事再生法87条1項1号、2号、会社更生法136条1項1号、2号等は、いずれも将来の請求権を法定利率による中間利息の控除によって現在価額に換算することを規定している。損害賠償額の算定に当たり被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するについても、法的安定及び統一的処理が必要とされるのであるから、民法は、民事法定利率により中間利息を控除することを予定しているものと考えられる。このように考えることによって、事案ごとに、また、裁判官ごとに中間利息の控除割合についての判断が区々に分かれることを防ぎ、被害者相互間の公平の確保、損害額の予測可能性による紛争の予防も図ることができる。上記の諸点に照らすと、損害賠償額の算定に当たり、被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は、民事法定利率によらなければならないというべきである。これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由がある。
5 以上のとおりであるから、原判決中上告人の敗訴部分を破棄し、損害額等について更に審理を尽くさせるため、同部分につき、本件を原審に差し戻すことにする。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷 裁判官 濱田邦夫 上田豊三 藤田宙靖 裁判長裁判官金谷利廣は、退官のため署名押印することができない。 裁判官 濱田邦夫
共同不法行為
共同不法行為に関する重要裁判例(最高裁判所判決等)を実装しました。
公害共同不法行為と賠償範囲(最判昭和43年4月23日民集22巻4号964頁)
共同行為者の流水汚染により惹起された損害と各行為者の賠償すべき損害の範囲
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告指定代理人武藤英一,同古館清吾の上告理由第一点について。
共同行為者各自の行為が客観的に関連し共同して違法に損害を加えた場合において,各自の行為がそれぞれ独立に不法行為の要件を備えるときは,各自が右違法な加害行為と相当因果関係にある損害についてその賠償の責に任ずべきであり,この理は,本件のごとき流水汚染により惹起された損害の賠償についても,同様であると解するのが相当である。これを本件についていえば,原判示の本件工場廃水を山王川に放出した上告人は,右廃水放出により惹起された損害のうち,右廃水放出と相当因果関係の範囲内にある全損害について,その賠償の責に任ずべきである。ところで,原審の確定するところによれば,山王川には自然の湧水も流入し水がとだえたことはなく,昭和三三年の旱害対策として多くの井戸が掘られたが,山王川の流域においてはその数が極めて少ないことが認められるから,上告人の放出した本件工場廃水がなくても山王川から灌漑用水をとることができなかったわけではないというのであり,また,山王川の流水が本件廃水のみならず所論の都市下水等によっても汚染されていたことは推測されるが,原判示の曝気槽設備のなかった昭和三三年までは,山王川の流水により稀釈される直前の本件工場廃水は,右流水の約一五倍の全窒素を含有していたと推測され,山王川の流水は右廃水のために水稲耕作の最大許容量をはるかに超過する窒素濃度を帯びていたというのである。そして,原審は,右の事実および原審認定の本件における事実関係のもとにおいては,本件工場廃水の山王川への放出がなければ,原判示の減収(損害)は発生しなかった筈であり,右減収の直接の原因は本件廃水の放出にあるとして,右廃水放出と損害発生との間に相当因果関係が存する旨判断しているのであって,原審の拳示する証拠によれば,原審の右認定および判断は,これを是認できる。所論は,畢竟,原審の前記認定を非難し,右認定にそわない事実を前提として原判決を非難するに帰し,採用できない。
同第二点について。
原審の確定するところによれば,原判示の本件工場廃水は多量の窒素を含み,これが水量の少ない山王川に排出されるときは,右山王川の流水は水稲耕作の窒素許容量をはるかに超える窒素濃度を有することになり,ために右流水を水稲耕作の灌漑用水として利用するにつき有害かつ不適当になるというのである。そして,原審は,右の事実および原審認定の本件における事実関係のもとにおいては,本件工場廃水の放出は,少なくとも本件の昭和三三年のように降雨量の少ない年においては,違法性を帯びるにいたる旨判断しているのであって,原審の右認定および判断は,挙示の証拠により,これを是認できる。所論は,原判決を正解せず,原審の前記認定にそわない事実を前提として原判決を非難するに帰し,採用できない。
同第三点(1)について。
記録によれば,甲四二号証として原審に提出された書証が,井戸掘負担金を証明する資料でないことは,論旨指摘のとおりである。しかし,記録によれば,原審は,所論の井戸掘負担金の額を認定する証拠として,被上告人□□甲本人尋問の結果を引用しているところ,右によれば,井戸掘負担金額の内訳が原判決添付目録井戸掘負担金欄記載のとおりであるとする原審の認定を是認できる。それ故,所論は,原判決の結論に影響を及ぼすものではなく,採用のかぎりではない。
同第三点(2)について。
原審の確定するところによれば,本件工場廃水の流入する直前の山王川の流水は通常の窒素施肥量にやや近い窒素を含有していたにすぎないが,活性汚泥法による曝気槽の設置された昭和三四年以降においても,右廃水の流入後における流水は,水稲耕作における窒素の最大許容量をはるかにこえる窒素濃度を帯びていたというのであり,また,同三四年頃,上告人と被上告人らとの間で,本件工場廃水の排出方法について原判示の約定が成立したが,その後においても山王川の窒素濃度が減少せず,灌漑用水として十分に利用することができない状態にあったので,被上告人らは,同三四年七月から同三六年五月までの間に,原判示の深井戸四本を掘ったというのであって,原審の挙示する証拠によれば,右の認定は,これを是認できる。そして,原審は,右の事実によれば,山王川の流水を水稲耕作に使用するためには,被上告人らとしては,本件工場廃水により汚染された流水を稀釈する等してこれを浄化し,流水の窒素含有量を水稲耕作に支障のない量にまで引き下げる必要があったのであり,前記深井戸四本による井戸水注入は汚染された流水の水質浄化のための一方法であるから,右深井戸四本の井戸掘に要した費用と,本件工場廃水放出との間には相当因果関係が存する旨,判断しているものと解せられ,原審の右判断は,前記の事実関係のもとにおいては,正当としてこれを是認できる。所論の実質は,畢竟,原審の前記認定を非難し,右認定にそわない事実を前提として,原判決を非難するに帰するものであって,採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官横田正俊,裁判官田中二郎,同下村三郎,同松本正雄,同飯村義美
民法719条1項前段の共同不法行為と意思連絡の要否(最判昭和32年3月26日民集11巻3号543頁)
民法719条1項前段の共同不法行為と意思連絡の要否
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人岡部秀温の上告理由第一点について。
所論は,上告人に共同不法行為の責任を認めるためには,上告人と他の不法行為者間に意思の連絡があったかどうかを証拠によって確定しなければならないのに,原判決はこの点を観過した違法があると主張する。しかし民法719条一項前段の共同の不法行為が成立するためには,不法行為者間に意思の共通(共謀)もしくは「共同の認識」を要せず,単に客観的に権利侵害が共同になされるを以て足りると解すべきであるから,原審が特に所論のような「意思連絡」の有無を確定しなかったからといって,なんら違法はない。(共同不法行為者各自に主観的要件たる故意,過失の具われることを要することはいうまでもないが,論旨が単に故意の判定を非難する趣旨としても,記録に存する資料について検討してみると,原審が上告人にも,権利侵害の故意ありしものと判定したのは相当であって所論の違法はない)。
同第二点について。
所論中,原審の採用した証人Aの供述を伝聞証言であると非難するが,民事訴訟においては,伝聞証言の証拠能力は当然に制限されるものではなく,その採否は,裁判官の自由な心証による判断に委されていると解すべきのみならず(昭和27年12月5日第二小法廷判決集6巻11号111七頁参照),また解雇された社員が常にその会社の社長について真実に反した証言をするものとは限らないから,その証言を採用することを違法ということはできない。畢竟所論は,原審の裁量に属する証拠の採否を非難するにすぎない。
よって,民訴四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官小林俊三,裁判官島保,同河村又介,同垂水克己
共同不法行為と求償(最判昭和41年11月18日民集20巻9号1886頁)
ア被用者と第三者との共同過失による交通事故の損害賠償をした使用者の第三者に対する求償権の成否
イこの場合の第三者の負担部分
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人野村千足の上告理由1ないし5について。
原審が確定した事実によれば「昭和三四年一月二九日午後一〇時頃,本件事故現場において,被上告会社の被用者(タクシー運転手)である被上告人甲の運転する自動車(タクシー)と上告人の運転する自動車とが衝突事故を起した。右事故は,被上告人甲と上告人の過失によって惹起されたものであり,これにより右タクシーの乗客乙は胸部,頭部打撲傷等の傷害を受けた。被上告会社は,乙に対し,右事故による損害を賠償した。」というのである。
右事実関係のもとにおいては,被上告会社と上告人及び被上告人甲らは,乙に対して,各自,乙が蒙った全損害を賠償する義務を負うものというべきであり,また,右債務の弁済をした被上告会社は,上告人に対し,上告人と被上告人甲との過失の割合にしたがって定められるべき上告人の負担部分について求償権を行使することができるものと解するのが相当である。したがって,この点に関する原審の判断は結論において正当であり,原判決に所論の違法はない。論旨は独自の見解であって採るをえない。
同追加上告理由1ないし4について。
原審が確定した事実関係のもとにおいては,上告人と被告人甲の過失の割合を八対二とした原審の判断は正当であり,原判決に所論の違法はないから,論旨は採用に値しない。
同追加上告理由5について。
所論の点に関する原審の認定は,これに対応する挙示の証拠によって是認することができる。また,原審が確定した事実関係に徴すれば,被上告会社所有の本件自動車の損傷が,上告人と被告人甲の不法行為によるものであるとした原審の判断も,これを首肯することができる。論旨は,ひつきよう,原審が適法にした事実の認定を非難し,あるいは,独自の見解から原判決の違法をいうにすぎないものであって,採るをえない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官奥野健一,裁判官草鹿浅之介,同城戸芳彦,同石田和外,同色川幸太郎
共同不法行為と民法437条の免除(最判平成6年11月24日裁判集民事173号431頁)
共同不法行為者が負担する損害賠償債務と民法437条の適用の有無
主 文
原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
右部分について被上告人の控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
理 由
上告代理人足立昌昭の上告理由一について
所論の点に関する原審の認定判断は,原判決挙示の証拠関係に照らし,正当として是認することができ,原判決に所論の違法はない。右判断は,所論引用の判例と抵触するものではない。論旨は採用できない。
同二について
本件訴訟は,上告人がXとの婚姻関係を継続中,被上告人がXと不貞行為に及び,そのため右婚姻関係が破綻するに至った(以下,これを「本件不法行為」という。)として,被上告人に対し,不法行為に基づく慰謝料三〇〇万円とこれに対する本件不法行為の日の後である平成元年一一月九日から支払済ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を請求するものである。
原審は,上告人の右主張事実を認め,本件不法行為に基づく慰謝料は三〇〇万円が相当であると判断したが,被上告人が原審において主張した債務免除の抗弁を一部認め,被上告人が上告人に支払うべき慰謝料は一五〇万円が相当であるとし,上告人の請求を全部認容した一審判決を変更して,被上告人に対し,一五〇万円及びこれに対する前記遅延損害金の支払を命じた。すなわち,原審は,(1) 被上告人とXの不貞行為は上告人に対する共同不法行為というべきところ,上告人とXとの間には平成元年六月二七日離婚の調停が成立し(以下,これを「本件調停」という。),その調停条項には,本件調停の「条項に定めるほか名目の如何を問わず互いに金銭その他一切の請求をしない」旨の定め(以下「本件条項」という。)があるから,上告人はXに対して離婚に伴う慰謝料支払義務を免除したものというべきである,(2) 被上告人とXが上告人に対して負う本件不法行為に基づく損害賠償債務は不真正連帯債務であるところ,両名にはそれぞれ負担部分があるものとみられるから,本件調停による右債務の免除はXの負担部分につき被上告人の利益のためにもその効力を生じ,被上告人とXが上告人に対して負う右損害賠償債務のうち被上告人固有の負担部分の額は一五〇万円とするのが相当であると判断した。
しかし,原審の右(1)の判断は是認できるが,右(2)のうち,本件調停による債務の免除が被上告人の利益のためにもその効力を生ずるとした判断は是認できない。その理由は次のとおりである。
民法七一九条所定の共同不法行為者が負担する損害賠償債務は,いわゆる不真正連帯債務であって連帯債務ではないから,その損害賠償債務については連帯債務に関する同法四三七条の規定は適用されないものと解するのが相当である(最高裁昭和四三年(オ)第四三一号同四八年二月一六日判決・民集二七巻一号九九頁参照)。
原審の確定した事実関係によれば,上告人とXとの間においては,平成元年六月二七日本件調停が成立し,その条項において,両名間の子の親権者を上告人とし,Xの上告人に対する養育費の支払,財産の分与などが約されたほか,本件条項が定められたものであるところ,右各条項からは,上告人が被上告人に対しても前記免除の効力を及ぼす意思であったことは何らうかがわれないのみならず,記録によれば,上告人は本件調停成立後四箇月を経過しない間の平成元年一〇月二四日に被上告人に対して本件訴訟を提起したことが明らかである。右事実関係の下では,上告人は,本件調停において,本件不法行為に基づく損害賠償債務のうちXの債務のみを免除したにすぎず,被上告人に対する関係では,後日その全額の賠償を請求する意思であったものというべきであり,本件調停による債務の免除は,被上告人に対してその債務を免除する意思を含むものではないから,被上告人に対する関係では何らの効力を有しないものというべきである。
そうすると,右と異なる見解に立って上告人の請求を一部棄却した原判決は,共同不法行為者に対する債務の免除の効力に関する法理の解釈適用を誤ったものであり,この違法が原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。この趣旨をいう論旨は理由があり,原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして,以上に判示したところによれば,上告人の本件損害賠償請求はすべて理由があることになり,これと結論を同じくする第一審判決は正当であるから,右部分に対する控訴は理由がなくこれを棄却すべきものである。
よって,民訴法四〇八条,三九六条,三八四条,九六条,八九条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官大白 勝,裁判官大堀誠一,同小野幹雄,同三好 達,同高橋久子
共同不法行為と賠償者の使用者への求償(最判昭和63年7月1日民集42巻6号451頁)
被用者と第三者との共同不法行為による損害を賠償した第三者からの使用者に対する求償権の成否
主 文
上告人の被上告人に対する本訴請求にかかる求償請求のうち金二四万一四五六円及びこれに対する昭和五八年九月二五日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員の支払を求める請求を棄却した部分につき,原判決を破棄し,第一審判決を取り消す。
被上告人は上告人に対し,金二四万一四五六円及びこれに対する昭和五八年九月二五日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
訴訟の総費用は,これを五分し,その四を被上告人の,その余を上告人の負担とする。
理 由
上告代理人出宮靖二郎の上告理由について
一 原審の確定した事実関係は,おおむね,次の1ないし3のとおりである。
1 昭和五八年三月二六日午前八時五分頃,上告人は,普通乗用自動車を運転して京都市内の烏丸通を時速約五〇㎞で南進中,丸太町通との交差点(変形交差点であるため,南行車両は,ハンドルをいったん左に切り,交差点中央部で右に切って走行する必要がある。)にさしかかった際,被上告人の被用者(タクシー運転手)である訴外甲の運転するタクシー(普通乗用自動車)が同交差点内の対向車線側の右折車線上を進行してくるのを発見したが,甲運転車両は同交差点中央部の停止線付近で停止するものと考え,青色信号に従いそのまま同交差点に進入し,いったんハンドルを左に切った後交差点中央部付近でこれを右に切って同一速度で進行しようとした瞬間,前記停止線のやや東側付近において右折進行してきた甲運転車両の右前部が上告人運転車両の右側後部に衝突し,その衝撃により上告人はハンドルを右へ取られ,急制動の措置をとったものの,上告人運転車両は対向車線上に進出したため,烏丸通を北進中の訴外乙運転の普通乗用自動車の前部に接触し,次いで訴外丙運転の普通乗用自動車の右後部に接触し,更に,訴外丁運転の原動機付自転車に急制動を余儀なくさせてこれを路上に転倒させた。
2 本件事故は,甲において,交差点で右折するに際し,前方から直進してくる上告人運転車両の動静を十分確認しないまま漫然と右折進行した過失と,上告人において,右折進行してくる甲運転車両の動静を十分確認しないまま漫然と同一速度で同一進路を進行した過失とによって発生したものであり,その過失割合は,上告人二割,甲八割とするのが相当である。
3 右事故により,右乙,丙及び丁所有の各車両が破損し,いずれも車両の修理代(乙については移動レツカー代を含む。)として,乙は一六万六一二〇円を,丙は一三万二〇〇〇円を,丁は三七〇〇円をそれぞれ支出して同額の損害を被ったため,上告人は,昭和五八年五月一三日までに,乙ら三名に対し,右合計三〇万一八二〇円を損害賠償として支払った。
二 本件訴訟における上告人の被上告人に対する本訴請求中,上告人が右乙ら三名に損害賠償として支払った額についての求償請求は,上告人と甲及び被上告人は本件事故に関し乙ら三名の被害者に対して共同不法行為者の関係にあるが,上告人と甲との過失割合は零対一〇割であるから,上告人は甲の使用者である被上告人に対し,上告人が石乙ら三名に支払った三〇万一八二〇円全額につき求償することができると主張して,その支払を求めるものである。
原審は,前記の事実関係を確定したうえ,被用者(甲)と第三者(上告人)の共同過失により惹起された交通事故の被害者に対しては,使用者(被上告人)及び被用者(甲)と第三者(上告人)は,各自その損害を賠償すべき責任を負い,右三者のうち一人が賠償をなしたときは,その者は他の二者に対し求償できる関係にあり,この場合の各自の負担部分はその過失割合に従って定められるべきところ,右使用者の責任は,その故意又は過失を理由とするものではなく,民法七一五条に定められたものであり,本件においては,被上告人において本件事故につき過失が存したとか,あるいは使用者として被用者甲の過失につき原因を与えていたような事実の主張立証はないのであるから,右三者の過失の割合は,上告人二割,甲八割と認める以上に,被上告人の過失割合を認める余地はなく,その過失割合は零というほかなく,従って被上告人の負担部分は存しないから,上告人は,甲に対してはともかく,被上告人に対しては求償することができないと判示して,上告人の被上告人に対する求償請求を全部棄却した第一審判決を維持し,上告人の控訴を棄却した。
三 しかし,原審の右判断は,是認できない。被用者がその使用者の事業の執行につき第三者との共同の不法行為により他人に損害を加えた場合において,右第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは,右第三者は,被用者の負担部分について使用者に対し求償することができるものと解するのが相当である。けだし,使用者の損害賠償責任を定める民法七一五条一項の規定は,主として,使用者が被用者の活動によって利益をあげる関係にあることに着目し,利益の存するところに損失をも帰せしめるとの見地から,被用者が使用者の事業活動を行うにつき他人に損害を加えた場合には,使用者も被用者と同じ内容の責任を負うべきものとしたものであって,このような規定の趣旨に照らせば,被用者が使用者の事業の執行につき第三者との共同の不法行為により他人に損害を加えた場合には,使用者と被用者とは一体をなすものとみて,右第三者との関係においても,使用者は被用者と同じ内容の責任を負うべきものと解すべきであるからである。
これを本件についてみるに,原審の確定したところによれば,本件交通事故は,上告人と被上告人の被用者である甲との共同の不法行為に該当し,その過失割合は上告人二割,甲八割とするのが相当であるところ,上告人は,被害者である乙ら三名に対し自己の負担部分を超えてその全損害の三〇万一八二〇円を賠償したというのであって,かかる事実関係のもとにおいては,右に説示したところに照らし,上告人は,乙ら三名に賠償した右三〇万一八二〇円のうち,自己の負担部分である六万〇三六四円(二割相当額)を超える二四万一四五六円(八割相当額)につき,甲の使用者である被上告人に対し求償することができるものというべきである。
従って,以上と異なる見解に立って上告人の被上告人に対する本訴請求にかかる求償請求を全部棄却した原審の判断は,不法行為に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであり,右違法が判決に影響を及ぼすことが明らかであるから,この点をいう論旨は理由があり,右求償請求のうち二四万一四五六円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和五八年九月二五日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員の支払を求める請求を棄却した部分につき,原判決は破棄を免れず,そして,原審の適法に確定した右事実関係によれば,右求償請求は右部分の限度で認容すべきものである。
四 よって,本訴請求にかかる求償請求のうち,上告人が本件上告において不服申立の範囲としている二四万一四五六円及びこれに対する昭和五八年九月二五日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員の支払を求める請求を棄却した部分につき,原判決を破棄し,第一審判決を取り消したうえ,右部分の請求を認容することとし,民訴法四〇八条,三九六条,三八六条,九六条,八九条,九二条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官香川保一,同牧圭次,同島谷六郎,同藤島昭 ,同奧野久之
不真正連帯と一方に過失相殺,他方が填補した場合填補の影響(最判平成11年1月29日裁判集民事191号265頁)
1交通事故について甲乙が連帯して損害賠償責任を負う場合に乙の損害賠償責任にのみ過失相殺がされ両者の賠償額が異なるときと甲のした損害の一部てん補が乙の賠償すべき額に及ぼす影響
主 文
一 原判決中,主文第一項を次のとおり変更する。
1 上告人らの控訴に基づき,第一審判決を次のとおり変更する。
(一) 被上告人らは,各自,上告人小野戊に対し,一四六九万二一八一円並びにうち一三六九万二一八一円に対する平成五年八月一七日から,及びうち一〇〇万円に対する被上告人丙征志については平成七年三月一七日から,被上告人オカモト建商株式会社については同月一八日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(二) 被上告人らは,各自,上告人小野丁に対し,一四九七万六〇六八円並びにうち一三九七万六〇六八円に対する平成五年八月一七日から,及びうち一〇〇万円に対する被上告人丙征志については平成七年三月一七日から,被上告人オカモト建商株式会社については同月一八日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 被上告人らの控訴を棄却する。
二 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人竹久保好勝,同大南修平,同齋藤尚之,同増井毅,同大塚由香,同鈴木紀子,同角川圭司の上告理由について
一 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
1 被上告人丙征志は,平成五年八月一七日午後一時二〇分ころ,埼玉県坂戸市八幡二丁目九番二五号先の国道四〇七号線上の歩道寄りの第一車線を,被上告人会社の保有する普通乗用自動車(以下「被上告人車」という。)を運転して走行中,中央線寄りの第二車線に進路変更しようとした。甲は,普通乗用自動車(以下「甲車」という。)を運転して被上告人車の後方で第二車線を進行中であったところ,被上告人車が右のとおり第二車線に進路変更をしようとするのを見て,ハンドルを右に転把したため,甲車は,中央線を越えて対向車線に進入し,対向車線を走行してきた普通乗用自動車と正面衝突した。
2 本件事故により,甲車の助手席に同乗していた乙は両側頸動脈断裂の傷害を負って死亡し,後部座席に同乗していた上告人丁は頭頂部切創,左手打撲の傷害を負った。
3 走行車線を第一車線から第二車線に変更しようとする場合,車両の運転者には,進路を変更する三秒前にその合図をするとともに第二車線の後方を走行する車両の安全を確認する注意義務があるのに,被上告人丙は,これを怠り,第二車線の後方を走行する車両の有無を確認せず,車線変更の合図もしないでハンドルを右に転把して第二車線を走行中の甲車の直前に進出した過失がある。
4 乙及び上告人丁の弁護士費用分を除く損害は,次のとおりである。
(一) 乙
遺体搬送料 六万六〇八〇円
逸失利益 三九一三万八五一二円
慰謝料 二〇〇〇万〇〇〇〇円
葬儀費用 一二〇万〇〇〇〇円
合計 六〇四〇万四五九二円
(二) 上告人丁
治療費 八万三六六〇円
入院雑費 二万二一〇〇円
休業損害 一六万〇九八七円
慰謝料 三一万〇〇〇〇円
合計 五七万六七四七円
5 ところで,甲は,走行中に先行車が急に進路を変更することもあり得るから,前方の車両の動静に注意して進行すべき注意義務があるのに,進路の前方注視を怠り,また,制限速度を約二〇㎞超過して甲車を走行させたために本件事故に至った。同人の過失割合は,三割五分が相当である。甲及び乙は上告人らの子であって,上告人丁及び乙と甲とは,身分上,生活関係上一体の関係があったから,甲の右過失は,被上告人らに対する関係において被害者側の過失としてしん酌すべきである。
また,乙にも,本件事故当時,シートベルトを装着していなかった過失があり,右過失が本件事故の損害を拡大させた。同人の過失割合は,五分が相当である。
従って,被上告人らに対する関係において,乙の損害については四割,上告人丁の損害については三割五分の過失相殺をするのが相当であり,過失相殺後の乙の損害額は三六二四万二七五五円,同上告人の損害額は三七万四八八五円となる。
6 上告人らは,乙の両親として,乙の本件事故による損害賠償請求権を相続により二分の一ずつ取得した。
7 自賠法により甲車について締結された自動車損害賠償責任保険契約(以下,「自賠責保険」という。)に基づき,上告人らは乙の損害の賠償として三〇〇〇万円,上告人丁は自己の損害の賠償として二九万二八六〇円の支払を受けた(以下,これらの支払額を「本件てん補額」という。)。
二 本件訴訟は,上告人らが,上告人丁は乙の相続人及び被害者として,上告人戊は乙の相続人として,被上告人丙に対しては民法七〇九条に基づき,被上告会社に対しては自賠法三条に基づきその損害賠償を請求するものである。その請求額は,各上告人につき乙がてん補を受けるべき損害額(前記一4(一)の損害の九割五分相当額)の二分の一の額から本件てん補額の二分の一の額を控除した残金,上告人丁につき同上告人がてん補を受けるべき損害額(前記一4(二))から本件てん補額を控除した残金に,各上告人につき弁護士費用の損害各一〇〇万円を加算した金員並びに右各残金に対する本件事故発生日の翌日から,及び弁護士費用の損害に対する訴状送達の日の翌日(被上告人丙については平成七年三月一七日,被上告会社については同月一八日)から年五分の割合による遅延損害金である。
被上告人らは,本件てん補額は被上告人らが支払うべき前記一5の過失相殺後の賠償額から控除すべきであると主張するのに対し,上告人らは,本件てん補額は上告人丁及び乙がてん補を受けるべき損害額から控除すべきであって,被上告人らが賠償すべき損害額から控除すべきではないと主張する。
三 原審は,被上告人らの損害賠償責任を認めた上,甲車についての自賠責保険に基づいて上告人らに支払われた金員であっても,本件事故によって生じた損害をてん補するために支払われたものというべきであるから,本件てん補額を被上告人らが賠償すべき損害額から控除すべきことは当然であるとして,上告人らの請求を右控除後の損害額に弁護士費用の損害を加算した金額及びこれらに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容すべきものであるとした。
四 しかし,原審の右判断は是認できない。その理由は,次のとおりである。
1 X及びYが一つの交通事故によってその被害者Zに対して連帯して損害賠償責任を負う場合において,Yの損害賠償責任についてのみ過失相殺がされ,X及びYが賠償すべき損害額が異なることになることがある。この場合,X損害の一部をてん補したときに,そのてん補された額をYが賠償すべき損害額から控除することができるとすると,次のような不合理な結果が生ずる。すなわち,Yは,自己の責任を果たしていないにもかかわらず右控除額だけ責任を免れることになるのに,X無資力のためにその余の賠償をすることができない場合には,Yが右控除後の額について賠償をしたとしても,Zはてん補を受けるべき損害の全額のてん補を受けることができないことになる。また,前記の設例において,X及びYが共に自賠責保険の被保険者である場合を考えると,Xの自賠責保険に基づき損害の一部がてん補された場合に右損害てん補額をYが賠償すべき損害額から控除すると,Yの自賠責保険に基づきてん補されるべき金額はそれだけ減少することになる。その結果,本来は甲,乙の自賠責保険金額の合計額の限度で被害者の損害全部をてん補することが可能な事故の場合であっても,自賠責保険金による損害のてん補が不可能な事態が生じ得る。以上の不合理な結果は,民法の定める不法行為法における公平の理念に反するといわざるを得ない。
したがって,Xがしたてん補の額はZがてん補を受けるべき損害額から控除すべきであって,控除後の残損害額がYが賠償すべき損害額を下回ることにならない限り,Yが賠償すべき損害額に影響しないものと解するのが相当である。
2 これを本件について見ると,本件事故は,被上告人兵藤及び昌睦の過失により発生したものであり,奈津子がてん補を受けるべき損害は,奈津子の過失を考慮すると,五七三八万四三六二円であるところ,昌睦が賠償すべき損害額は右と同額であり,被上告人らが賠償すべき損害額は前記一5の過失相殺後の三六二四万二七五五円である。そして,本件てん補額三〇〇〇万円を右五七三八万四三六二円から控除すると,奈津子の残損害額は二七三八万四三六二円となるから,被上告人らが賠償すべき損害額は,右と同額となる。また,上告人ヒデの損害についても,以上と同様であって,同上告人がてん補を受けるべき損害額は五七万六七四七円であるところ,昌睦が賠償すべき損害額は右と同額であり,被上告人らが賠償すべき損害額は前記過失相殺後の三七万四八八五円であって,本件てん補額二九万二八六〇円を右五七万六七四七円から控除すると,同上告人の残損害額は二八万三八八七円となるから,被上告人らが賠償すべき損害額は,右と同額になる。
3 そうすると,右と異なる原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法があり,右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由がある。
五 以上に説示したところによると,被上告人らは,各自,上告人誠司に対しては,奈津子の右残損害額の二分の一相当の一三六九万二一八一円に弁護士費用の損害として一〇〇万円を加算した一四六九万二一八一円並びにうち一三六九万二一八一円に対する本件事故発生の日である平成五年八月一七日から,及びうち一〇〇万円に対する被上告人兵藤については訴状送達日の翌日である平成七年三月一七日から,被上告人会社については訴状送達日の翌日である同月一八日から各支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払義務があり,上告人ヒデに対しては,奈津子の右残損害額の二分の一相当の一三六九万二一八一円及び同上告人の右残損害額二八万三八八七円に弁護士費用の損害として一〇〇万円を加算した一四九七万六〇六八円並びにうち一三九七万六〇六八円に対する平成五年八月一七日から,及びうち一〇〇万円に対する被上告人兵藤については平成七年三月一七日から,被上告会社については同月一八日から各支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払義務があるから,これと同旨の上告人らの請求はすべて理由がある。したがって,原判決中上告人らの敗訴部分は破棄を免れず,これを主文第一項のとおり変更するのが相当である。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官尾崎行信,裁判官園部逸夫,同千種秀夫,同元原利文,同金谷利廣
共同不法行為と絶対的過失相殺(最判平成15年7月11日民集57巻7号815頁)
共同不法行為者の過失及び被害者の過失が競合する交通事故においていわゆる絶対的過失割合を認定することができる場合における過失相殺の方法と加害者らの賠償責任
主 文
1 原判決を次のとおり変更する。
第1審判決を次のとおり変更する。
(1) 上告人は,被上告人堀口運輸有限会社に対し,53万5862円及びこれに対する平成9年9月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 上告人は,被上告人三重県交通共済協同組合に対し,87万3388円及びこれに対する平成11年9月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 被上告人らのその余の請求を棄却する。
2 上告人と被上告人堀口運輸有限会社との間の訴訟の総費用は,これを10分し,その9を上告人の,その余を被上告人堀口運輸有限会社の負担とし,上告人と被上告人三重県交通共済協同組合との間の訴訟の総費用は,これを3分し,その1を上告人の,その余を被上告人三重県交通共済協同組合の負担とする。
理 由
第1 事案の概要
1 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 上告人の被用者であるAは,平成9年9月20日午前2時25分ころ,片側1車線の三重県松阪市五反田町1丁目1277番先道路(以下「本件道路」という。)上に,普通貨物自動車(以下「上告人車」という。)を西側路側帯から北行車線にはみ出るような状態で駐車させ,非常点滅表示灯等を点灯させることもなかった。被上告人堀口運輸有限会社(以下「被上告会社」という。)の被用者であるBは,そのころ,被上告会社の保有する普通貨物自動車(以下「被上告人車」という。)を運転して,本件道路を南方から北方に向けて進行し,上告人車を避けるため,中央線からはみ出して進行したところ,本件道路を北方から南方に向けて,最高速度として規制されている時速40㎞を上回る時速80㎞以上で進行してきたCの運転に係る普通乗用自動車と衝突した(以下「本件交通事故」という。)。
本件道路は,終日駐車禁止の交通規制がされていたが,追越しのための右側部分はみ出し禁止の交通規制はされていなかった。また,本件道路は,北方から南方に向かう場合,本件交通事故現場の手前約60m付近で左にカーブしており,Cは,被上告人車を左カーブを抜けた地点で発見した。本件交通事故現場付近に街灯はなく,Cの進行方向からは,上記左カーブを抜けた地点より手前で被上告人車を発見することは容易ではなかった。
(2) Aには非常点滅表示灯等を点灯させることなく,上告人車を駐車禁止の車道にはみ出して駐車させた過失,Bには被上告人車を対向車線にはみ出して進行させた過失,Cには速度違反,安全運転義務違反の過失がある。A,B,Cの各過失割合は1対4対1である。
(3) 本件交通事故により,被上告会社は270万3110円の損害を被り,Cは581万1400円の損害を被った。
(4) 被上告人車につき,被上告人三重県交通共済協同組合(以下「被上告組合」という。)を保険者として,自動車共済契約が締結されており,また,被上告人車につき,自動車損害賠償保障法により自動車損害賠償責任保険契約(以下,「自賠責保険」といい,自賠責保険に基づいて支払われる保険金を「自賠責保険金」という。)が締結されていた。
(5) 被上告会社とCとの間では,本件交通事故による損害賠償につき示談が成立し,被上告会社は,Cから,36万5174円の支払を受け,被上告組合は,Cに対し,上記自動車共済契約に基づき,被上告会社に代わって,本件交通事故による損害賠償として474万7654円を支払った。
(6) 被上告会社が本件交通事故による自己の損害額270万3110円のうち上告人及びCに対して請求し得る額の合計は,自己の過失割合6分の4を控除した6分の2に相当する90万1036円である。
(7) 被上告組合は,Cに支払った損害賠償金につき自賠責保険金120万円の支払を受けた。
2 本件は,上告人に対し,被上告会社が自動車損害賠償保障法3条又は民法715条に基づき損害賠償を請求し,Cに損害賠償金を支払った被上告組合が保険代位に基づいて上告人が被上告会社に対して負う求償義務の履行を求める事案である。
第2 上告代理人西村英一郎の上告理由について
1 上告代理人西村英一郎の上告理由第1の2(2)について
原審は,被上告会社が本件交通事故による自己の損害額のうち上告人及び丙に対して請求し得る額の合計を90万1036円とし,丙から36万5174円の支払を受けたとしているので,被上告会社が上告人に対して請求し得る額は53万5862円となる。しかし,原審は,上告人に対し,これを上回る53万8242円の支払を命じており,原判決には理由の食違いがある。この点をいう論旨は理由がある。
2 その余の上告理由について
その余の上告理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,民訴法312条1項又は2項に規定する事由に該当しない。
第3 上告代理人西村英一郎の上告受理申立て理由第3の2(3)について
1 原審は,概要次のとおり判断して,被上告組合の上告人に対する請求を170万6109円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容した。
(1) 丙は,本件交通事故による自己の損害につき,自己の過失割合である6分の1を控除した6分の5の限度で,被上告会社及び上告人に対して,各当事者ごとの相対的な過失割合に従って損害賠償を請求することができる。従って,丙は,581万1400円の6分の5である484万2833円を上限として,被上告会社に対しては581万1400円を丙の過失割合5分の1による過失相殺をした後の464万9120円,上告人に対しては丙の過失割合2分の1による過失相殺をした後の290万5700円を請求し得るものというべきである。
(2) 被上告会社及び上告人の損害賠償義務が競合する範囲は,上記464万9120円と290万5700円を加え,484万2833円を控除した271万1987円であり,被上告会社のみが損害賠償義務を負うのは,上記464万9120円から上記271万1987円を控除した193万7133円である。
被上告会社の負担部分は,上記271万1987円に5分の1を乗じ,上記193万7133円を加えた247万9530円である。
被上告会社は,上告人に対し,丙に対して支払った474万7654円から上記247万9530円を控除した226万8124円を求償することができる。
(3) 被上告組合が支払を受けた自賠責保険金120万円は,被上告会社のみが損害賠償義務を負う範囲,上告人のみが損害賠償義務を負う範囲及び被上告会社と上告人の損害賠償義務が競合する範囲に案分して充当される。従って,上記120万円のうち,被上告会社の求償金から控除すべき金額は56万2015円である。
(4) よって,被上告組合は,上告人に対し,226万8124円から56万2015円を控除した170万6109円を請求することができる。
2 しかし,原審の上記判断は是認できない。その理由は,次のとおりである。
(1) (要約)複数の加害者の過失と被害者の過失が競合する一つの交通事故において,その事故の原因となったすべての過失の割合(以下「絶対的過失割合」という。)を認定できるときは,絶対的過失割合に基づく被害者の過失による過失相殺をした損害賠償額について,加害者らは連帯して共同不法行為に基づく賠償責任を負うものと解すべきである。これに反し,各加害者と被害者との関係ごとにその間の過失の割合に応じて相対的に過失相殺をすることは,被害者が共同不法行為者のいずれからも全額の損害賠償を受けられるとすることによって被害者保護を図ろうとする民法719条の趣旨に反することになる。
(2) 以上説示したところによれば,被上告会社及び上告人は,丙の損害581万1400円につき丙の絶対的過失割合である6分の1による過失相殺をした後の484万2833円(円未満切捨て。以下同じ。)の限度で不真正連帯責任を負担する。このうち,被上告会社の負担部分は5分の4に当たる387万4266円であり,上告人の負担部分は5分の1に当たる96万8566円である。被上告会社に代わり丙に対し損害賠償として474万7654円を支払った被上告組合は,上告人に対し,被上告会社の負担部分を超える87万3388円の求償権を代位取得したというべきである。
なお,自賠責保険金は,被保険者の損害賠償債務の負担による損害をてん補するものであるから,共同不法行為者間の求償関係においては,被保険者の負担部分に充当されるべきである。従って,自賠責保険金120万円は,被上告組合が支払った被上告会社の負担部分に充当される。
そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
第4 結論
以上によれば,被上告会社の請求は,上告人に対し,53万5862円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,被上告組合の請求は,上告人に対し,87万3388円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,被上告人らのその余の請求は理由がないから棄却すべきである。従って,これと異なる原判決を主文のとおり変更する。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官梶谷玄,裁判官福田博,同北川弘治,同亀山継夫,同滝井繁男
共同不法行為の1人との訴訟上の和解(最判平成10年9月10日民集52巻6号1494頁)
共同不法行為者の1人と被害者との訴訟上の和解における債務の免除の効力と求償の範囲
主 文
原判決中,上告人の求償金請求に関し,第一審判決が一〇一四万〇五四八円及びこれに対する平成七年八月三日から支払済みまで年五分の割合による金員の支払請求を棄却した部分について控訴を棄却した部分を破棄する。
前項の部分につき,本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
上告人のその余の上告を棄却する。
前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人加藤豊の上告理由について
一 本件は,被上告人の被用者との共同不法行為により他人に損害を加え,その者との間の訴訟上の和解に基づき和解金を支払った上告人が,右被用者の負担部分につき,使用者である被上告人に対し,求償金として一六〇〇万円及びこれに対する和解金支払の日の翌日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
1 被上告人は,自動車販売等を業とする会社であり,平成六年に日産サニー中部販売株式会社を吸収合併した。同社は,甲(旧姓乙)を従業員として雇用し,自動車販売に従事させていた。甲は,昭和六一年五月以降,同社の半田営業所長の職にあった。
2 上告人は,個人で又は平成元年一〇月に設立した株式会社大豊の代表者として,自動車販売業を営む者である。上告人は,株式会社JXとの間で「オートローン制度取扱に関する契約」を締結し,顧客に自動車を販売するに当たり,代金の分割払を希望する顧客からの申出により,顧客とJXとの間のオートローン契約の締結を仲介していた。
3 甲は,販売実績を挙げたように見せかけるため,実際には販売されていない自動車が販売されたと本社に報告し,新車登録をしていた。甲は,その代金の穴埋めのために,オートローン契約を利用した仮装の自動車販売を企て,知人に仮装の買主となることの承諾を得た上,上告人に仮装の買主のためにオートローン契約を使うことを依頼し,その了承を得た。
4 上告人は,昭和六三年四月二一日ころから平成元年一〇月二五日ころまでの間,甲の依頼に応し,JXと仮装の買主三三名との間の架空のオートローン契約の締結を仲介し,これにより,JXは,売買代金合計三三〇三万八六八一円を上告人に立替払した。上告人は,ほぼその全額を甲に交付した。
5 甲と上告人との右共同不法行為における責任割合は,六対四である。
6 JXは,平成二年一月,上告人に対し,右オートローン制度取扱契約の債務不履行に基づく損害賠償金三三〇三万八六八一円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年六分の割合による遅延損害金の支払を求める別件訴訟を提起した。
7 JXと上告人は,平成七年一月二〇日,別件訴訟において,(1) 上告人は,JXに対し,上告人が甲と共同してJXに加えた損害につき,二〇〇〇万円の支払義務があることを認める,(2)JXはその余の請求を放棄する,との内容の訴訟上の和解(以下「本件和解」という。)をし,同日,上告人はJXに和解金二〇〇〇万円を支払った。
二 原審は,右の事実関係の下において,次のとおり判断し,一八五万九四五二円及びこれに対する支払催告の日の翌日である平成七年八月三日から支払斉みまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,上告人の求償金請求を認容し,その余を棄却すべきものとした。
1 甲の行為と上告人の行為は,JXに対する関係で共同不法行為を構成し,被上告人も,JXに対し民法七一五条一項の使用者責任を負う。一方,上告人の行為は,JXに対する右オートローン制度取扱契約の債務不履行をも構成し,上告人の不法行為責任と債務不履行責任とは請求権競合の関係に立つ。従って,上告人が債務不履行責任を問われた別件訴訟における本件和解により支払った損害賠償金についても,甲及び被上告人に対する求償が認められるべきである。
2 上告人がJXに支払った損害賠償額が甲と上告人との前記責任割合によって定められる自己の負担部分を超えたものであるときは,上告人は,その超える部分につき,被上告人に対し求償権を行使することができる。
3 JXの被った損害額は,少なくとも,別件訴訟において請求していた三三〇三万八六八一円及びこれに対する平成二年二月一日から本件和解金支払時までの年六分の割合による遅延損害金であり,その額は四二八八万八八三三円となる。そして,そのうち不真正連帯関係にあるのは,年五分の割合で遅延損害金を計算した四一二四万七一四一円である。
4 従って,右四一二四万七一四一円に対する上告人の負担部分(四割)は,一六四九万八八五六円であり,これに不真正連帯関係にない遅延損害金一六四万一六九二円を加えた合計一八一四万〇五四八円を超える一八五万九四五二円が,上告人から被上告人に対して求償することができる金額である。
5 そして,上告人と被上告人のJXに対する責任は,各自の立場に応じて別個に生じたもので,ただ同一の損害のてん補を目的とする限度で関連しているにすぎず,右限度以上の関連性はないのであるから,JXが上告人に対し二〇〇〇万円を超える損害賠償債権を放棄ないし免除したとしても,それが債権を満足させるものでない以上,放棄ないし免除した部分を除いた現実の支払額のみを対象として求償金額の範囲を定めるのは相当ではない。
三 しかし,被上告人に対する求償金額の算定に関する原審の右判断は是認できない。その理由は,次のとおりである。
1 甲と乙が共同の不法行為により他人に損害を加えた場合において,甲が乙との責任割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは,甲は,乙の負担部分について求償することができる(最高裁昭和六〇年(オ)第一一四五号同六三年七月一日判決・民集四二巻六号四五一頁,最高裁昭和六三年(オ)第一三八三号,平成三年(オ)第一三七七号同年一〇月二五日判決・民集四五巻七号一一七三頁参照)。
2 この場合,XとYが負担する損害賠償債務は,いわゆる不真正連帯債務であるから,Xと被害者との間で訴訟上の和解が成立し,請求額の一部につき和解金が支払われるとともに,和解調書中に「被害者はその余の請求を放棄する」旨の条項が設けられ,被害者がXに対し残債務を免除したと解し得るときでも,連帯債務における免除の絶対的効力を定めた民法四三七条の規定は適用されず,Yに対して当然に免除の効力が及ぶものではない(最高裁昭和四三年(オ)第四三一号同四八年二月一六日第二小法廷判決・民集二七巻一号九九頁,最高裁平成四年(オ)第一八一四号同六年一一月二四日第一小法廷判決・裁判集民事一七三号四三一頁参照)。
しかし,被害者が,右訴訟上の和解に際し,Yの残債務をも免除する意思を有していると認められるときは,Yに対しても残債務の免除の効力及ぶものというべきである。そして,この場合には,Yはもはや被害者から残債務を訴求される可能性はないのであるから,XのYに対する求償金額は,確定した損害額である右訴訟上の和解におけるXの支払額を基準とし,双方の責任割合に従いその負担部分を定めて,これを算定するのが相当であると解される。
3 以上の理は,本件のように,被用者(A)がその使用者(被上告人)の事業の執行につき第三者(上告人)との共同の不法行為により他人に損害を加えた場合において,右第三者が,自己と被用者との責任割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償し,被用者の負担部分について使用者に対し求償する場合においても異なるところはない(前掲昭和六三年七月一日第二小法廷判決参照)。
4 これを本件について見ると,本件和解調書の記載からはジャックスの意思は明確ではないものの,記録によれば,ジャックスは,被上告人に対して裁判上又は裁判外で残債務の履行を請求した形跡もなく(ちなみに,本件和解時においては,既に右残債権について消滅時効期間が経過していた。),かえって,上告人が被上告人に対してAの負担部分につき求償金の支払を求める本件訴訟の提起に協力する姿勢を示していた等の事情がうかがわれないではない。そうすると,ジャックスとしては,本件和解により被上告人との関係も含めて全面的に紛争の解決を図る意向であり,本件和解において被上告人の残債務をも免除する意思を有していたと解する余地が十分にある。したがって,本件和解に際し,ジャックスが被上告人に対しても残債務を免除する意思を有していたか否かについて審理判断することなく,上告人の被上告人に対する求償金額を算定した原審の判断には,法令の解釈適用の誤り,審理不尽の違法があるというべきである。
5 そして,仮に,本件和解における上告人の支払額二〇〇〇万円を基準とし,原審の確定した前記責任割合に基づき算定した場合には,本件共同不法行為における上告人の負担部分は八〇〇万円となる。従って,上告人は被上告人に対し,その支払額のうち一二〇〇万円の求償をすることができ,右の違法はこの範囲で原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。この点をいう論旨は理由がある(なお,上告人は,当審において,不服申立ての範囲を一二〇〇万円の求償金請求に関する部分に限定している。)。
四 以上によれば,その余の上告理由について判断するまでもなく,原判決中,本判決主文第一項掲記の部分は破棄を免れず,右部分については更に審理を尽くさせる必要があるので,これを原審に差し戻すこととし,また,遅延損害金の起算点に関する原審の判断は正当として是認できるから,上告人のその余の上告を棄却することとする。
最高裁裁判長裁判官藤井正雄,裁判官小野幹雄,同遠藤光男,同井嶋一友,同大出峻郎
順次複数事故と損害(最判平成8年5月31日民集50巻6号1323頁)
ア 交通事故被害者がその後に第2の交通事故で死亡した場合,第1事故の後遺障害による財産上の損害額の算定につき被害者の死亡を考慮できるか
イ 被害者が事故後に死亡した場合に後遺障害損害の額の算定に当たり死亡後の生活費を控除できるか
上告代理人吉澤功の上告理由第一点について
所論の点に関する原審の認定判断は,原判決挙示の証拠関係に照らし,正当として是認することができ,その過程に所論の違法はない。論旨は,原審の専権に属する証拠の取捨判断,事実の認定を非難するか,又は原審の認定に沿わない事実に基づいて原判決を論難するものにすぎず,採用できない。
同第二点について
一 原審の適法に確定したところによれば,平成2年4月15日,千葉県八日市場市内の県道上を甲が自動二輪車を運転して走行中,上告人が普通貨物自動車を運転して沿道のガソリンスタンド敷地内から右自動二輪車の走行車線上に進入したため,同車が右普通貨物自動車との衝突を回避しようとして急制動し,転倒する事故(以下「本件交通事故」という。)が発生し,甲は,これにより左膝開放骨折,右第五中手骨骨折の傷害を負って,平成3年9月19日まで入通院して治療を受けた結果,左膝痛,右小指関節部痛,右第五中手骨変形等の後遺障害(以下「本件後遺障害」という。)を残して症状が固定したが,同年12月11日,本件とは別の交通事故(以下「別件交通事故」という。)により死亡した,というのである。
甲の相続人である被上告人らは,本件において,甲の本件後遺障害による損害として,甲が平成3年3月に高等学校を卒業して同年四月に就職した場合のその後の10年間についての労働能力の一部喪失を理由とする逸失利益を主張している。
二 交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害のために労働能力の一部を喪失した場合における財産上の損害の額を算定するに当たっては,その後に被害者が死亡したとしても,交通事故の時点で,その死亡の原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,右死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきものではないと解するのが相当である(最高裁平成五年(オ)第五二七号同八年四月二五日判決・民集五〇巻五号登載予定参照)。
右のように解すべきことは,被害者の死亡が病気,事故,自殺,天災等のいかなる事由に基づくものか,死亡につき不法行為等に基づく責任を負担すべき第三者が存在するかどうか,交通事故と死亡との間に相当因果関係ないし条件関係が存在するかどうかといった事情によって異なるものではない。本件のように被害者が第二の交通事故によって死亡した場合,それが第三者の不法行為によるものであっても,右第三者の負担すべき賠償額は最初の交通事故に基づく後遺障害により低下した被害者の労働能力を前提として算定すべきものであるから,前記のように解することによって初めて,被害者ないしその遺族が,前後二つの交通事故により被害者の被った全損害についての賠償を受けることが可能となるのである。
三 また,交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害のために労働能力の一部を喪失した後に死亡した場合,労働能力の一部喪失による財産上の損害の額の算定に当たっては,交通事故と被害者の死亡との間に相当因果関係があって死亡による損害の賠償をも請求できる場合に限り,死亡後の生活費を控除することができると解するのが相当である。何故なら,交通事故と死亡との間の相当因果関係が認められない場合には,被害者が死亡により生活費の支出を必要としなくなったことは,損害の原因と同一原因により生じたものということができず,両者は損益相殺の法理又はその類推適用により控除すべき損失と利得との関係にないからである。
四 これを本件についてみるに,前記事実関係によれば,甲は,本件後遺障害により労働能力の一部を喪失し,これによる損害を被っていたところ,別件交通事故による甲の死亡については,前記の特段の事情があるとは認められず,また,本件交通事故との間の相当因果関係も認められない。従って,右労働能力喪失による財産上の損害額の算定に当たっては,別件交通事故による甲の死亡の事実を就労可能期間の算定上考慮すべきではなく,また,甲の死亡後の生活費を控除することもできない。
原判決は,結論においてこれと同旨をいうものであって,正当として是認できる。論旨は,独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず,採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官,河合伸一,裁判官大西勝也,同根岸重治,同福田 博
交通事故と医療事故の共同不法行為(最判平成13年3月13日民集55巻2号328頁)
交通事故と医療事故とが順次競合して共同不法行為に当たる場合の各不法行為者が責任を問うべき損害額を被害者の損害額の一部に限定できるか
上告代理人森永友健の上告受理申立て理由第一ないし第三及び第五について
1 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 上告人らの長男である甲(昭和57年1月生)は,昭和63年9月12日午後3時40分ころ,埼玉県上福岡市○○先路上において,自転車を運転し,一時停止を怠って時速約15㎞の速度で交通整理の行われていない交差点内に進入したところ,同交差点内に減速することなく進入しようとした上告補助参加人K自動車会社の従業員である同乙運転に係る普通乗用自動車と接触し,転倒した(以下「本件交通事故」という。)。
(2) 甲は,本件交通事故後直ちに,救急車で被上告人が経営する上福岡第二病院(以下「被上告人病院」という。)に搬送された。被上告人の代表者で被上告人病院院長である丙医師は,甲を診察し,左頭部に軽い皮下挫傷による点状出血を,顔面表皮に軽度の挫傷を認めたが,甲の意識が清明で外観上は異常が認められず,甲が事故態様についてタクシーと軽く衝突したとの説明をし,前記負傷部分の痛みを訴えたのみであったことから,甲の歩行中の軽微な事故であると考えた。そして,丙医師は,甲の頭部正面及び左側面から撮影したレントゲン写真を検討し,頭がい骨骨折を発見しなかったことから,さらに甲について頭部のCT検査をしたり,病院内で相当時間経過観察をするまでの必要はないと判断し,前記負傷部分を消毒し,抗生物質を服用させる治療をした上,甲及び上告人丁に対し,「明日は学校へ行ってもよいが,体育は止めるように。明日も診察を受けに来るように。」「何か変わったことがあれば来るように。」との一般的指示をしたのみで,甲を帰宅させた。
(3) 上告人丁は,甲とともに午後5時30分ころ帰宅したが,甲が帰宅直後におう吐し,眠気を訴えたため,疲労のためと考えてそのまま寝かせたところ,甲は,夕食を欲しがることもなく午後6時30分ころに寝入った。甲は,同日午後7時ころには,いびきをかいたり,よだれを流したりするようになり,かなり汗をかくようになっていたが,上告人らは,多少の異常は感じたものの,甲は普段でもいびきをかいたりよだれを流したりして寝ることがあったことから,この容態を重大なこととは考えず,同日午後7時30分ころ,氷枕を使用させ,そのままにしておいた。しかし,甲は,同日午後11時ころには,体温が39度まで上昇してけいれん様の症状を示し,午後11時50分ころにはいびきをかかなくなったため,上告人らは初めて甲が重篤な状況にあるものと疑うに至り,翌13日午前0時17分ころ,救急車を要請した。救急車は同日午前0時25分に上告人方に到着したが,甲は,既に脈が触れず呼吸も停止しており,同日午前0時44分,三芳厚生病院に搬送されたが,同日午前0時45分,死亡した(以下「本件医療事故」という。)。
(4) 甲は,頭がい外面線状骨折による硬膜動脈損傷を原因とする硬膜外血しゅにより死亡したものであり,被上告人病院から帰宅したころには,脳出血による脳圧の亢進によりおう吐の症状が発現し,午後6時ころには傾眠状態を示し,いびき,よだれを伴う睡眠,脳の機能障害が発生し,午後11時ころには,治療が困難な程度であるけいれん様の症状を示す除脳硬直が始まり,午後11時50分には自発呼吸が不可能な容態になったものである。
硬膜外血しゅは,骨折を伴わずに発生することもあり,また,当初相当期間の意識清明期が存することが特徴であって,その後,頭痛,おう吐,傾眠,意識障害等の経過をたどり,脳障害である除脳硬直が開始した後はその救命率が著しく減少し,仮に救命に成功したとしても重い後遺障害をもたらすおそれが高いものであるが,早期に血しゅの除去を行えば予後は良く,高い確率での救命可能性があるものである。従って,交通事故により頭部に強い衝撃を受けている可能性のある甲の診療に当たった丙医師は,外見上の傷害の程度にかかわらず,当該患者ないしその看護者に対し,病院内にとどめて経過観察をするか,仮にやむを得ず帰宅させるにしても,事故後に意識が清明であってもその後硬膜外血しゅの発生に至る脳出血の進行が発生することがあること及びその典型的な前記症状を具体的に説明し,事故後少なくとも6時間以上は慎重な経過観察と,前記症状の疑いが発見されたときには直ちに医師の診察を受ける必要があること等を教示,指導すべき義務が存したのであって,丙医師にはこれを懈怠した過失がある。
(5) 他方,上告人らにおいても,除脳硬直が発生して呼吸停止の容態に陥るまで甲が重篤な状態に至っていることに気付くことなく,何らの措置をも講じなかった点において,甲の経過観察や保護義務を懈怠した過失があり,その過失割合は1割が相当である。
(6) なお,本件交通事故は,本件交差点に進入するに際し,自動車運転手として遵守すべき注意義務を懈怠した,上告補助参加人乙の過失によるものであるが,甲にも,交差点に進入するに際しての一時停止義務,左右の安全確認義務を怠った過失があり,その過失割合は3割が相当である。
(7) 上告人らは,甲の本件交通事故及び本件医療事故による次の損害賠償請求権を各2分の1の割合で相続した。甲の死亡による上告人らの弁護士費用分を除く全損害は,次のとおりである。
逸失利益 2378万8076円
慰謝料 1600万円
葬儀費用 100万円
なお,上告人らは,上告補助参加人K自動車会社から葬儀費用として50万円の支払を受けた。
2 本件は,上告人らが,丙医師の診療行為の過失により甲が死亡したとして,被上告人に対し,民法709条に基づき損害賠償を求めている事案である。
原審は,前記事実関係の下において,概要次のとおり判断した。
(1) 被害者である甲の死亡事故は,本件交通事故と本件医療事故が競合した結果発生したものであるところ,原因競合の寄与度を特定して主張立証することに困難を伴うので,被害者保護の見地から,本件交通事故における上告補助参加人乙の過失行為と本件医療事故における丙医師の過失行為とを共同不法行為として,被害者は,各不法行為に基づく損害賠償請求を分別することなく,全額の損害の賠償を請求することもできると解すべきである。
(2) しかし,本件の場合のように,個々の不法行為が当該事故の全体の一部を時間的前後関係において構成し,その行為類型が異なり,行為の本質や過失構造が異なり,かつ,共同不法行為を構成する一方又は双方の不法行為につき,被害者側に過失相殺すべき事由が存する場合には,各不法行為者は,各不法行為の損害発生に対する寄与度の分別を主張することができ,かつ,個別的に過失相殺の主張をすることができるものと解すべきである。すなわち,被害者の被った損害の全額を算定した上,各加害行為の寄与度に応じてこれを案分して割り付け,その上で個々の不法行為についての過失相殺をして,各不法行為者が責任を負うべき損害賠償額を分別して認定するのが相当である。
(3) 本件においては,甲の死亡の経過等を総合して判断すると,本件交通事故と本件医療事故の各寄与度は,それぞれ5割と推認するのが相当であるから,被上告人が賠償すべき損害額は,甲の死亡による弁護士費用分を除く全損害4078万8076円の5割である2039万4038円から本件医療事故における被害者側の過失1割を過失相殺した上で弁護士費用180万円を加算した2015万4634円と算定し,上告人らの請求をこの金員の2分の1である各1007万7317円及びうち917万7317円に対する本件医療事故の後である昭和63年9月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容すべきものである。
3 しかし,原審の前記2(2)(3)の判断は是認できない。その理由は,次のとおりである。
原審の確定した事実関係によれば,本件交通事故により,甲は放置すれば死亡するに至る傷害を負ったものの,事故後搬入された被上告人病院において,甲に対し通常期待されるべき適切な経過観察がされるなどして脳内出血が早期に発見され適切な治療が施されていれば,高度の蓋然性をもって甲を救命できたということができるから,本件交通事故と本件医療事故とのいずれもが,甲の死亡という不可分の一個の結果を招来し,この結果について相当因果関係を有する関係にある。したがって本件交通事故における運転行為と本件医療事故における医療行為とは民法719条所定の共同不法行為に当たるから,各不法行為者は被害者の被った損害の全額について連帯して責任を負うべきものである。本件のようにそれぞれ独立して成立する複数の不法行為が順次競合した共同不法行為においても別異に解する理由はないから,被害者との関係においては,各不法行為者の結果発生に対する寄与の割合をもって被害者の被った損害の額を案分し,各不法行為者において責任を負うべき損害額を限定することは許されないと解するのが相当である。けだし,共同不法行為によって被害者の被った損害は,各不法行為者の行為のいずれとの関係でも相当因果関係に立つものとして,各不法行為者はその全額を負担すべきものであり,各不法行為者が賠償すべき損害額を案分,限定することは連帯関係を免除することとなり,共同不法行為者のいずれからも全額の損害賠償を受けられるとしている民法719条の明文に反し,これにより被害者保護を図る同条の趣旨を没却することとなり,損害の負担について公平の理念に反することとなるからである。
従って原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法があり,この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由がある。
4 本件は,本件交通事故と本件医療事故という加害者及び侵害行為を異にする二つの不法行為が順次競合した共同不法行為であり,各不法行為については加害者及び被害者の過失の内容も別異の性質を有するものである。ところで,過失相殺は不法行為により生じた損害について加害者と被害者との間においてそれぞれの過失の割合を基準にして相対的な負担の公平を図る制度であるから本件のような共同不法行為においても,過失相殺は各不法行為の加害者と被害者との間の過失の割合に応じてすべきものであり,他の不法行為者と被害者との間における過失の割合をしん酌して過失相殺をすることは許されない。
本件において被上告人の負担すべき損害額は,甲の死亡による上告人らの損害の全額(弁護士費用を除く。)である4078万8076円につき被害者側の過失を1割として過失相殺による減額をした3670万9268円から上告補助参加人川越乗用自動車株式会社から葬儀費用として支払を受けた50万円を控除し,これに弁護士費用相当額180万円を加算した3800万9268円となる。従って,上告人ら各自の請求できる損害額は,この2分の1である1900万4634円となる。
5 以上によれば,上告人らの本件請求は,各自1900万4634円及びうち1810万4634円に対する本件医療事故の後である昭和63年9月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,その余は理由がないから棄却すべきである。従って,これと異なる原判決は,主文第1項のとおり変更する。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官元原利文,裁判官千種秀夫,同金谷利廣,同奥田昌道
過失相殺等
過失相殺に関する重要裁判例(最高裁判所判決等)を実装しました。
過失相殺と事理弁識能力(最判昭和39年6月24日民集18巻5号854頁)
民法第七二二条第二項により被害者の過失を斟酌するについて必要な被害者の弁識能力の程度
主 文
本件各上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人奥嶋庄治郎の上告理由について。
未成年者が他人に加えた損害につき,その不法行為上の賠償責任を問うには,未成年者がその行為の責任を弁識するに足る知能を具えていることを要することは民法七一二条の規定するところであるが,他人の不法行為により未成年者がこうむった損害の賠償額を定めるにつき,被害者たる未成年者の過失をしんしゃくするためには,未成年者にいかなる知能が具わっていることを要するかに関しては,民法には別段の規定はなく,ただ,この場合においても,被害者たる未成年者においてその行為の責任を弁識するに足る知能を具えていないときは,その不注意を直ちに被害者の過失となし民法七二二条二項を適用すべきではないとする当裁判所の判例(昭和二九年(オ)第七二六号,同三一年七月二〇日第二小法廷判決)があることは,所論のとおりである。しかしながら,民法七二二条二項の過失相殺の問題は,不法行為者に対し積極的に損害賠償責任を負わせる問題とは趣を異にし,不法行為者が責任を負うべき損害賠償の額を定めるにつき,公平の見地から,損害発生についての被害者の不注意をいかにしんしゃくするかの問題に過ぎないのであるから,被害者たる未成年者の過失をしんしゃくする場合においても,未成年者に事理を弁識するに足る知能が具わっていれば足り,未成年者に対し不法行為責任を負わせる場合のごとく,行為の責任を弁識するに足る知能が具わっていることを要しないものと解するのが相当である。したがって,前示判例は,これを変更すべきものと認める。
原審の確定するところによれば,本件被害者らは,事故当時は満八才余の普通健康体を有する男子であり,また,当時すでに小学校二年生として,日頃学校及び家庭で交通の危険につき充分訓戒されており,交通の危険につき弁識があったものと推定することができるというのであり,右認定は原判決挙示の証拠関係に照らし肯認するに足る。右によれば,本件被害者らは事理を弁識するに足る知能を具えていたものというべきであるから,原審が,右事実関係の下において,進んで被害者らの過失を認定した上,本件損害賠償額を決定するにつき右過失をしんしゃくしたのは正当であり,所論掲記の判例(昭和二八年(オ)第九一号,同三二年六月二〇日第一小法廷判決)は事案を異にし本件の場合に適切でない。所論は,採用することをえない。
よって,民訴四〇一条,九五条,九三条,八九条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官横田喜三郎,同入江俊郎,同奥野健一,同石坂修一,同山田作之助,同横田正俊,同斎藤朔郎,同草鹿浅之介,同長部謹吾,同城戸芳彦,同石田和外
裁判官河村又介,同下飯坂潤夫は退官につき,署名押印することができない。
裁判長裁判官横田喜三郎
使用者の不法行為と過失相殺(最判平成20年3月27日裁判集民事227号585頁)
業務上の過重負荷と基礎疾患とが共に原因で従業員が死亡した場合使用者の不法行為を理由とする損害賠償額を算定につき,使用者による過失相殺の主張が訴訟上の信義則に反するとして民法722条2項の規定を類推しなかった原審は違法
主 文
原判決を破棄する。
本件を札幌高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人冨岡公治ほかの上告受理申立て理由第4について
1 本件は,上告人の従業員であった甲(以下「甲」という。)の相続人である被上告人らが,甲が急性心筋虚血で死亡したのは,上告人が甲の健康状態に対して十分な注意を払わずに甲をして宿泊を伴う研修に参加させたことなどが原因であるとして,上告人に対し,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償を求めている事案である。
2 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 事実関係
ア 甲(昭和18年*月*日生まれ)は,昭和37年に日本電信電話公社に入社して旭川事業所に配属され,その後,その雇用関係は,同公社から日本電信電話株式会社を経て上告人に引き継がれた。
イ 甲は,平成5年5月に職場の定期健康診断で心電図の異常を指摘され,同年7月に市立旭川病院に入院して精密検査を受けた結果,陳旧性心筋梗塞と診断された。その際,甲には,遺伝的に総コレステロール値が高くなる疾患で,虚血性心疾患の危険因子となる家族性高コレステロール血症(ヘテロ型)が認められた。甲は,同年8月及び同年12月に同病院に入院して経皮的経管的冠状動脈血管形成術の手術を受けるなどしたが,結局,冠状動脈の2枝に障害のある状態は改善されず,その後は内服治療を続けることとなった。
ウ 上告人においては,平成13年4月以降,事業構造改革が進められていたところ,甲は,これに伴う雇用形態及び処遇体系の選択に当たり,上告人との雇用契約を継続し,60歳を定年として法人営業等の業務に従事することなどを条件とする「60歳満了型」を選択したため,同14年4月24日付けで法人営業部門に配置換えとなり,法人営業に必要な技能等の習得を目的とする研修(以下「本件研修」という。)への参加を命じられた。本件研修は,同日から約2か月間にわたって,札幌市内や東京都内の上告人の研修施設等で行われたものであり,その研修期間中,研修施設やホテルでの宿泊を伴うものであった。
エ 甲は,平成14年6月7日,札幌市内での研修終了後に旭川市内の自宅に帰宅し,日曜日である同月9日の午前中,墓参りのため北海道樺戸郡新十津川町所在の先祖の墓に1人で出かけたが,同日午後10時過ぎころ,先祖の墓の前で死亡しているのを発見された。
オ 甲の直接の死因は急性心筋虚血であるが,これは,上告人における事業構造改革に伴う雇用形態及び処遇体系の選択の際の精神的ストレス並びに本件研修への参加に伴う精神的,肉体的ストレスが,前記のとおりの基礎疾患を有していた甲の冠状動脈の状態を自然の経過を超えて増悪させ,心筋梗塞などの冠状動脈疾患等が発症したことによるものであった。
(2) 本件訴訟の経過
ア 上告人は,第1審の第8回口頭弁論期日に陳述した平成16年3月31日付け準備書面において,甲は,死亡した当日,墓の手入れのためにスコップを持参して地面を掘り起こす運動を行って心臓に激しい突発的な負荷をかけたものであるとし,甲の死亡については,甲の自己健康管理保持に著しい過失があり,また,甲がスコップを持参して墓の手入れに行くことを制止しなかった被上告人らにも過失がある旨主張したが,同期日において,これは過失相殺を主張する趣旨ではない旨釈明した。その後,第1審において,上告人から本件につき過失相殺をすべきである旨の主張がされたことはなかった。
なお,第1審において,甲が家族性高コレステロール血症にり患していること又はその疑いのあることを示す文書(甲第11号証の市立旭川病院の入院経過概要)が書証として提出されていたが,被上告人らが提出したその訳文(甲第13号証)では,家族性高コレステロール血症を示す略語である「FH」が脂肪肝と誤訳されたり,当該部分の翻訳が省略されたりしていた。第1審において,甲が家族性高コレステロール血症にり患していた旨の主張は,上告人からも被上告人らからもされることはなかった。
イ 第1審判決は,上告人の不法行為責任を認め,上告人に対し被上告人ら各自に3314万1886円及びこれに対する遅延損害金を支払うよう命ずる限度で被上告人らの請求を認容したが,その理由中において,甲につき動脈硬化に関する遺伝的素因等を具体的に認めるに足りる的確な証拠が見当たらない旨述べており,過失相殺については何ら言及しなかった。
ウ 上告人は,控訴理由を記載した平成17年5月11日付け準備書面において,甲が家族性高コレステロール血症にり患していたことを指摘し,また,同年6月27日付け準備書面(原審第2回口頭弁論期日に陳述)において,予備的主張として,甲が陳旧性心筋梗塞の合併症を有する家族性高コレステロール血症にり患していたことなどから,過失相殺に関する規定を類推適用して上告人が賠償すべき金額を減額すべきである旨主張した。
3 原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断し,上告人の不法行為を理由とする被上告人らに対する損害賠償の額を定めるに当たり過失相殺に関する規定(民法722条2項)の類推適用をしなかった。
(1) 上告人は,第1審において過失相殺を主張しない旨釈明しているところ,控訴審において過失相殺に関する規定の類推適用を主張することは,著しく信義に反するものであり,また,第1審の軽視にもつながるものである。従って,上告人の上記主張は,訴訟上の信義則に反するものとして許されない。
(2) 上記の経緯に照らすと,本件において,上告人の主張がないのに過失相殺に関する規定を類推適用することは相当でない。
4 しかし,原審の上記判断は是認できない。その理由は,次のとおりである。
(1) 被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合において,当該疾患の態様,程度等に照らし,加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは,裁判所は,損害賠償の額を定めるに当たり,民法722条2項の規定を類推適用して,被害者の疾患をしんしゃくすることができる(最高裁昭和63年(オ)第1094号平成4年6月25日第一小法廷判決・民集46巻4号400頁参照)。このことは,労災事故による損害賠償請求の場合においても,基本的に同様であると解される。
また,同項の規定による過失相殺については,賠償義務者から過失相殺の主張がなくとも,裁判所は訴訟にあらわれた資料に基づき被害者に過失があると認めるべき場合には,損害賠償の額を定めるに当たり,職権をもってこれをしんしゃくすることができる(最高裁昭和39年(オ)第437号同41年6月21日第三小法廷判決・民集20巻5号1078頁参照)。このことは,同項の規定を類推適用する場合においても,別異に解すべき理由はない。
(2) 前記事実関係等によれば,甲が急性心筋虚血により死亡するに至ったことについては,業務上の過重負荷とAが有していた基礎疾患とが共に原因となったものということができるところ,家族性高コレステロール血症(ヘテロ型)にり患し,冠状動脈の2枝に障害があり,陳旧性心筋梗塞の合併症を有していたという甲の基礎疾患の態様,程度,本件における不法行為の態様等に照らせば,上告人に甲の死亡による損害の全部を賠償させることは,公平を失するものといわざるを得ない。
原審は,前記3(1)記載の理由により,上告人が原審において過失相殺に関する規定の類推適用を主張することは訴訟上の信義則に反するものとして許されないというのであるが,そもそも,裁判所が過失相殺に関する規定を類推適用するには賠償義務者によるその旨の主張を要しないことは前述のとおりであり,この点をおくとしても,前記2(2)記載の本件訴訟の経過にかんがみれば,第1審の段階では上告人において甲が家族性高コレステロール血症にり患していた事実を認識していなかったことがうかがわれるのであって,上告甲の上記主張が訴訟上の信義則に反するものということもできない。
(3) そうすると,上告人の不法行為を理由とする被上告人らに対する損害賠償の額を定めるに当たり過失相殺に関する規定(民法722条2項)の類推適用をしなかった原審の判断には,過失相殺に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきである。
5 以上のとおり,原審の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,本件については,更に審理を尽くさせるため,原審に差し戻すのが相当である。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官才口千晴,裁判官横尾和子,同甲斐中辰夫,同泉徳治,同涌井紀夫
民法722条の被害者の範囲(最判昭和42年6月27日民集21巻6号1507頁)
被害者本人が幼児である場合と民法722条2項にいう被害者の範囲
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人池田正映の上告理由について。
民法722条2項に定める被害者の過失とは単に被害者本人の過失のみでなく,ひろく被害者側の過失をも包含する趣旨と解すべきではあるが,本件のように被害者本人が幼児である場合において,右にいう被害者側の過失とは,例えば被害者に対する監督者である父母ないしはその被用者である家事使用人などのように,被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失をいうものと解するを相当とし,所論のように両親より幼児の監護を委託された者の被用者のような被害者と一体をなすとみられない者の過失はこれに含まれないものと解すべきである。何故なら,同条項が損害賠償の額を定めるにあたって被害者の過失を斟酌することができる旨を定めたのは,発生した損害を加害者と被害者との間において公平に分担させるという公平の理念に基づくものである以上,被害者と一体をなすとみられない者の過失を斟酌することは,第三者の過失によって生じた損害を被害者の負担に帰せしめ,加害者の負担を免ずることとなり,却って公平の理念に反する結果となるからである。
原審の確定した事実によれば,城東保育園保母甲の被害者乙を監護するについての過失が本件事故発生の一因となっているのであるが,乙の通園する右保育園と被上告人らを含む園児の保護者との間には,園児の登園帰宅の際には一定の区間は保育園側において監護の責任を受けもつ旨の取極めがされていたとはいえ,右甲は,乙の両親である被上告人らより直接に委託を受け被上告人らの被用者として乙の監護をしていたのではなく,城東保育園の被用者として本件事故当日乙その他の園児を引率監護していたに過ぎないというのであるから,右の事実関係に基づけば,甲は,被害者乙と一体をなすとみられるような関係を有する者と解することはできず,右甲の過失をもって民法七二二条二項に定める被害者の過失にあたるとすることはできない。従って,これと同旨の原審の判断は正当であり,論旨は理由がない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条,九三条に従い,裁判官全員の一致で,主文とおり判決する。
最高裁裁判長裁判官横田正俊,同柏原語六,同田中二郎,同下村三郎,同松本正雄
被害者側の過失(最判昭和34年11月26日民集13巻12号1573頁)
慰藉料を請求する父母の一方に過失のある場合と民法第722条第2項
上告人両名代理人弁護士前田慶一の上告理由第一,二点について。
原判決の引用した第一審判決は,その挙示の証拠により上告人甲は本件トラックを運転し,本件事故発生の地点にさしかかった際,乙(当時八歳)が進路左側から右側に向け進路前方を横断しようとして進出したのに気付かず,約八米に接近して初めて乙を発見し急遽急停車の措置をとったが,間に合わず,右トラックを乙に激突させたものと認定した上(乙が上告人甲において何ら応急の処置もとり得ない予測し難い地点から突然飛出して来たとは認定していない),以上のような事実関係であるから,本件事故は上告人甲の前方注視の義務を怠った過失に起因するものであると判断しているのであって,前示証拠に照合すれば右のような事実認定も首肯できないことはなく,そして右事実に基づき上告人甲に前方を注視する義務を怠った過失あるを免れないものとした判断もこれを正当と認めざるを得ない。所論る述の要旨は右認定事実と異る事実関係を想定して上告人甲の無過失を論証せんとするものであって,結局原審の専権に属する事実認定の非難に帰する。なお,所論は本件事故に関する刑事判決を云為するが右判決の内容が如何ようにもあれ,原審としてこれに一致する判断をしなければならない筋合はなく,また右判決と一致しない事実認定をするについて第一審判決の説明以上の場面を附け加えなければならないわけもない。されば原判決には所論の違法ありというを得ず,所論は採用できない。
同第三点について。
按ずるに,民法722条にいわゆる過失とは単に被害者本人の過失のみでなく,ひろく被害者側の過失をも包含する趣旨と解するを相当とする。従って本件のような場合被害者乙の過失だけでなく,もし,事故発生の際乙の監督義務者の如きものが同伴しおり,同人において乙を抑制できたにもかかわらず,不注意にも抑制しなかったというのであれば,原審としてはその同伴者の過失を斟酌したであろうやも測り難いのである。然るに記録によっても明かなように,上告人らは原審において右過失の斟酌さるべきことを主張したにもかかわらず,原審はその点について何ら考慮を運らした形跡がないのであるから,原判決はこの点において審理不尽,理由不備の欠陥を蔵するものと云うの外なく,論旨は結局理由あるに帰する。よって,右の点について更に審理をつくさせるため,原判決はこれを破棄し本件はこれを原裁判所に差戻すを相当とし,民訴四〇七条一項に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官下飯坂潤夫,裁判官斎藤悠輔,同高木常七
被害者側の過失(最判昭和51年3月25日民集30巻2号160頁)
夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被つた場合において夫にも過失があるとき民法722条2項
上告代理人中島一郎の上告理由について
民法722条2項が不法行為による損害賠償の額を定めるにつき被害者の過失を斟酌することができる旨を定めたのは,不法行為によって発生した損害を加害者と被害者との間において公平に分担させるという公平の理念に基づくものであると考えられるから,右被害者の過失には,被害者本人と身分上,生活関係上,一体をなすとみられるような関係にある者の過失,すなわちいわゆる被害者側の過失をも包含する。従って,夫が妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが,右第三者と夫との双方の過失の競合により衝突したため,傷害を被った妻が右第三者に対し損害賠償を請求する場合の損害額を算定するについては,右夫婦の婚姻関係が既に破綻にひんしているなど特段の事情のない限り,夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができるものと解するのを相当とする。このように解するときは,加害者が,いったん被害者である妻に対して全損害を賠償した後,夫にその過失に応じた負担部分を求償するという求償関係をも一挙に解決し,紛争を一回で処理することができるという合理性もある。
これを本件についてみると,原判決は,被上告人甲は夫である被上告人乙の運転する自動車に同乗して岩手県盛岡市○町○丁目先の道路を進行中,上告人丙の運転する上告人有限会社北州急行所有の自動車に衝突され,傷害を被ったものであり,右交通事故における上告人丙と被上告人乙の過失の割合は,五対五であるが,被上告人甲自身に過失はなく,同被上告人が被った損害額を定めるについて,夫である被上告人乙の過失は斟酌すべきではないとするものである。
しかし,前記のとおり,夫の運転する自動車に同乗していた妻が第三者の運転する自動車に衝突されて,傷害を被った場合に,その損害額を定めるにつき,特段の事情のない限り,運転者である夫の過失を被害者側の過失として斟酌すべきであるから,原判決には,この点について法令の解釈適用を誤った違法があり,右違法が判決に影響を及ぼすことは,明らかである。従って,右の点についての論旨は理由があり,原判決中破上告人甲に関する上告人ら敗訴部分は破棄を免れず,前記特段の事情の有無,同被上告人の損害額を定めるについての過失の割合等について,更に審理を尽くさせるため,右部分につき本件を原審に差し戻すこととし,上告人らの被上告人乙に対する上告は,理由がないから棄却する。
よつて,民訴法四〇七条一項,三九六条,三八四条,九五条,九三条,八九条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官岸盛一,裁判官藤林益三,同下田武三,同岸上康夫,同団藤重光
被害者側の過失(最判昭和56年2月17日裁判集民事132号149頁)
被害自動車の運転者と同乗中の被害者が同じ職場に勤務する同僚である場合と民法722条2項の適用の有無
上告代理人最所憲治の上告理由第二点について
原審は,加害車の運転者である被上告人の過失相殺の主張について判断するにあたり,上告人が同乗していた被害車の運転者である訴外人Aの本件事故における過失割合を四割と認めたうえ,上告人と訴外人Aとは身分上,生活関係上一体をなす関係にあるものとして,被上告人が上告人に対して支払うべき損害賠償額から右過失割合に相当する金額を控除している。
しかしながら,原審が確定したところによれば,上告人と訴外人Aとは,訴外大神孝志が経営する寿司店に勤務する同僚であって,上告人がX所有の被害車の助手席に乗り,訴外人がこれを運転中に本件事故を惹起したというにとどまるから,上告人と訴外人Aとは,他に特段の事情がない限り,身分上,生活関係上一体をなす関係にあると認めることは相当でないものといわなければならない。したがって,原審が,他に特段の事情があることを確定することなしに,同じ職場に勤務する同僚であるというだけの事実から,直ちに,上告人と訴外人Aとは身分上,生活関係上一体をなす関係にあるものと判断したことは,民法722条2項の解釈適用を誤り,ひいて審理不尽,理由不備の違法を犯したものといわざるをえず,右法令違背が原判決に影響を及ぼすことは明らかであるから,論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。
よって,その余の上告理由の判断を省略して,さらに審理を尽くさせるため本件を福岡高裁に差し戻すこととし,民訴法四〇七条一項に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官環昌一,裁判官横井大三,同伊藤正己,同寺田治郎
上告代理人最所憲治の上告理由
第一点《略》
第二点,原判決は訴外谷と上告人が身分上及び生活関係上一体をなすとして,訴外谷の過失を被害者側の過失として上告人の損害額算定について斟酌している。
一般的に言って,民法第七二二条二項の被害者の過失が,単に被害者本人の過失のみでなく,被害者と身分上ないし生活関係上一体をなすものとみられる関係にある者の過失を含むことは承認される。
しかし,上告人と訴外谷とは,同じ寿司店に勤務する単なる同僚の関係にすぎない。両者は,同一の仕事に従事するだけの関係であり,仕事外のことについては各々全く独立した存在であり,共同生活をしているという事実もない。
上告人と訴外谷とは,いわゆる財布を共通にする関係でもなく,訴外谷の過失を上告人の過失として斟酌することが,夫婦間におけるが如く求償関係を一挙に解決するような結果にもならない。
訴外谷が上告人に損害を与えれば,同僚であっても上告人は訴外谷に対して損害賠償請求権が発生するのであって,訴外谷の行為に起因する損害を,同人が同僚であるからと言って,上告人が自から惹起した損害として忍受すべきなんらの合理的理由は存しない。
右の理は,訴外谷が被上告人との共同行為によって不法に上告人に損害を与えた場合にも同様であって,上告人は訴外谷と被上告人を共同不法行為者として,蒙った全損害の賠償を請求しうべきものである(訴外谷と被上告人との過失割合は共同不法行為者間の求償問題である。)。
同じ職場に働く者から受けた損害部分については,自からが加えた損害と同視して,もはや請求しえないとすることは,一般条理からしても納得出来ないものであって,同僚であるという事実は,加害者である被上告人と同様に訴外谷を損害賠償の相手方とすることを妨げる合理的な理由にはなり得ないものである。
また,上告人は勤務先からの指示により,訴外谷運転の勤務先所有の車両に同乗していたものであり,なんら非難さるべき事由はない。
かかる場合に,訴外谷の過失を上告人の過失として斟酌するならば,これは第三者(訴外谷)の過失によって生じた損害を上告人の負担に帰せしめ,反面,不当に加害者(被上告人)を利することとなり,却って過失相殺の理念である公平の理念に反することとなる。
以上より,訴外谷の過失を上告人の過失として斟酌した原判決には,民法第七二二条二項の解釈を誤った法令違背があり,また,最高裁判所昭和四〇年(オ)第一〇五六号慰藉料請求事件の昭和四二年六月二七日第三小法廷判決にも反する。
右法令違背が判決に影響を与えることは明白である。
第三点《略》
被害者側の過失 使用者責任(最判昭和56年11月27日民集35巻8号1271頁)
兄が弟に兄所有の自動車を運転させこれに同乗して自宅に帰る途中で発生した交通事故につき兄弟間に民法715条1項にいう使用者・被用者の関係が成立していたとされた事例
上告代理人小野寺信一の上告理由について
原審が適法に確定したところによれば,上告人は,本件事故の当日,出先から自宅に連絡し,弟の訴外甲をして上告人所有の本件自動車を運転して迎えに来させたうえ,更に,右訴外人をして右自動車の運転を継続させこれに同乗して自宅に戻る途中,本件事故が発生したものであるところ,右同乗後は運転経験の長い上告人が助手席に坐つて,運転免許の取得後半年位で運転経歴の浅い甲の運転に気を配り,事故発生の直前にも同人に対し「ゴー」と合図して発進の指示をした,というのである。
同事実関係のもとにおいては,上告人は,一時的にせよ甲を指揮監督して,その自動車により自己を自宅に送り届けさせるという仕事に従事させていたということができるから,上告人と甲との間に本件事故当時上告人の右の仕事につき民法七一五条一項にいう使用者・被用者の関係が成立していたと解するのが相当である。したがって,これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ,原判決に所論の違法はない。論旨は,採用することができない。
よつて,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官栗本一夫,裁判官木下忠良,同鹽野宜慶,同宮崎梧一
被害者側の過失(最判平成9年9月9日裁判集民事185号217頁)
過失相殺において運転者の過失が被害者側の過失と認められるために必要な身分上,生活関係上の一体性の有無(否定)
主 文
一 原判決中,主文第二項を次のとおり変更する。
上告人らの控訴に基づき,第一審判決を次のとおり変更する。
1 被上告人は,上告人らに対し,各一〇四〇万三〇三三円及びうち九七一万三〇三三円に対する平成二年五月二八日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 上告人らのその余の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟の総費用はこれを二分し,その一を上告人らの,その余を被上告人の負担とする。
理 由
上告代理人徳田靖之の上告理由第一点及び同第三点について
所論の点に関する原審の事実認定は,原判決挙示の証拠関係に照らして是認するに足り,原判決に所論の違法はない。論旨は,原審の専権に属する証拠の取捨判断,事実の認定を非難するものであって,採用することができない。
同第二点について
一 本件は,自動車同士の衝突事故により死亡した甲の両親である上告人らが,甲が乗車していた車両に衝突した相手方車両の運転者兼運行供用者である被上告人に対し,自動車損害賠償保障法三条に基づいて慰謝料,逸失利益等の損害賠償の支払を求めるものである。原審の適法に確定した事実関係の概要は,以下のとおりである。
1 乙勝は,平成二年五月二七日午後九時ころ,甲を助手席に同乗させ,普通乗用自動車(以下「乙車」という。)を運転し,東京都豊島区東池袋五丁目七番六号先路上において,甲の居住するマンションの前で同女を降車させるため,乙車を反対車線に入れるべく転回中,反対車線を時速約九〇㎞で進行してきた被上告人運転の普通乗用自動車と衝突した。
甲は,右事故により,乙車の助手席左側ドアに左けい部を挟まれ,同日午後一〇時四二分,けい髄損傷により死亡した。
2 甲の死亡により生じた損害は,慰謝料二〇〇〇万円,逸失利益三三五五万八七六七円,葬儀費用及び仏壇費用一五〇万円の合計五五〇五万八七六七円並びに弁護士費用上告人ら各自六九万円である。
3 本件事故の原因は,指定最高速度(五〇㎞毎時)をはるかに超える時速約九〇㎞で走行し,かつ,自車線上に進入しようとしていた乙車を前方に発見しながら,自車の通過を待ってくれるものと軽信して,直ちに減速するなどの適切な措置を執らなかった被上告人の過失と,交通量の多い危険な箇所で自車を転回させるに際し,反対車線上を走行してくる自動車の有無を注視しなかった乙の過失との競合によるもので,その過失割合は,被上告人六割,乙四割である。
4 甲と乙は,本件事故の約三年前から恋愛関係にあったものの,婚姻していたわけでも,同居していたわけでもなく,本件事故は,乙と甲が待ち合わせてデートをした後,乙が甲を同女宅に送り届ける途中に発生したものである。
5 上告人らは,自賠責保険から各一七八一万六三五〇円の支払を受けている。
二 原審は,乙と甲は未だ正式の夫婦ではないから,乙の過失を直ちに被害者側の過失ととらえて過失相殺をすることはできないが,本件事故は,乙と甲が待ち合わせてデートをした後,乙が甲を同女宅に送り届ける途中に発生したもので,乙の過失も重大であることなどの事情をかんがみれば,なお,衡平の見地から過失相殺に関する民法七二二条二項を類推適用し,損害額から一割を減ずる限度で乙の過失を斟酌するのが相当であるとして,損害合計額五五〇五万八七六七円を二分した二七五二万九三八三円(円未満切捨て。以下同じ)から一割を減じ,てん補額各一七八一万六三五〇円を差し引き,弁護士費用各六九万円を付加し,上告人らに対し支払うべき賠償額を各七六五万〇〇九四円とした。
三 しかし,原審の右判断は是認できない。その理由は,次のとおりである。
不法行為に基づく損害賠償額を定めるに当たり,被害者と身分上,生活関係上一体を成すとみることができない者の過失を被害者側の過失として斟酌することは許されないところ(最高裁昭和四〇年(オ)第一〇五六号同四二年六月二七日第三小法廷判決・民集二一巻六号一五〇七頁,最高裁昭和四七年(オ)第四五七号同五一年三月二五日第一小法廷判決・民集三〇巻二号一六〇頁参照),甲と乙は,本件事故の約三年前から恋愛関係にあったものの,婚姻していたわけても,同居していたわけてもないから,身分上,生活関係上一体を成す関係にあったということはできない。甲と乙との関係が右のようなものにすぎない以上,乙の過失の有無及びその程度は,上告人らに対し損害を賠償した被上告人が乙に対しその過失に応じた負担部分を求償する際に考慮されるべき事柄であるにすぎず,被上告人の支払うべき損害賠償額を定めるにつき,乙の過失を斟酌して損害額を減額することは許されないと解すべきである。
四 そうすると,乙の過失を斟酌し,甲の死亡により生じた損害額の全体を一割減額した金額を基に賠償額を定めた原審の判断には,民法七二二条二項の解釈適用を誤った違法があり,右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。これと同旨をいう論旨は理由がある。
そして,以上の説示に照らせば,被上告人が上告人らに支払うべき賠償額は,原審の確定した上告人ら各自の損害額二七五二万九三八三円に,弁護士費用各六九万円を加えた額から損害てん補額各一七八一万六三五〇円を控除した各一〇四〇万三〇三三円となるから,上告人らの請求は,各一〇四〇万三〇三三円及びうち九七一万三〇三三円に対する平成二年五月二八日から各支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,その余は棄却すべきものである。従って,原判決中,上告人らの敗訴部分は,この限度において破棄を免れず,これを主文第一項のとおり変更するのが相当である。
よって,原判決中,主文第二項を右のとおり変更し,民訴法四〇八条,三九六条,三八六条,三八四条,九六条,八九条,九二条,九三条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官千種秀夫,裁判官園部逸夫,同大野正男,同尾崎行信,同山口繁
被害者側の過失(最判平成19年4月24日裁判集民事224号261頁 )
内縁の夫の運転する自動車に同乗中に第三者運転車両との衝突事故により傷害を負った内縁妻が第三者に損害賠償請求する場合と内縁の夫の過失
上告代理人片岡剛の上告受理申立て理由について
1 本件は,内縁の夫の運転する自動車の助手席に同乗していた被上告人が,同車と上告人の運転する自動車とが衝突した事故により傷害を負い,後遺障害が残ったなどと主張して,運行供用者である上告人に対し,自賠法3条に基づき損害賠償を請求したところ,上告人が,過失相殺の抗弁として,被上告人の内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮すべきである旨を主張して,その損害賠償額を争っている事案である。
2 原審が確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)平成13年8月6日午後0時10分ころ,被上告人の内縁の夫である甲が被上告人を助手席に同乗させて運転する自動車が,X市Z先の交通整理の行われていない交差点に進入したところ,交差する道路を左側から走行してきて同交差点に進入した上告人運転の自動車と衝突するという事故が発生した(以下,この事故を「本件事故」という。)。
(2)被上告人は,本件事故により,頸椎捻挫,腰椎捻挫の傷害を負い,また,パニック障害,うつ症状等の後遺障害が残った。
(3)上告人は,運行供用者として,自賠法3条に基づき,被上告人に対して被上告人が本件事故により被った損害を賠償する責任を有する。
3 原審は,被上告人において甲が飲酒運転や無謀運転をすることを知りながら同乗したなどの事情が認められない本件においては,上告人が被上告人に対して支払うべき損害賠償額を定めるに当たり,甲の過失を被害者側の過失として考慮することはできず,上告人の過失相殺の抗弁はそれ自体として理由がないと判断して,194万8976円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で被上告人の請求を認容した。
4 しかし,原審の上記判断は是認できない。その理由は,次のとおりである。
不法行為に基づき被害者に対して支払われるべき損害賠償額を定めるに当たっては,被害者と身分上,生活関係上一体を成すとみられるような関係にある者の過失についても,民法722条2項の規定により,いわゆる被害者側の過失としてこれを考慮することができる(最高裁昭和40年(オ)第1056号同42年6月27日第三小法廷判決・民集21巻6号1507頁,最高裁昭和47年(オ)第457号同51年3月25日第一小法廷判決・民集30巻2号160頁参照)。内縁の夫婦は,婚姻の届出はしていないが,男女が相協力して夫婦としての共同生活を営んでいるものであり,身分上,生活関係上一体を成す関係にあるとみることができる。そうすると,内縁の夫が内縁の妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが衝突し,それにより傷害を負った内縁の妻が第三者に対して損害賠償を請求する場合において,その損害賠償額を定めるに当たっては,内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することができると解するのが相当である。
本件において,被上告人は,内縁の夫である甲の運転する自動車に同乗していたところ,同車と上告人運転の自動車とが衝突した本件事故により傷害を負ったというのであるから,上告人が被上告人に対して支払うべき損害賠償額を定めるに当たっては,甲の過失を被害者側の過失として考慮することができるというべきである。
5 以上によれば,上告人が被上告人に対して支払うべき損害賠償額を定めるに当たり,甲の過失を被害者側の過失として考慮することができないとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決のうち上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして,甲の過失の有無,過失割合について更に審理を尽くさせるため,上記部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官上田豊三,裁判官藤田宙靖,同堀籠幸男,同那須弘平,同田原睦夫
被害者側の過失-共同暴走行為(最判平成20年7月4日裁判集民事228号399頁)
甲が運転し乙が同乗する自動二輪車とパトカーとが衝突し乙が死亡した交通事故につき,乙の相続人がパトカーの運行供用者に対し損害賠償を請求する場合において,過失相殺をするに当たり,甲の過失を乙の過失として考慮することができるとされた事例
上告代理人田野壽,同宮崎隆博の上告受理申立て理由第3の3について
1 本件は,甲(当時22歳)運転の自動二輪車とパトカーとが衝突し,自動二輪車に同乗していた乙(当時19歳)が死亡した交通事故につき,乙の相続人である被上告人らが,パトカーの運行供用者である上告人に対し,自賠法(以下「自賠法」という。)3条に基づく損害賠償を請求する事案である。
2 原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 甲及び乙は,中学校時代の先輩と後輩の関係であり,平成13年8月13日午後9時ころから,友人ら約20名と共に,自動二輪車3台,乗用車数台に分乗して,集合,離散しながら,空吹かし,蛇行運転,低速走行等の暴走行為を繰り返した。乙は,ヘルメットを着用せずに,消音器を改造した自動二輪車(以下「本件自動二輪車」という。)に甲と二人乗りし,交代で運転をしながら走行していた。
(2) 岡山県警察勝山警察署の丙らは,付近の住民から暴走族が爆音を立てて暴走している旨の通報を受け,同日午後11時20分ころ,これを取り締まるために丙が運転するパトカー(以下「本件パトカー」という。)及び他の警察官が運転する小型パトカー(以下「本件小型パトカー」という。)の2台で出動した。上告人は,本件パトカーの運行供用者である。
(3) 丙は,国道313号線(以下「本件国道」という。)を走行中,同日午後11時35分ころ,本件自動二輪車が対向車線を走行してくるのを発見し追跡したが,本件自動二輪車が転回して逃走したためこれを見失い,いったん本件国道に面した商業施設の駐車場(以下「本件駐車場」という。)に入って本件パトカーを停車させた。また,本件小型パトカーも本件駐車場に入って停車していた。本件駐車場先の本件国道は片側1車線で,制限速度は時速40kmであった。
(4) 同日午後11時49分ころ,甲が運転し乙が同乗した本件自動二輪車が本件国道を時速約40kmで走行してきたため,丙は,これを停止させる目的で,本件パトカーを本件国道上に中央線をまたぐ形で斜めに進出させ,本件自動二輪車が走行してくる車線を完全にふさいだ状態で停車させた。
付近の道路は暗く,本件パトカーは前照灯及び尾灯をつけていたが,本件自動二輪車に遠くから発見されないように,赤色の警光灯はつけず,サイレンも鳴らしていなかった。
(5) 甲は,本件駐車場内に本件小型パトカーが停車しているのに気付き,時速約70~80kmに加速して本件駐車場前を通過し逃走しようとしたが,その際,友人が捕まっているのではないかと思い,本件小型パトカーの様子をうかがおうとしてわき見をしたため,前方に停車した本件パトカーを発見するのが遅れ,回避する間もなく,その側面に衝突した(以下「本件事故」という。)。
(6) 乙は,本件事故により頭がい骨骨折等の傷害を負い,同月14日午前1時13分ころ死亡した。
(7) 本件事故により乙が受けた損害の額は合計6600万5364円であり,乙の両親である被上告人らは,乙の有する損害賠償請求権を各2分の1の割合で相続した。被上告人らの固有の損害の額は各100万円である。
また,被上告人らは,損害の一部てん補として,56万5000円の支払を受けた。
3 原審は,次のとおり判断して,被上告人らの上告人に対する請求を,各2961万9645円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容すべきものとした。
(1) 丙が本件自動二輪車を停止させるために執った措置は,赤色の警光灯をつけず,サイレンも鳴らさずに片側1車線を完全にふさいで本件パトカーを停車させるという交通事故発生の危険が高いものであり,相当と認められる限度を超えるもので,自賠法3条ただし書所定の免責事由は存しないし,正当業務行為として違法性が阻却されるものでもない。従って,上告人は,同条本文に基づき,被上告人らに対し損害賠償責任を負う。
(2) 甲には前方注視義務違反及び制限速度違反が,乙にはヘルメット着用義務違反及び甲と共に暴走行為をしてパトカーに追跡される原因を作ったという事情があることを考慮すれば,甲,乙,丙の過失割合は6対2対2である。
本件事故は,乙との関係では,甲と丙との共同不法行為により発生したものである。そして,甲と乙との間に身分上,生活関係上の一体性はないから,過失相殺をするに当たって甲の過失をいわゆる被害者側の過失として考慮することはできない。
従って,上告人は,被上告人らに対して,甲と連帯して損害の8割を賠償する責任を負う。損害の一部てん補額を控除し,弁護士費用を加算すると,被上告人らの上告人に対する損害賠償の請求は,各2961万9645円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
4 しかし,原審の上記3(2)の判断は是認できない。その理由は,次のとおりである。
前記事実関係によれば,甲と乙は,本件事故当日の午後9時ころから本件自動二輪車を交代で運転しながら共同して暴走行為を繰り返し,午後11時35分ころ,本件国道上で取締りに向かった本件パトカーから追跡され,いったんこれを逃れた後,午後11時49分ころ,甲が本件自動二輪車を運転して本件国道を走行中,本件駐車場内の本件小型パトカーを見付け,再度これから逃れるために制限速度を大きく超過して走行するとともに,一緒に暴走行為をしていた友人が捕まっていないか本件小型パトカーの様子をうかがおうとしてわき見をしたため,本件自動二輪車を停止させるために停車していた本件パトカーの発見が遅れ,本件事故が発生したというのである(以下,本件小型パトカーを見付けてからの甲の運転行為を「本件運転行為」という。)。
以上のような本件運転行為に至る経過や本件運転行為の態様からすれば,本件運転行為は,乙と甲が共同して行っていた暴走行為から独立した甲の単独行為とみることはできず,上記共同暴走行為の一環を成すものというべきである。
従って,上告人との関係で民法722条2項の過失相殺をするに当たっては,公平の見地に照らし,本件運転行為における甲の過失も乙の過失として考慮することができると解すべきである。
これと異なり,甲の過失は乙の過失として考慮することができないとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして,以上の見解の下に乙と丙との過失割合等につき更に審理を尽くさせるため,上記部分及び上告人の民訴法260条2項の裁判を求める申立てにつき,本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官古田佑紀,裁判官津野修,同今井功,同中川了滋
素因減額(最判昭和63年4月21日民集42巻4号243頁)
身体に対する加害行為によって生じた損害について被害者の心因的要因が寄与しているときと民法722条2項の類推適用
上告代理人永瀬精一の上告理由について
論旨は,原判決が,事故と損害との因果関係についていわゆる割合的認定の理論を採用し,過失相殺の規定の類推適用をして,被上告人らに賠償責任を負担させるのが相当であるのは事故後三年を経過した昭和四七年三月二〇日までに発生した損害のうちその四割の限度であるとし,その余は負担させるべきでないと判断したのは,法令の解釈適用を誤ったもので,原判決には判決に影響のある法令違反,理由不備の違法があるというのである。
思うに,身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において,その損害がその加害行為のみによって通常発生する程度,範囲を超えるものであって,かつ,その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは,損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし,裁判所は,損害賠償の額を定めるに当たり,民法七二二条二項の過失相殺の規定を類推適用して,その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができるものと解するのが相当である。
これを本件についてみるに,原判決が適法に確定した事実関係は,次のとおりである。
1 昭和四四年三月二〇日午後六時四〇分静岡県浜松市甲町乙番地先路上で本件事故が発生した。被上告人甲は,加害車を,時速四〇㎞ないし五〇㎞の速度で,上告人(当時五二歳)が同乗し,その夫である乙が運転している被害車の一五mないし一八m後方を追従して進行中,被害車が突然急停車したので,急ブレーキをかけて停止しようとしたが間に合わず,被害車の後部に自車の前部を接触させた。接触の際,乙はブレーキを踏んでいなかったため,被害車は若干前に押し出された。しかし,その衝撃の程度は軽度であったが,接触の衝撃は,人体に感じうるものであった。被上告人甲は,直ちに下車して上告人及び乙(以下「上告人ら」という。)に負傷及び車体の損傷の有無を尋ね,車体を点検したところ,目立った損傷も見つからず,また上告人らから何ら異常がない旨の回答を得た。しかし,念のため医師の診察を受けるよう,また,事故の申告のため警察に同行してもらいたい旨申し入れたが,上告人らは,帰りを急いでいるからと述べて被上告人甲の氏名と住所を聞いただけで帰宅した。その後の点検によって,本件事故により,加害車には接触のため若干の凹損を生じ,被害車には肉眼では識別できないが手指の感触によって他の部分との違いがわかる程度の僅かな凹損等が生じたことが判明した。
2 本件事故後の上告人の症状は次のとおりであった。すなわち,上告人は,同月二二日東病院に赴き,同病院の丙医師に対し,当初は何の異常もなかったが,暫くして気分が悪くなり,頭,頸に痛みがあり吐き気がする等と訴えて同医師の診察を受けたところ,外傷性頭頸部症候群として約五〇日の安静加療を必要とするとの診断で入院を勧められたため,即日入院し,牽引,消炎剤,止血剤の投与等の治療を受けた。同年五月二九日ころから軽いマッサージの治療が始まったが,同年八月ころから頑固な頭痛,頸部強直,流涙等の症状が続き,昭和四五年ころには頸部強直,左半身のしびれ,頭痛,嘔気,流涙等の症状が固定し,用便等のほかはほとんど離床せず,昭和四六年一二月一五日ころまで注射,湿布及び赤外線・超短波・マッサージ等の物理療法による治療が継続された。上告人は,同日ころ東病院を退院し,その後は自宅で療養を継続したが,時々丙医師の往診を受けた。昭和四九年一〇月当時頭痛,頸部痛,肩部痛,左上下肢がきかない,左上下肢のしびれ感,左足背部感覚障害,吐き気,左耳鳴,腰痛,体重減少の症状がある旨の訴えがあり,食事は自分で箸を持ってしていたが,外出時には頸部をコルセツトで固定していた。その後,昭和五二年七月五日板橋中央総合病院において頭部外傷後遺症,頸部変形症と診断され,同日から昭和五四年一月三〇日まで同病院に入院し,頭痛,頭重感,めまい,肩部痛,背部痛,嘔気,手足のしびれ感等の症状がある旨訴え,点滴静脈注射,マッサージ等の理学的療法等の治療を受け,同日同病院を退院し,即日高橋脳神経外科・外科医院に入院し,頸椎症候群,大後頭神経痛の診断を受け,同日以降は頭痛,項部痛,両肩疼痛,眠気,嘔吐,嘔気,両手のしびれ感等の症状がある旨訴え,点滴静脈注射,鎮痛剤投与,マッサージ等の理学的療法等の治療が継続された。同年七月三一日同病院を退院し,その後同医院に通院治療を受けた。最近では寝ていることは少なくなり,頭痛,項部痛の頻度が減少し,嘔吐,嘔気は消失し,日常生活は徐々に活発化してきている。
3 東病院において当初丙医師の行った安静加療約五〇日を要する旨の診断は,客観的な検査結果及びその後の所見から判断して,医師の常識を超えた診断であり,安静加療二週間ないし三週間と診断するのが相当であったと考えられるが,丙医師が右診断をした原因としては,上告人の誇張した愁訴があったことが窺われ,同病院で初診時に撮影したレントゲン写真によると,上告人の第四・第五頸椎間に軽度の角状形成と第四頸椎の約二mmの前方へのすべり及び第五頸椎体前上縁の幼若な骨棘形成像が認められるが,これは老人性変性現象によるもので,他に他覚的所見として明らかなものは,頸椎運動の制限のみであり,上告人の症状には心理的な要因が多分に影響していること,同病院の治療も上告人の愁訴を鵜のみにして行っていたこと,上告人には回復への自発的意欲を欠いていたことが窺われ,本訴における鑑定のため実施された上告人に対する諸検査の結果によると,上告人は,頸部が全く硬直して動かず,他動的に動かそうとすると強く抵抗を示すが,これはレントゲン写真上,頸部が全く硬直して動かないことはありえないということと矛盾し,上告人の意思が介在しているか,少なくとも上告人の自発性の欠如が原因と考えられる等,上告人の性格は,自己暗示にかかりやすく,自己中心的で,神経症的傾向が極めて強く,昭和五五年五月一二日当時頸椎は変形著明で骨粗しよう症を呈しているが,これは長期にわたる頸部のコルセツトによる固定の後遺症と考えられる。
4 また,上告人は,昭和四三年三月二三日,国鉄小岩駅で電車に乗る際乗客に押されて左肋骨亀裂骨折の傷害を受け,同年四月五日から同年六月四日まで栗原医院に入院し,退院後も昭和四四年三月一五日まで通院を続け,同年二月一一日にも駅の階段から転落して左胸部及び左下腿打撲傷を負ったが,本件事故当時は,右各負傷は一応治癒していた。上告人は,右小岩駅での事故について国鉄を相手方として損害賠償請求の訴えを提起し,和解により賠償金を受領したことがある。
5 被上告人甲は,事故後車体を点検したが目立った損傷も見つからず,また念のため医師の診察を受けるよう申し入れたにもかかわらず,上告人らから何の異常もない旨の回答を得ていたので,上告人の受傷について疑惑を持ち,また本件事故の一か月後になって一〇〇万円の損害賠償を要求してきた上告人らの態度に不信感を持ったため,上告人を見舞うこともなく,また自動車損害賠償責任保険による弁済のほか治療費の支払いもしていない。
6 外傷性頭頸部症候群とは,追突等によるむち打ち機転によって頭頸部に損傷を受けた患者が示す症状の総称であり,その症状は,身体的原因によって起こるばかりでなく,外傷を受けたという体験によりさまざまな精神症状を示し,患者の性格,家庭的,社会的,経済的条件,医師の言動等によっても影響を受け,ことに交通事故や労働災害事故等に遭遇した場合に,その事故の責任が他人にあり損害賠償の請求をする権利があるときには,加害者に対する不満等が原因となって症状をますます複雑にし,治癒を遷延させる例も多く,衝撃の程度が軽度で損傷が頸部軟部組織(筋肉,靱帯,自律神経など)にとどまっている場合には,入院安静を要するとしても長期間にわたる必要はなく,その後は多少の自覚症状があっても日常生活に復帰させたうえ適切な治療を施せば,ほとんど一か月以内,長くとも二,三か月以内に通常の生活に戻ることができるのが一般である。
以上,原審の確定した事実関係のもとにおいては,上告人は本件事故により頭頸部軟部組織に損傷を生じ外傷性頭頸部症候群の症状を発するに至ったが,これにとどまらず,上告人の特異な性格,初診医の安静加療約五〇日という常識はずれの診断に対する過剰な反応,本件事故前の受傷及び損害賠償請求の経験,加害者の態度に対する不満等の心理的な要因によって外傷性神経症を引き起こし,更に長期の療養生活によりその症状が固定化したものと認めるのが相当であり,この上告人の症状のうち頭頸部軟部組織の受傷による外傷性頭頸部症候群の症状が被上告人甲の惹起した本件事故と因果関係があることは当然であるが,その後の神経症に基づく症状についても右受傷を契機として発現したもので,その症状の態様からみて,東病院退院後自宅療養を開始したのち約三か月を経過した日,すなわち事故後三年を経過した昭和四七年三月二〇日までに,右各症状に起因して生じた損害については,本件事故との間に相当因果関係があるものというべきであるが,その後生じた分については,本件事故との間に相当因果関係があるものとはいえない。また,右事実関係のもとにおいては,上告人の訴えている右症状のうちには上告人の特異な性格に起因する症状も多く,初診医の診断についても上告人の言動に誘発された一面があり,更に上告人の回復への自発的意欲の欠如等があいまって,適切さを欠く治療を継続させた結果,症状の悪化とその固定化を招いたと考えられ,このような事情のもとでは,本件事故による受傷及びそれに起因して三年間にわたって上告人に生じた損害を全部被上告人らに負担させることは公平の理念に照らし相当ではない。すなわち,右損害は本件事故のみによって通常発生する程度,範囲を超えているものということができ,かつ,その損害の拡大について上告人の心因的要因が寄与していることが明らかであるから,本件の損害賠償の額を定めるに当たっては,民法七二二条二項の過失相殺の規定を類推適用して,その損害の拡大に寄与した上告人の右事情を斟酌することができるものというべきである。そして,前記事実関係のもとでは,事故後昭和四七年三月二〇日までに発生した損害のうちその四割の限度に減額して被上告人らに負担させるのが相当であるとした原審の判断は,結局正当として是認できる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官高島益郎,裁判官大内恒夫,同佐藤哲郎,同四ツ谷巖
事故前からの被害者疾患(最判平成4年6月25日民集46巻4号400頁)
損害賠償額の算定に当たって加害行為前から存在した被害者の疾患をしんしゃくすることの可否
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人後藤徳司,同日浅伸廣の上告理由第一点について
一 被害者に対する加害行為と被害者のり患していた疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において,当該疾患の態様,程度などに照らし,加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは,裁判所は,損害賠償の額を定めるに当たり,民法七二二条二項の過失相殺の規定を類推適用して,被害者の当該疾患を斟酌できると解するのが相当である。けだし,このような場合においてもなお,被害者に生じた損害の全部を加害者に賠償させるのは,損害の公平な分担を図る損害賠償法の理念に反するものといわなければならないからである。
二 これを本件についてみるに,原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
1 本件事故は,昭和五二年一一月二五日午前四時五八分ころ,東京都杉並区甲丁目乙番先の首都高速道路四号線下り車線上で発生した。すなわち,被上告人甲は,加害車両を運転し,下り車線の左側第一車線を新宿方面から高井戸方面に向かって走行中,進路前方の非常待避所から第一車線に進出しようとする車両があり,これに対応して先行車両が急ブレーキをかけたため,第二車線に進路を変更した。被上告人甲は,第二車線の被害車両(乙の運転する個人タクシー)が前方を走行しているものと思っていたが,実は被害車両が停止し,第二車線をふさいでいることを前方約一四メートルに迫って発見した。そこで,あわててハンドルを左に切り戻し,被害車両と第一車線の先行車両との間を通り抜けようとしたが,その際,加害車両の右側面を被害車両の左後部に衝突させた。
2 乙は,本件事故前の昭和五二年一〇月二五日早朝,タクシー内でエンジンをかけたまま仮眠中,一酸化炭素中毒にかかり,意識もうろう状態で内野病院に入院し,翌日意識が戻り,一一月七日に退院して直ちにタクシーの運転業務に従事したが,右一酸化炭素中毒の程度は必ずしも軽微なものではなかった。
3 乙は,本件事故によって頭部打撲傷を負い,その後次のとおりの経過をたどって死亡するに至った。
(一) 乙は,本件事故直後,意識が比較的はっきりしており,被上告人甲や臨場した警察官の質問に対して不十分ながらも対応していた。動作には精神症状に問題のあることをうかがわせるような不自然な点がみられたが,これといった外傷もなく,乙から頭部の痛み等の訴えもなかった。しかし,乙は,ほどなく記憶喪失に陥り,一人で自宅に戻れなくなったため,長男が引取りに出向いた。
(二) 乙は,その後,自宅療養を続けていたところ,煙草を二本同時に吸おうとするなど奇異な振舞いを示すこともあって,同月三〇日,中村外科病院に入院し,頭部外傷,外傷性項部痛症と診断されたが,精神症状の存在を理由に精神病院への転院を指示された。
(三) 乙は,一二月七日,国立国府台病院精神科で診察を受け,痴呆様行動,理解力欠如,失見当識,記銘力障害,言語さてつ症等の多様な精神障害が生じていると診断され,同月一六日,右病院に入院し,以後,同病院で治療を受けたが,症状が改善しないまま,昭和五五年一二月二九日,呼吸麻痺を直接の原因として死亡した。
4 乙の前記精神障害は,頭部打撲傷等の頭部外傷及び一酸化炭素中毒のそれぞれの症状に共通しているところ,昭和五四年六月ころの丙Tスキャナーによる脳室の撮影では,乙の脳室全体の拡大(脳の萎縮)がみられ,これは頭部外傷を理由とするだけでは説明が困難である。乙は,本件事故により頭部,頸部及び脳に対し相当に強い衝撃を受け,これが一酸化炭素中毒による脳内の損傷に悪影響を負荷し,本件事故による頭部打撲傷と一酸化炭素中毒とが併存競合することによって,一たんは潜在化ないし消失していた一酸化炭素中毒における各種の精神的症状が本件事故による頭部打撲傷を引金に顕在発現して長期にわたり持続し,次第に増悪し,ついに死亡したと推認するのが相当である。
三 原審の右認定は,原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り,これによれば,本件事故後,乙が前記精神障害を呈して死亡するに至ったのは,本件事故による頭部打撲傷のほか,本件事故前にり患した一酸化炭素中毒もその原因となっていたことが明らかである。そして,原審は,前記事実関係の下において,乙に生じた損害につき,右一酸化炭素中毒の態様,程度その他の諸般の事情を斟酌し,損害の五〇パーセントを減額するのが相当であるとしているのであって,その判断は,前示したところに照らし,正当として是認できる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用できない。
同第二点について
所論の点に関する原審の認定判断は,原判決挙示の証拠関係に照らし,正当として是認することができ,原判決に所論の違法はない。論旨は,原審の裁量に属する過失割合の判断の不当をいうものにすぎず,採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条,九三条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官味村治,裁判官大堀誠一,同橋元四郎平,同小野幹雄,同三好達
被害者の身体的特徴を斟酌することの可否(最判平成8年10月29日民集50巻9号2474頁)
一 損害賠償の額を定めるに当たり被害者の身体的特徴を斟酌することの可否
二 首が長いという被害者の身体的特徴をしんしゃくする事はできないとされた事例
主 文
原判決中、上告人敗訴の部分を破棄する。
前項の部分につき、本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人西野泰夫、同斉藤洋、同後藤潤一郎、同新海聡の上告理由について
一 原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
1 被上告人甲は,昭和六二年二月二七日,宮崎県東臼杵郡甲町内の道路上において,被上告人株式会社エフピコが所有する普通乗用自動車を運転して走行中,上告人の運転する自家用乗用自動車に自車を追突させた。上告人は,本件事故により,運転席のシートに頭部を強く打ちつけ,その直後から首筋にしびれや痛みを感じ,翌日,整形外科医院において受診したが,その時点で,頸部痛等の症状があり,頸椎捻挫と診断された。上告人は,同年三月四日から同年一二月一六日まで,右医院に入院し治療を受けたが,頸部・後頭部疼痛等の症状があり,右退院後も通院治療を継続している。上告人は,右入院中に視力の低下を訴えて,同年四月二三日,眼科医院において受診したところ,矯正視力の低下等の症状が見られ,これら眼症状は,頭頸部外傷症候群によるものと診断された。
2 上告人は,平均的体格に比して首が長く多少の頸椎の不安定症があるという身体的特徴を有していたところ,この身体的特徴に本件事故による損傷が加わって,左胸郭出口症候群の疾患やバレリュー症候群を生じた。バレリュー症候群については,少なくとも同身体的特徴が同疾患に起因する症状を悪化ないし拡大させた。また,頭頸部外傷症候群による前記眼症状についても,上告人の右身体的特徴がその症状の拡大に寄与している。
3 右事実関係における上告人の症状に加え,バレリュー症候群にあっては,その症状の多くは他覚的所見に乏しく,自覚的愁訴が主となっており,実際においては神経症が重畳していることが多いので,更にその治療が困難とされていること,そのためもあって,初期治療に当たり,不要に重症感を与えたり後遺症の危険を過大に示唆したりしないことが肝要であるとされていることが認められ,これを上告人の前記症状等に照らすとき,上告人の右各症状の悪化ないし拡大につき,少なからず心因的要素が存するということができる。
二 本件は,上告人が本件事故により被った損害の賠償を請求するものであるが,原審は,右事実関係を前提として,本件において上告人の首が長いこと等の事情に鑑みると,民法七二二条二項の過失相殺の規定を類推適用して上告人の首が長いという素因及び前記心因的要素を斟酌し,本件事故による上告人の損害のうち四割を減額するのが相当であると判断した。
三 しかし,原審の右判断はすぐには是認できない。その理由は,次のとおりである。
被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合において,当該疾患の態様,程度などに照らし,加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは,裁判所は,損害賠償の額を定めるに当たり,民法七二二条二項の規定を類推適用して,被害者の疾患を斟酌することができることは,当裁判所の判例(最高裁昭和六三年(オ)第一〇九四号平成四年六月二五日判決・民集四六巻四号四〇〇頁)とするところである。しかし,被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても,それが疾患に当たらない場合には,特段の事情がない限り,被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできないと解すべきである。何故なら,人の体格ないし体質は,すべての人が均一同質なものということはできず,極端な肥満など通常人の平均値から著しくかけ離れた身体的特徴を有する者が,転倒などにより重大な傷害を被りかねないことから日常生活において通常人に比べてより慎重な行動をとることが求められるような場合は格別,その程度に至らない身体的特徴は,個々人の個体差の範囲として当然にその存在が予定されているものというべきだからである。
これを本件についてみるに,上告人の身体的特徴は首が長くこれに伴う多少の頸椎不安定症があるということであり,これが疾患に当たらないことはもちろん,このような身体的特徴を有する者が一般的に負傷しやすいものとして慎重な行動を要請されているといった事情は認められないから,前記特段の事情が存するということはできず,右身体的特徴と本件事故による加害行為とが競合して上告人の右傷害が発生し,又は右身体的特徴が被害者の損害の拡大に寄与していたとしても,これを損害賠償の額を定めるに当たり斟酌するのは相当でない。
そうすると,損害賠償の額を定めるに当たり上告人の心因的要素を斟酌すべきか否かはさておき,前示と異なる原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法があり,その違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由があり,原判決は上告人敗訴部分につき破棄を免れない。そして,本件については,損害額全般について更に審理を尽くさせる必要があるから,右破棄部分につきこれを原審に差し戻すのが相当である。
よって,民訴法四〇七条一項に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官千種秀夫,裁判官園部逸夫,同可部恒雄,同大野正男,同尾崎行信
損益相殺(最判平成5年3月24日民集47巻4号3039頁)
1 不法行為と同一原因で被害者らが第三者に対して取得した債権額を賠償額から控除することの要否と範囲
2 地方公務員等共済組合法(昭和60年法律第108号の改正前)に基づく退職年金受給者が不法行為で死亡した場合に相続人が同死亡を原因として受給権を得た同法上の遺族年金の額を賠償額から控除することの要否と範囲
主 文
1 原判決を次のとおり変更する。
1 上告人は,被上告人に対し,178万9794円及びこれに対する昭和61年1月14日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被上告人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟の総費用はこれを5分し,その1を上告人の,その余を被上告人の負担とする。
理 由
上告代理人芝康司,同山本寅之助,同森本輝男,同藤井勲,同山本彼1郎,同泉薫,同矢倉昌子,同阿部清司の上告理由について
所論は,要するに,被上告人の請求は,上告人に対し,本件事故によって死亡した甲の相続人(妻)である被上告人が,地方公務員等共済組合法(昭和60年法律第108号による改正前のもの。以下「法」という。)の規定する退職年金を受給していた甲が生存していればその平均余命期間に受給することができた退職年金の現在額などを同人の損害として,その賠償を求めるものであるところ,被上告人は,甲の死亡を原因として,法の規定する遺族年金の受給権を取得したのであるから,甲の平均余命年数を基準に遺族年金の現在額を算定し,これを被上告人が上告人に対して賠償を求める損害額から控除すべきであると解するのが最高裁の判例(最高裁昭和48年(オ)第813号同50年10月21日第3小法廷判決裁判集民事116号307頁)であるのに,これと異なり,被上告人が原審の口頭弁論終結時までに現実に支給を受けた遺族年金の額に限って損害額から控除すれば足りるとした原判決には,法令の解釈適用を誤った違法がある,というのである。
1 不法行為に基づく損害賠償制度は,被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し,加害者にこれを賠償させることにより,被害者が被った不利益を補てんして,不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものである。
2 被害者が不法行為によって損害を被ると同時に,同一の原因によって利益を受ける場合には,損害と利益との間に同質性がある限り,公平の見地から,その利益の額を被害者が加害者に対して賠償を求める損害額から控除することによって損益相殺的な調整を図る必要があり,また,被害者が不法行為によって死亡し,その損害賠償請求権を取得した相続人が不法行為と同1の原因によって利益を受ける場合にも,右の損益相殺的な調整を図ることが必要なときがあり得る。このような調整は,前記の不法行為に基づく損害賠償制度の目的から考えると,被害者又はその相続人の受ける利益によって被害者に生じた損害が現実に補てんされたということができる範囲に限られるべきである。
3 ところで,不法行為と同一の原因によって被害者又はその相続人が第三者に対する債権を取得した場合には,当該債権を取得したということだけから右の損益相殺的な調整をすることは,原則として許されないものといわなければならない。何故なら,債権には,程度の差こそあれ,履行の不確実性を伴うことが避けられず,現実に履行されることが常に確実であるということはできない上,特に当該債権が将来にわたって継続的に履行されることを内容とするもので,その存続自体についても不確実性を伴うものであるような場合には,当該債権を取得したということだけでは,これによって被害者に生じた損害が現実に補てんされたものということができないからである。
4 従って,被害者又はその相続人が取得した債権につき,損益相殺的な調整を図ることが許されるのは,当該債権が現実に履行された場合又はこれと同視し得る程度にその存続及び履行が確実であるということができる場合に限られるものというべきである。
2(1) 法の規定する退職年金及び遺族年金は,本人及びその退職又は死亡の当時その者が直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とする地方公務員法所定の退職年金に関する制度に基づく給付であって,その目的及び機能において,両者が同質性を有することは明らかである。そして,給付義務を負う者が共済組合であることに照らせば,遺族年金については,その履行の不確実性を問題とすべき余地がないということができる。しかし,法の規定によれば,退職年金の受給者の相続人が遺族年金の受給権を取得した場合においても,その者の婚姻あるいは死亡などによって遺族年金の受給権の喪失が予定されているのであるから(法96条),既に支給を受けることが確定した遺族年金については,現実に履行された場合と同視し得る程度にその存続が確実であるということができるけれども,支給を受けることが未だ確定していない遺族年金については,右の程度にその存続が確実であるということはできない。
(2) 退職年金を受給していた者が不法行為によって死亡した場合には,相続人は,加害者に対し,退職年金の受給者が生存していればその平均余命期間に受給することができた退職年金の現在額を同人の損害として,その賠償を求めることができる。この場合において,右の相続人のうちに,退職年金の受給者の死亡を原因として,遺族年金の受給権を取得した者があるときは,遺族年金の支給を受けるべき者につき,支給を受けることが確定した遺族年金の額の限度で,その者が加害者に対して賠償を求め得る損害額からこれを控除すべきものであるが,未だ支給を受けることが確定していない遺族年金の額についてまで損害額から控除することを要しないと解するのが相当である。
(3) 以上説示するところに従い,所論引用の当裁判所第3小法廷昭和50年10月21日判決及び最高裁昭和52年(オ)第429号同年12月22日第1小法廷判決裁判集民事122号559頁その他上記見解と異なる当裁判所の判例は,いずれも変更すべきものである。
3(1) これを本件についてみるのに,原審の適法に確定した事実関係によれば,(1) 甲は,本件事故前,退職年金を受給していた,(2) 甲が本件事故によって死亡しなければその平均余命期間に受給することができた退職年金の現在額(被上告人の相続分)は,1035万5671円である,(3) 被上告人は,甲が本件事故によって死亡したため,遺族年金の受給権を取得し,原審の口頭弁論終結時までに合計321万1151円の支給を受けた,というのである。
(2) 原審は,右事実関係の下において,被上告人が現実に支給を受けた遺族年金の額に限って,これを損害の額から控除すべきものとし,甲の得べかりし退職年金の現在額その他の損害額に過失相殺による減額を加えた額から遺族年金の既払分321万1151円及び自賠法に基づく保険金を控除した残額に弁護士費用を加え,結局,216万2144円が上告人の被上告人に対する損害賠償額であると判断した。
(3) しかし,法75条1項,4項によれば,年金である給付は,その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなった日の属する月までの分を支給し,毎年3月,6月,9月及び12月(なお,昭和60年法律第108号により,毎年2月,5月,8月及び11月と改正され,改正前の遺族年金にも適用されることになった。)において,それぞれの前月までの分を支給するものとされており,被上告人について遺族年金の受給権の喪失事由が発生した旨の主張のない本件においては,原審口頭弁論終結の日である昭和63年7月8日現在で被上告人が同年7月分までの遺族年金の支給を受けることが確定していたものである。
ところで,被上告人が原審最終口頭弁論期日までに支給を受けた最終の分は昭和63年5月(原判決の事実摘示欄に同年6月とあるのは誤記と認める。)に支払われた37万2350円であることは,原判決の記載から認められるところ,右金員は,前記の法75条4項の規定によれば,同年2月から4月までの遺族年金であるとみるべきであるから,被上告人の当時の遺族年金の3か月分の金額は37万2350円であることが明らかである。
4 従って,本件において,前記の損害額から控除すべき遺族年金の額は,被上告人が既に支給を受けた321万1151円と原審の口頭弁論終結時において支給を受けることが確定していた同年5月から7月までの3か月分37万2350円との合計額であるというべきである。
5 そうすると,彼上告人に関する損害賠償として上告人に対し支払を命ずべき額は,原審の認容額216万2144円から右の37万2350円を控除した178万9794円ということになるので,これと結論を一部異にする原審の前記判断には,損害賠償額の算定に関する法令の解釈適用を誤った違法があるといわなければならない。論旨は,その限度で理由があり,原判決は,右の37万2350円を控除しなかった限度で破棄を免れず,同部分につき,被上告人の請求は棄却すべきものである。
よって,原判決を主文第1項のとおり変更することとし,民訴法408条,396条,386条,384条,96条,89条,92条に従い,裁判官藤島昭,同園部逸夫,同佐藤庄市郎,同木崎良平,同味村治の反対意見(略)があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官草場良八,裁判官藤島昭,同坂上壽夫,同貞家克己,同大堀誠一,同園部逸夫,同橋元四郎平,同中島敏次郎,同佐藤庄市郎,同可部恒雄,同木崎良平,同味村治,同大西勝也,同小野幹雄,同三好達
生命保険金の控除の要否(最判昭和39年9月25日民集18巻7号1528頁)
不法行為による死亡に基づく損害賠償額から生命保険金を控除することの適否
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人高岡次郎の上告理由第一点について。
不法行為における過失相殺については,裁判所は,具体的な事案につき公平の観念に基づき諸般の事情を考慮し,自由なる裁量によって被害者の過失を斟酌して損害額を定めればよく,所論のごとく斟酌すべき過失の度合につき一々その理由を記載する必要はない。
そして,原判決は,その認定した事実のもとにおいて,被害者甲に過失がある旨を判示した上,過失相殺により損害額を約三分の二に減じたのであって,原判決には,所論のごとき違法のかどは見当らない。
同第二点について。
生命保険契約に基づいて給付される保険金は,すでに払い込んだ保険料の対価の性質を有し,もともと不法行為の原因と関係なく支払わるべきものであるから,たまたま本件事故のように不法行為により被保険者が死亡したためにその相続人たる被上告人両名に保険金の給付がされたとしても,これを不法行為による損害賠償額から控除すべきいわれはない。
したがって,損害額の算定に当ってこれを控除しなかった原判決の判断は正当であって,これと異なる所論は,独自の見解として排斥を免れない。
よって,民訴四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官奥野健一,同山田作之助,同草鹿浅之介,同城戸芳彦,同石田和外
消滅時効と除斥期間
不法行為に基づく損害賠償請求の消滅時効と除斥期間に関する重要裁判例(最高裁判所判決等)を実装しました。
除斥期間(最判決平成元年12月21日民集43巻12号2209頁 )
民法724条後段の法意
上告代理人藤井俊彦,同並木茂,同横山匡輝,同前田順司,同北野節夫,同森脇勝,同堀江憲二,同末永紘一,同長谷川哲,同松下邦男,同谷山幸雄,同田林均,同石山利夫,同大重五男の上告理由第一点について
一 原審が適法に確定した事実関係は,次のとおりである。
(一) 被上告人甲は,昭和二四年二月一四日,X町の山林中において,同山林中で発見された三個の不発油脂焼夷弾の処理作業に伴う山林の防火活動に従事していたが,その際,右不発弾の一個が同人の至近距離で突然爆発し,燃焼した油脂を顔面その他身体前面部全体に浴びて重傷を負った(以下「本件事故」という。)。(二) 右不発弾の処理は,国の公権力の行使に当たる公務員である国家地方警察鹿児島地区警察署西桜島派出所勤務,同警察署二俣派出所補勤の巡査乙又はその要請を受けた米軍小倉弾薬処理班の将兵二名がその職務として行ったものであり,前記山林の防火活動は,乙巡査の出動要請を受けた東桜島消防分団高免分団長丙の求めに応じて消防団員でない被上告人甲が乙部落の消防団員約二〇名と共に参加したものであった。(三) 右不発弾の処理作業は,米兵が不発弾の露出部分に爆薬を詰めて爆破装置により爆発させる方法をとり,爆破の際は全員が不発弾から五,六〇メートル離れた箇所に避難して行われた。このような方法で二個の不発弾の処理作業は終わったが,三個目の不発弾に前記爆破装置を付けて爆発させようとしたところ爆発せず,不発弾の胴体が割れ,そこから火が出て燻焼し,山火事の発生のおそれがある状況であったので,乙巡査らの指図で被上告人甲や消防団員らが右不発弾にスコップで砂をかぶせる作業をした。ところが,その作業が終わると同時に不発弾が突然爆発して本件事故が発生した。(四) 本件事故は,不発弾の爆発による人身事故等の発生を未然に防止すべき義務を負っていた乙巡査が,被上告人甲ら消防団員に燻焼し続ける極めて危険な不発弾にスコップで砂をかぶせる作業をさせる等した過失により発生した。(五) 本件事故の結果,被上告人甲は,全身の火傷に丹毒症を併発し,約六か月間入院加療して漸く一命をとりとめたものの,現在,顔面全体の瘢痕,高度の醜貌,左無眼球,右眼視力の極度の低下,両耳の難聴,瘢痕性萎縮による左肘関節の伸展位の固定等の後遺症がある。(六) 上告人は,昭和二四年八月から同年一二月までの間,四回にわたり療養見舞金として合計五万二三九〇円,同年一一月に療養費として四万五〇六〇円,昭和二六年三月及び同二八年二月に特別補償費事故見舞金として合計一〇万八〇〇〇円を被上告人甲に支払った。また,上告人は,昭和三七年九月に被上告人甲に対し,連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三六年法律第二一五号)に基づく障害給付金として一三万円,休業給付金として七五〇〇円を支払い,同四二年一二月には同法(昭和四二年法律第二号による改正後のもの)に基づき,被上告人甲に対し特別障害給付金として一八万四〇〇〇円,同人の妻である被上告人丁に対し障害者の妻に対する支給金として七万五〇〇〇円を支払った。(七) 被上告人甲及び同丁は,上告人に対し,本件事故発生の日から二八年一〇か月余を経過した昭和五二年一二月一七日,国家賠償法一条に基づき,本件事故による損害の賠償を求めて本訴を提起した。
二 原審は,以上の事実関係のもとにおいて,次の理由により,被上告人らは,上告人に対し,国家賠償法一条に基づき,損害賠償請求権(以下「本件請求権」という。)を有するとした上,被上告人らの請求は,被上告人甲につき慰謝料五〇〇万円,被上告人丁につき慰謝料二五〇万円及び右両名に対しそれぞれ右各金員に対する訴状送達の日の翌日である昭和五三年一月六日から完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容すべきものであり,被上告人らの請求を全部棄却した第一審判決は右のとおり変更すべきである旨判決した。
1 本件事故は国の公権力の行使に当たる乙巡査らがその職務を行うにつき過失によって被上告人らに損害を加えたものであり,上告人は,被上告人らに対し,国家賠償法一条により本件事故による損害を賠償する責任がある。
2 上告人は,本件事故発生の日から本訴提起の日まで二八年一〇か月余を経過しており,本件請求権は民法724条後段に規定する二〇年の除斥期間の経過により消滅した旨を主張するが,同条後段の二〇年の期間は,同条の規定の文言,立法者の説明,三年の短期時効に対する補充的機能,時効の中断,停止,援用を認めないと被害者に極めて酷な場合が生ずること等に照らし消滅時効を定めたものと考えるべきであり,仮に,これを除斥期間と解するとしても,被害者保護の観点から中断,停止を認めるいわゆる弱い除斥期間(混合除斥期間)であると解すべきである。
3 そして,本件事故当時,上告人の被用者である前記鹿児島地区警察署係員らにおいて上告人の右損害賠償義務を知り,又は容易に知りうべかりし状況にあった上,右事故直後,同警察署長名で本件事故の責任の所在を不明確にしたと認められる被害調査書が作成されたこと,被上告人らは,本件事故後,鹿児島市役所,鹿児島県庁等上告人の出先機関等に何度となく被害の救済を求めており,権利の上に眠る者とはいえないこと等原判示の事情を総合すると,上告人が本訴において被上告人らの本件請求権につき二〇年の長期の消滅時効を援用し,又は前記除斥期間の徒過を主張することは信義則に反し,権利の濫用として許されない。
三 しかし,原審の右判断は是認できない。その理由は,次のとおりである。
民法724条後段の規定は,不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものと解するのが相当である。けだし,同条がその前段で三年の短期の時効について規定し,更に同条後段で二〇年の長期の時効を規定していると解することは,不法行為をめぐる法律関係の速やかな確定を意図する同条の規定の趣旨に沿わず,むしろ同条前段の三年の時効は損害及び加害者の認識という被害者側の主観的な事情によってその完成が左右されるが,同条後段の二〇年の期間は被害者側の認識のいかんを問わず一定の時の経過によって法律関係を確定させるため請求権の存続期間を画一的に定めたものと解するのが相当であるからである。
これを本件についてみるに,被上告人らは,本件事故発生の日である昭和二四年二月一四日から二〇年以上経過した後の昭和五二年一二月一七日に本訴を提起して損害賠償を求めたものであるところ,被上告人らの本件請求権は,すでに本訴提起前の右二〇年の除斥期間が経過した時点で法律上当然に消滅したことになる。そして,このような場合には,裁判所は,除斥期間の性質にかんがみ,本件請求権が除斥期間の経過により消滅した旨の主張がなくても,右期間の経過により本件請求権が消滅したものと判断すべきであり,従って,被上告人ら主張に係る信義則違反又は権利濫用の主張は,主張自体失当であって採用の限りではない。
してみると,被上告人らの本訴請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がなく,これを棄却すべきものである。しかるに,これと異なる見解に立って本訴請求を一部認容した原判決は,民法724条後段の解釈適用を誤った違法があり,その違法は判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから,この点の違法をいう論旨は理由があり,その余の論旨について判断するまでもなく,原判決中,上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして,以上判示したところと結論を同じくする第一審判決は正当であるから,右部分に対する控訴は理由がなくこれを棄却すべきものである。
よって,民訴法四〇八条,三九六条,三八四条,九六条,八九条,九三条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官佐藤哲郎,裁判官角田禮次郎,同大内恒夫,同四ツ谷巖,同大堀誠一
除斥期間の起算点-じん肺(最判平成16年4月27日民集58巻4号1032頁)
加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合における民法724条後段所定の除斥期間の起算点
第1 事案の概要
1 被上告人らは,筑豊地区に存在した炭鉱で粉じん作業に従事したことによりじん肺にり患したと主張する者(1審判決別表1-5原告ら相続関係一覧表」の原告番号(元番)104~106,115,118,138,150,155,161,162,165,166,170,172,184,190,195,210,212,215,229,313,316,319,323,324,328,332,408及び414に対応する死亡従業員名欄記載の者,原判決別紙1「当事者目録」の番号109,112,113,117,136,146,175,189,216,217,306,314,322及び403記載の者並びに原判決別紙4「相続関係一覧表」の元番148,149,177,218,219及び226に対応する被承継者欄記載の者。以下「本件元従業員ら」という。)又はその承継人である。本件は,被上告人らが,上告人に対し,上告人がじん肺の発生又はその増悪を防止するために鉱山保安法に基づく規制権限を行使することを怠ったことが違法であるなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。
2 原審の適法に確定した事実関係及び関係法令の概要は,次のとおりである。
(1)じん肺法2条1項1号は,じん肺を,「粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病」と定義している。このうち,特に遊離けい酸を含有する粉じんの吸入によって生ずるものは「けい肺」と呼ばれ,後述のとおり,じん肺法制定前においては,専ら金属鉱山における遊離けい酸を含有する粉じんの吸入を原因とするけい肺に関心が寄せられてきた。
じん肺の病像は,肺胞内に取り込まれた粉じんが,リンパ腺や肺胞において長期間にわたり線維増殖性変化を進行させ,じん肺結節,小血管の閉そく等の病変を生じさせるというものであり,粉じんに暴露した後においても,じん肺結節が拡大融合するなどの病状が進行すること(進行性),いったん発生した線維増殖性変化,気腫性変化等を元の状態に戻すための治療方法がないこと(不可逆性)に特徴がある。発症までの期間は,粉じんへの暴露を開始してから最短でも2,3年,通常は5年~10年以上,長い場合で30年以上とされ,しばしば遅発性であって,粉じんへの暴露が終わった後,相当長期間経過後に発症することも少なくない。自覚症状としては,せき,たん,息切れ,呼吸困難等があり,病状が著しく重くなると,呼吸不全,心肺機能障害等から全身の衰弱を来し,肺結核等の合併症を生じ,死に至ることもある。
(2)じん肺に関する法令の概要は,以下のとおりである。
ア 昭和35年3月31日に公布されたじん肺法は,じん肺に関し,適正な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより,労働者の健康の保持を図ること等を目的とするものであり(1条),事業者にじん肺の予防のための措置を講ずべき義務を課し(5条),粉じん作業に従事する労働者等につき,じん肺健康診断の結果に基づいて健康管理の区分(管理一~四)が決定され,事業者は,当該労働者の管理区分に応じて従事させる作業内容を配慮すること等を定めている(4条,21条~23条)。じん肺法は,同法の制定に伴い廃止された「けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法」(昭和30年法律第91号。昭和35年法律第29号により廃止された。以下「けい肺特別保護法」という。)と同様,労働省の所管であった。
イ 昭和24年5月16日に公布された鉱山保安法は,鉱山労働者に対する危害の防止等を目的とするものであり(1条),鉱業権者は,粉じん等の処理に伴う危害又は鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならないものとされ(4条2号),同法30条の委任に基づき,金属鉱山等保安規則(昭和24年通商産業省令第33号),石炭鉱山保安規則(昭和24年通商産業省令第34号)等が,鉱業権者が同法4条の規定によって講ずべき具体的な保安措置を定めている。金属鉱山等保安規則は,石炭,亜炭及び石油を目的とする鉱業以外の鉱業,すなわち金属鉱山等における鉱業の保安について定めたものであり,石炭鉱山保安規則は,石炭鉱業及び亜炭鉱業に関する保安について定めたものである。同法及び両規則は、鉱業権者が鉱山労働者のじん肺を防止するために講ずべき粉じん対策等の規制の法的根拠となるものであり,いずれも通商産業省の所管であった。
(3)我が国における戦後から昭和30年代ころまでの国の石炭政策の概要は,次のとおりである。
戦時中,多くの炭鉱は,資材欠乏下での出炭強制により荒廃していたところ,政府は,石炭の増産が戦後経済復興のための最重要課題であるとの認識に基づき,昭和20年10月に石炭生産緊急対策を閣議決定するなどして,いわゆる傾斜生産方式と呼ばれる石炭増産政策を強力に推進した。なお,昭和24年5月の鉱山保安法の制定により,鉱山における保安行政は通商産業省(その前身である商工省)の所管とされたが(前記(2)イ参照),これは,石炭増産の必要性が考慮されたものであった。
その後,重油などの輸入エネルギーの増加等により,昭和28,29年には石炭大不況が到来した。政府は,これに対処するため,高能率炭鉱に生産を集中させ,非能率炭鉱の閉山を支援する合理化政策を進めることとなった。昭和30年7月には,石炭鉱業合理化臨時措置法が成立したが,政府は,その施行に当たり,重油に対抗していくための徹底的な合理化が必要であるとして,各企業に具体的な合理化策を指導するなどした。昭和38年からは,石炭鉱業の合理化政策の目標を「石炭が重油に対抗できないことを認めつつ,石炭鉱業の崩壊がもたらす社会的摩擦の回避等に着目した幅広い政策」とする第一次石炭政策が開始され,以後,数次にわたる石炭政策が策定された。
このように,政府は,戦後,いわば国策として,強力に石炭増産政策を推進し,また,合理化政策への転換後においても,石炭産業の経営にかかわる事項について強い影響力を及ぼしてきた。
(4)戦前から昭和30年代にかけてのじん肺に関する医学的知見の進展等は,次のとおりである。
ア 昭和の初めころまでは,粉じんの吸入を原因とする坑夫の職業病としては,専ら金属鉱山におけるけい肺が問題視されていた。けい肺は,金属鉱山等において遊離けい酸分を多量に含有する粉じんを長期間吸入することにより肺に線維増殖性変化を生ずる慢性疾患であり,呼吸困難,肺気腫等の症状がみられること,心肺機能の悪化,肺結核等との合併症を生じて死に至ることもあることは,その当時から,周知の事実とされていた。これに対し,当時,炭鉱において炭鉱夫がり患するじん肺は,炭肺などとも呼ばれ,症例もそれほど多くなく,ほとんどが軽症であるとされ,重大な職業病としての認識は,一般的に希薄であり,炭じんは無害でけい肺や肺結核の予防効果があるなどという説さえも存在した。その後,昭和10年ころまでには,炭鉱におけるけい肺患者の発生を指摘し,粉じん対策の必要性を説く講習会等も開かれるようになったが,やがて戦時体制になり,じん肺に関する医学的知見に大きな進展は見られなかった。
イ 戦後,金属鉱山を中心として,けい肺の撲滅を目指し,けい肺に関する特別法の制定を求める運動が広がり,鉱山経営者の生産協議会である金属鉱山復興会議が,けい肺対策に関する建議書を衆参両議院の議長あてに提出するなど,特別法制定の機運が高まった。そして,昭和25年には労働省がけい肺法案をけい肺協議会に付議し,昭和28年には国会議員がけい肺法案を国会に提出するなどしたが,いずれも法律制定には至らず,けい肺に関する特別法が制定されたのは,昭和30年7月29日に公布されたけい肺特別保護法が最初であった。けい肺特別保護法は,その2条1項1号で,けい肺を「遊離けい酸じん又は遊離けい酸を含む粉じんを吸入することによって肺に生じた繊(ママ)維増殖性変化の疾病及びこれと肺結核の合併した疾病」と定義していることからも明らかなように,同法は,遊離けい酸を含む粉じんの吸入により発症するけい肺を対象とし,その病勢の悪化の防止等を目的とするものであった(1条)。
ウ 労働省は,昭和23年10月,国の行政機関として初めて本格的なけい肺巡回検診を実施し,その結果,炭鉱においても,多くのけい肺患者が存在することが明らかとなった。さらに,労働省は,昭和30年9月から昭和32年3月にかけて,対象事業所数1万2981事業所,対象労働者数33万9450人(うち炭鉱労働者数14万4247人)に及ぶ国内外を通じて最大規模のけい肺健康診断を実施した。そして,昭和34年ころには,その実施結果として,有所見者が3万8738人であること,そのうち炭鉱労働者が1万1747人(全有所見者の約30%)にも達していることが明らかとなった。
エ 炭鉱夫じん肺に関する医学的知見に関しては,昭和30年前後から,医学雑誌に掲載された論文等において,炭鉱労働者のじん肺についての調査結果を踏まえて,炭鉱におけるじん肺の実情は軽視することができない旨を指摘したり,粉じんを有害なものと無害なものとに分けるべきではなく,すべての粉じんは,長期間多量に吸入すると有害である旨を指摘したりするものが多数に上り,さらに,炭じんをラットに長期間吸入させると,その肺に高度の線維増殖性結節が見られたとの動物実験の結果が紹介されるなど,炭じんを長期間吸入した場合には,じん肺にり患するおそれがある旨の医学的知見が次第に明確なものとなってきた。
オ 労働大臣は,昭和33年6月,けい肺審議会に,けい肺特別保護法の改正について諮問をし,同審議会は,医学的な観点からの専門的な検討を行うための医学部会を設置した。医学部会は,昭和34年9月,「けい肺に関する医学上の問題点についての意見」を公表し,「最近,屍体解剖の結果,石綿肺,ろう石肺,アルミニウム肺,けいそう土肺,その他各種のじん肺の存在が認められており,いずれのじん肺もそれが高度となってくれば,心肺機能障害を来すものであるので,あらゆる粉じんからの被害を予防し,健康管理を行っていく必要がある」との意見を表明した。この意見は,じん肺に関する当時の医学的知見に基づき,炭じん等のあらゆる種類の粉じんの吸入によるじん肺発症の可能性,危険性を肯定し,その症状が高度なものとなった場合の健康被害の重大性を指摘した上で,けい肺の原因となる遊離けい酸を含有する粉じんに限定せず,あらゆる種類の粉じんに対する被害の予防と健康管理の必要性を述べたものである。
カ 上記のとおり,炭鉱労働者のじん肺に関する実態が明らかとなり,じん肺に関する上記医学部会の意見が公表されたことから,けい肺に限定していた従来のじん肺に関する施策を根本的に見直す必要があると認識されるようになり,政府は,昭和34年12月,上記医学部会の意見に基づくけい肺審議会の答申を受けて,じん肺法案を国会に提出した。同法案は,国会審議を経て,昭和35年3月31日に可決成立し,同日公布され,翌4月1日に施行された。
制定当時のじん肺法は,じん肺を「鉱物性粉じんを吸入することによって生じたじん肺及びこれと肺結核の合併した病気」と定義した(2条1項1号)。これは,じん肺を,遊離けい酸を含有する粉じんの吸入によるけい肺に限定せず,炭じん等の鉱物性粉じんの吸入によって生じたものを広く含むものとして定義したものであり,これを同法による施策の対象とする趣旨である。なお,参議院社会労働委員会は,じん肺法案の採択に際し,「政府は,じん肺法の実施に当たっては,特に予防対策に主点をおき,労働衛生全般について適切なる指導を行うべきである」との附帯決議をした。
(5)じん肺法案が国会に提出された昭和34年当時の鉱山保安法30条の委任に基づく石炭鉱山保安規則による粉じん防止のための規制内容は,次のようなものであった。
石炭鉱業及び亜炭鉱業における粉じん対策に関する一般的な保安規制としては,「岩石の掘進,運搬,破砕等を行う坑内作業場において,岩石の掘進,運搬,破砕等によりいちぢるしく粉じんを飛散するときは,粉じんの飛散を防止するため,粉じん防止装置の設置,散水等適当な措置を講じなければならない。ただし,別に告示する規格に適合する防じんマスクを備えたときは,この限りでない。」と定められているにすぎなかった(昭和54年通商産業省令第115号による改正前の石炭鉱山保安規則284条)。これに対し、掘採作業場の岩盤中に遊離けい酸分を多量に含有し,通商産業大臣が指定する区域,すなわち「けい酸質区域」においては,規制を強化し,せん孔するときには,せん孔前に周囲の岩盤等に散水することを義務付け,衝撃式さく岩機を使用するときには,湿式型でなければならないものとしていた(昭和61年通商産業省令第74号による改正前の石炭鉱山保安規則284条の2)。岩盤中に遊離けい酸分を多量に含有するけい酸質区域のみを対象とする上記保安規制の強化は,昭和25年8月の石炭鉱山保安規則の改正により導入されたものであった。
上記の石炭鉱山保安規則による保安規制と同様の規制は,金属鉱山等保安規則においても,同時期に導入されたが,金属鉱山等保安規則においては,昭和27年9月の改正により,せん孔前の散水,衝撃式さく岩機の湿式型化を義務付ける旨の上記保安規制は,同規則が対象とする金属鉱山等のすべての坑内作業場に適用されるべき一般的な保安規制と改められ,同規則においては,けい酸質区城指定制度は廃止された。これに対し,石炭鉱山においては、上記金属鉱山等保安規則の改正後もけい酸質区域指定制度が維持され,その後,前記の炭鉱労働者に対する健康診断の実施結果や前記医学部会の意見が公表され,前記答申に基づきじん肺法が制定された昭和35年3月以降も,特定の指定区域だけを対象として保安規制の強化を図る上記制度が存続した。石炭鉱山保安規則において,せん孔前の散水,衝撃式さく岩機の湿式型化を義務付ける旨の保安規制が,一般的な保安規制に改められたのは,昭和61年11月であった。
(6)じん肺防止のための粉じん対策は,粉じんの生成,発散,吸入を防止することにあるが,中でも,粉じんの発生の抑止が粉じん対策の要であるとされており,昭和30年代初頭までには,さく岩機の湿式型化により粉じんの発生を著しく抑制することができるとの工学的知見が明らかとなっていた。また,そのころまでには,軽量の手持型湿式さく岩機が実用に供されるようになっており,遅くとも,昭和35年ころには,すべての石炭鉱山における衝撃式さく岩機の湿式型化を図ることに特段の障害はなかった。現に,金属鉱山においては,昭和27年9月に上記のとおり金属鉱山等保安規則が改正されて以降,坑内排水管の敷設及びさく岩機の湿式型化は急速に進展し,昭和29年までにはさく岩機の湿式型化率は99.7%となり,昭和33年までには坑内排水管の敷設率は100%を達成した。
これに対し,石炭鉱山においては,昭和36年の調査で,さく岩機の湿式型化率は,九州大手炭鉱で18.7%,九州中小炭鉱で5.9%にとどまり,金属鉱山と比較して大きく立ち遅れていた。とりわけ,けい酸質区城に指定された坑(以下「指定坑」という。)以外の坑(以下「非指定坑」という。)では,衝撃式さく岩機の湿式型化はほとんど進んでおらず,また,非指定坑の坑内作業の掘採現場において散水が行われていた箇所は,指定坑の3分の1程度でしかなく,非指定坑における湿式型化率,散水実施率は,極めて低かった。九州地区において,昭和35年までに指定された指定坑は,全体の3.6%にすぎず,また,その指定の基準(昭和31年の遊離けい酸分含有率40%基準,昭和34年の同30%基準等)自体も,粉じんの許容限度についての医学的な知見等に基づいて設定されたものではなく,非指定坑における炭坑労働者の粉じんへの暴露が健康上許容される範囲内のものであることを確保するための基準として,合理性の認められないものであった。そして,粉じんの生成,発散,吸入の各段階での対策を全体としてみても,昭和35年当時,湿式型さく岩機の導入と同等の効果を有するとされていた集じん機はさほど普及せず,また,防じんマスクの設置率も低調であり,その必要性に関する労働者の理解を深めるためのじん肺教育も不十分なものにとどまるなど,石炭鉱山におけるじん肺防止対策が適切に実施されているとはいえない状況であった。
3 原審は,上告人は,昭和35年3月のじん肺法の成立に合わせて石炭鉱山保安規則を見直し,前記のけい酸質区域指定制度を廃止するか,少なくとも,指定の基準を引き下げ,又はけい酸質区域の内外を問わず,衝撃式さく岩機の湿式型化等の粉じんの生成,発散防止策を義務付ける必要があったものというべきであり,上告人が,上記の時点において,これらの措置をいずれも採らなかったことは,著しく不合理といわざるを得ず,また,けい酸質区域の内外を問わず適用される粉じん対策についても,その指導,監督は不十分なものにとどまり,上記の不合理性を解消するに足りるものではなかったとして,上告人が上記規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとした上,同年4月以降に粉じん作業に従事し,じん肺にり患した本件元従業員らのうち,合併症のない管理二,三の認定を受けている者を除外した者につき,各損害の3分の1を限度として,損害賠償責任を負うと判断した。
第2 上告代理人都築弘外27名の上告受理申立ての理由第2,第3について
1 国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は,その権限を定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下において,その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは,その不行使により被害を受けた者との関係において,国家賠償法1条1項の適用上違法となるものと解するのが相当である(最高裁昭和61年(オ)第1152号平成元年11月24日第二小法廷判決・民集43巻10号1169頁,最高裁平成元年(オ)第1260号同7年6月23日第二小法廷判決・民集49巻6号1600頁参照)。
これを本件についてみると,鉱山保安法は,鉱山労働者に対する危害の防止等をその目的とするものであり(1条),鉱山における保安,すなわち,鉱山労働者の労働災害の防止等に関しては,同法のみが適用され,労働安全衛生法は適用されないものとされており(同法115条1項),鉱山保安法は,職場における労働者の安全と健康を確保すること等を目的とする労働安全衛生法の特別法としての性格を有する。そして,鉱山保安法は,鉱業権者は,粉じん等の処理に伴う危害又は鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならないものとし(4条2号),同法30条は,鉱業権者が同法4条の規定によって講ずべき具体的な保安措置を省令に委任しているところ,同法30条が省令に包括的に委任した趣旨は,規定すべき鉱業権者が講ずべき保安措置の内容が,多岐にわたる専門的,技術的事項であること,また,その内容を,できる限り速やかに,技術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正していくためには,これを主務大臣にゆだねるのが適当であるとされたことによる。
同法の目的,上記各規定の趣旨にかんがみると,同法の主務大臣であった通商産業大臣の同法に基づく保安規制権限,特に同法30条の規定に基づく省令制定権限は,鉱山労働者の労働環境を整備し,その生命,身体に対する危害を防止し,その健康を確保することをその主要な目的として,できる限り速やかに,技術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正すべく,適時にかつ適切に行使されるべきものである。
2 前記の事実関係によれば,次のことが明らかである。(1)労働省が昭和30年9月から昭和32年3月にかけて実施した大規模なけい肺健康診断の結果により,昭和34年ころには,全有所見者の約30%,1万人を超える炭鉱労働者の有所見者が存在することなど,炭坑労働者のじん肺り患の実情が相当深刻なものであることが明らかになっていた。(2)じん肺に関する医学的知見に関しては,けい肺審議会医学部会が,昭和34年9月,じん肺に関する当時の医学的知見に基づき,炭じん等のあらゆる種類の粉じんの吸入によるじん肺発症の可能性,危険性を肯定し,その症状が高度なものとなった場合の健康被害の重大性を指摘した上で,けい肺の原因となる遊離けい酸を含有する粉じんに限定せず,あらゆる種類の粉じんに対する被害の予防と健康管理の必要性を指摘する旨の意見を公表した。(3)上記のとおり,炭鉱労働者のじん肺り患の深刻な実情が明らかとなり,じん肺に関する上記医学部会の意見が公表されたことから,けい肺に限定していた従来のじん肺に関する施策を根本的に見直す必要があると認識されるようになり,政府は,昭和34年12月,上記医学部会の意見に基づくけい肺審議会の答申を受けて,じん肺法案を国会に提出したが,同法案は,じん肺を,遊離けい酸を含有する粉じんの吸入によるけい肺に限定せず,炭じん等の鉱物性粉じんの吸入によって生じたものを広く含むものとして定義し,これを同法による施策の対象とするものであった。(4)じん肺防止のための粉じん対策の要は,粉じんの発生の抑止であるとされているが,昭和30年代初頭までには,さく岩機の湿式型化により粉じんの発生を著しく抑制することができるとの工学的知見が明らかとなっており,また,そのころまでには,軽量の手持型湿式さく岩機が実用に供されるようになっていたことから,遅くとも,昭和35年ころまでには,すべての石炭鉱山における衝撃式さく岩機の湿式型化を図ることに特段の障害はなく,現に,金属鉱山においては,昭和27年9月に金属鉱山等保安規則が改正されて以降,さく岩機の湿式型化は急速に進展し,昭和29年までにはさく岩機の湿式型化率は99.7%を達成していた。(5)しかるに,石炭鉱山においては,前記のとおり,いわば国策としての強力な石炭増産政策が推進されるなどしてきたのに,上記金属鉱山等保安規則の改正後も,石炭鉱山保安規則によるけい酸質区域指定制度が維持され,その後,前記答申に基づきじん肺法が制定された昭和35年3月以降も,指定の基準も含め,保安規制に関する大きな見直しもされずに,上記制度が存続し,せん孔前の散水,衝撃式さく岩機の湿式型化を義務付ける旨の保安規制が,一般的な保安規制に改められたのは,昭和61年11月であった。そのため,石炭鉱山においては,その大部分を占める非指定坑におけるさく岩機の湿式型化率,せん孔前の散水実施率は極めて低い状態で推移したのであり,じん肺防止対策の実施状況は,一般的な粉じん対策も含めて,極めて不十分なものであった。
以上の諸点に照らすと,通商産業大臣は,遅くとも,昭和35年3月31日のじん肺法成立の時までに,前記のじん肺に関する医学的知見及びこれに基づくじん肺法制定の趣旨に沿った石炭鉱山保安規則の内容の見直しをして,石炭鉱山においても,衝撃式さく岩機の湿式型化やせん孔前の散水の実施等の有効な粉じん発生防止策を一般的に義務付ける等の新たな保安規制措置を執った上で,鉱山保安法に基づく監督権限を適切に行使して,上記粉じん発生防止策の速やかな普及,実施を図るべき状況にあったというべきである。そして,上記の時点までに,上記の保安規制の権限(省令改正権限等)が適切に行使されていれば,それ以降の炭坑労働者のじん肺の被害拡大を相当程度防ぐことができた。
本件における以上の事情を総合すると,昭和35年4月以降,鉱山保安法に基づく上記の保安規制の権限を直ちに行使しなかったことは,その趣旨,目的に照らし,著しく合理性を欠くものであって,国家賠償法1条1項の適用上違法である。
したがって,同項による上告人の損害賠償責任を認めた原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用できない。
第3 上告代理人都築弘外27名の上告受理申立て理由第4について
民法724条後段所定の除斥期間の起算点は,「不法行為ノ時」と規定されており,加害行為が行われた時に損害が発生する不法行為の場合には,加害行為の時がその起算点となると考えられる。しかし,身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害や,一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害のように,当該不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると解すべきである。なぜなら,このような場合に損害の発生を待たずに除斥期間の進行を認めることは,被害者にとって著しく酷であるし,また,加害者としても,自己の行為により生じ得る損害の性質からみて,相当の期間が経過した後に被害者が現れて,損害賠償の請求を受けることを予期すべきであると考えられるからである。
これを本件についてみるに,前記のとおり,じん肺は,肺胞内に取り込まれた粉じんが,長期間にわたり線維増殖性変化を進行させ,じん肺結節等の病変を生じさせるものであって,粉じんへの暴露が終わった後,相当長期間経過後に発症することも少なくないから,じん肺被害を理由とする損害賠償請求権については,その損害発生の時が除斥期間の起算点となる。これと同旨の原審の判断は,正当として是認できる。論旨は採用できない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官藤田宙靖,裁判官金谷利廣,同濱田邦夫,同上田豊三
除斥期間と起算点-水俣病(最判平成16年10月15日民集58巻7号1802頁)
水俣病による健康被害につき加害行為の終了から相当期間を経過した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例
第1 事案の概要
1 被上告人らは,水俣病の患者であると主張する者(原判決別紙「結果一覧表」の患者氏名欄記載の58名のうち,患者番号13~15,28,41,42,44,46,47,52,53,58,59の13名を除く45名。以下「本件患者」と総称する。)又はその承継人である。本件は,被上告人らが,上告人らは水俣病の発生及び被害拡大の防止のために規制権限を行使することを怠ったことにつき国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うなどと主張して,上告人らに対し,損害賠償を請求する訴訟である。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)水俣病は,水俣湾又はその周辺海域の魚介類を多量に摂取したことによって起こる中毒性中枢神経疾患である。その主要な症状としては,感覚障害,運動失調,求心性視野狭さく,聴力障害,言語障害等がある。個々の患者には重症例から軽症例まで多様な形態がみられ,症状が重篤なときは,死亡するに至る。
水俣病の原因物質は,有機水銀化合物の一種であるメチル水銀化合物であり,これは,チッソ株式会社(昭和40年に商号を変更する前の商号は,新日本窒素肥料株式会社。以下「チッソ」という。)水俣工場のアセトアルデヒド製造施設内で生成され,同工場の排水に含まれて工場外に流出したものであった。水俣病は,このメチル水銀化合物が,魚介類の体内に蓄積され,その魚介類を多量に摂取した者の体内に取り込まれ,大脳,小脳等に蓄積し,神経細胞に障害を与えることによって引き起こされた疾病である。
(2)本件患者らは,かつて水俣湾周辺地域に居住し,水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取していた。本件患者らのうち,甲(患者番号16),T23(同17),T36(同24),T51(同32),T52(同33),乙(同34),丙(同45),T68(同49)は昭和34年12月末までに,それ以外の者は昭和35年1月以降に,関西方面に転居した。
(3)昭和31年5月1日,チッソ水俣工場附属病院の医師が,水俣保健所に対し,水俣市内において脳症状を呈する原因不明の患者が発生した旨の報告をした。公的機関が水俣病の存在を認識したのはこれが初めてであり,この時が水俣病の「公式発見」と呼ばれる。この報告を受けた水俣保健所等が調査をしたところ,昭和28年ころから同様の症状を呈する患者が発生していたこと,昭和32年1月の時点で54名の患者が発生し,うち17名が死亡していたことが判明した。
(4)水俣病の原因については,上記公式発見以降,水俣保健所,熊本大学医学部の水俣病医学研究班(以下「熊大研究班」という。),厚生省(以下,省庁名,官職名等は,いずれも当時のものである。)の厚生科学研究班等により,調査や研究が行われた。原因究明は困難を極めたが,昭和31年11月開催の熊大研究班の研究報告会において魚介類との関係が一応疑われるとの報告がされ,昭和32年1月開催の国立公衆衛生院での上告人国,上告人県の関係者も参加した合同研究発表会において魚介類の摂取が原因であるとの一応の結論に達した。上告人県は,水俣市の住民に対して水俣湾の魚介類を摂取しないように呼び掛けるとともに,湾内での漁業を自粛するよう,地元の漁業協同組合に申し入れた。このような行政指導の結果,昭和31年12月以降,しばらくの間は,新たな患者の発生がみられなくなった。
昭和32年7月開催の厚生科学研究班の研究報告会において,水俣病は,感染症ではなく,中毒症であり,何らかの化学物質によって汚染された魚介類を多量に摂取することによって発症するものであるとの結論が示されたが,原因物質が何であるかは不明のままであり,当時は,マンガン,タリウム,セレン等の物質が疑われていた。
昭和33年6月開催の参議院社会労働委員会において,厚生省環境衛生部長は,水俣病の原因物質は水俣市の肥料工場から流失したと推定されるとの発言をした。また,同年7月,同省公衆衛生局長は,関係省庁及び上告人県に対して発した文書により,水俣病はある種の化学毒物によって有毒化された魚介類を多量に摂取することによって発症するものであり,肥料工場の廃棄物によって魚介類が有毒化されると推定した上で,水俣病の対策について一層効率的な措置を講ずることを要望した。他方,通商産業省(以下「通産省」という。)軽工業局長は,同年9月ころ,厚生省に対し,水俣病の原因が確定していない現段階において断定的な見解を述べることがないよう申し入れた。
(5)昭和33年8月,新たな水俣病患者の発生が確認された。この患者は,水俣湾の魚介類を自ら捕獲して,多量に摂取したものであった。上告人県は,水俣湾の魚介類を摂取しないことを周知徹底させるべく,住民に対して改めて広報活動を行うとともに,地元の漁業協同組合に対し漁業を自粛するよう申し入れた。
(6)昭和33年9月,チッソは,アセトアルデヒド製造施設からの排水の放出経路を,水俣湾内にある百間港から湾外の水俣川河口付近へと変更した。その結果,昭和34年3月以降,水俣湾外の海域で漁獲された魚介類を多食していた者についても水俣病の発症が確認され,湾外の魚介類も危険視されることとなった。
(7)昭和34年3月刊行の熊大研究班の報告書に,水俣病の症状が有機水銀中毒の症状(いわゆるハンター・ラッセル症候群)と一致する旨を述べた論文が掲載された。熊大研究班は,その後も調査研究を続け,同年7月22日に開催された研究報告会において,水俣病は現地の魚介類を摂取することによって引き起こされる神経系疾患であり,魚介類を汚染する毒物としては水銀が極めて注目されるに至ったと発表した。
また,厚生大臣の諮問機関である食品衛生調査会の特別部会として昭和34年1月に発足した水俣食中毒部会は,同年10月6日,水俣病は有機水銀中毒症に酷似しており,その原因物質としては水銀が最も重要視されるとの中間報告を行った。同年11月12日,食品衛生調査会は,この中間報告に基づいて,水俣病の主因を成すものはある種の有機水銀化合物であるとの結論を出し,厚生大臣に対してその旨を答申した。水俣食中毒部会は,この答申によりその目的を達したとして,そのころ解散した。その後,水俣病の原因についての総合的な調査研究は,経済企画庁が中心となり,厚生省,通産省及び水産庁が分担して行うものとされた。
なお,昭和34年10月ころ,チッソ水俣工場附属病院の医師が行った実験により,チッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設の排水を経口投与したネコに水俣病と同様の症状が現れることが認められた。ところが,チッソは,実験の続行を中止し,この実験結果を公表しなかった。
(8)上告人らが把握していた昭和34年8月現在の水俣病患者の発生状況は,患者数71名,死亡者28名であった。通産省は,そのころ,水俣病が現地において極めて深刻な問題となっている状況にかんがみ,チッソ水俣工場に対し,口頭で,水俣川河口への排水路を廃止すること,排水処理装置の完備を急ぐこと,原因究明のための調査に十分協力することを求める行政指導を行った。また,通産省は,同年10月末から11月にかけて,厚生省公衆衛生局長,水産庁長官等から,チッソ水俣工場の排水に対して適切な処置を至急講ずるよう求める旨の要望を受けたので,チッソの社長あてに文書を送付して,一刻も早く排水処理施設を完備することなどを求めた。
昭和34年12月,サイクレーター,セディフローターを主体とする排水浄化装置がチッソ水俣工場に設置された。チッソは,これによって工場排水が浄化される旨を強調したが,この装置は水銀の除去を目的とするものではなかった。そのことは,多少の化学知識のある者が,上記装置の設計図等を見れば,容易に知ることができた。
(9)昭和34年12月,熊本県知事らのあっせんにより,チッソと熊本県漁業協同組合連合会との間に漁業補償に関する契約が,水俣病患者家庭互助会との間に見舞金の支払に関する契約が,それぞれ締結された。
(10)昭和34年当時の総水銀(有機水銀化合物に加え,金属水銀,無機水銀化合物を含むもの)の一般的な定量分析技術においては,0.01ppmが定量分析の限界であるとされていたが,工業技術院東京工業試験所は,同年11月下旬ころには,独自に工夫した方法によって総水銀について0.001ppmレベルまで定量分析し得る技術を有していた。同試験所は,そのころから昭和35年8月までの間,通産省の依頼を受けて,チッソ水俣工場の排水中の総水銀を定量分析し,0.002~0.084ppmの総水銀が検出されたとの検査結果を報告した。
(11)上告人らは,遅くとも昭和34年11月末ころまでには,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であること,その排出源がチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあった。また,上告人らにおいて,そのころまでには,チッソ水俣工場の排水に微量の水銀が含まれていることについての定量分析は可能であったし,チッソが整備した上記排水浄化施設が水銀の除去を目的としたものではなかったことも容易に知ることができた。
(12)昭和43年5月,チッソは,水俣工場におけるアセトアルデヒドの製造を取りやめた。これにより,同工場からメチル水銀化合物が排出されることはなくなった。同年9月,上告人国は,水俣病はチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設内で生成されたメチル水銀化合物が原因で発生したものである旨の政府見解を発表した。昭和44年,水俣湾及びその周辺海域について,後述する水質二法に基づく指定水域の指定等がされた。
第2 平成13年(オ)第1194号上告代理人都築弘ほかの上告理由について
1 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備及び食違いをいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,上記各項に規定する事由に該当しない。
2 所論にかんがみ,職権により判断する。
前記の事実関係の下において,上告人らが,昭和35年1月以降,チッソ水俣工場の排水に関して規制権限を行使しなかったことが違法であり,上告人らは,同月以降に水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取して水俣病となった者及び健康被害の拡大があった者に対して国家賠償法1条1項による損害賠償責任を負うとした原審の判断は,後述のとおり,正当として是認することができる。そうすると,本件患者らのうち,昭和34年12月末以前に水俣湾周辺地域からその地域外へ転居した者については,水俣病となったことによる損害を受けているとしても,上告人らの上記の違法な不作為と損害との間の因果関係を認めることはできない。ところが,原審は,本件患者らのうち甲,T23,T36,T51,T52,乙,丙,T68について,昭和34年12月末以前に水俣湾周辺地域から転居したとの事実を認定しながら,上記8名の本件患者に係る損害賠償請求を一部認容したものであって,原判決には,上告人らの上記の違法な不作為と損害との間の因果関係の存否の判断につき,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるといわざるを得ない。
したがって,原判決のうち,上記8名の本件患者ら又はその承継人である被上告人T22,同T23,同T36,同T51,同T52,同T53,同T54,同T55,同T64,同T65,同T66,同T67及び同T68の上告人らに対する請求(ただし,被上告人T36,同T51及び同T52については,丁(患者番号31)の承継人として請求する部分を除く。)を認容した部分は,破棄を免れない。そして,同部分に係る上記被上告人らの請求を棄却した第1審判決は,結論において是認することができるから,同部分についての上記被上告人らの控訴はいずれも棄却されるべきものである。
第3 平成13年(受)第1172号上告代理人都築弘ほかの上告受理申立て理由第3及び第4について
1 公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和45年法律第108号による改正前のもの。以下「水質保全法」という。)及び工場排水等の規制に関する法律(以下「工場排水規制法」という。また,水質保全法と併せて,「水質二法」という。)は,昭和33年12月25日に公布され,昭和34年3月1日に施行された(その後,水質二法は,昭和45年12月に公布された水質汚濁防止法の施行に伴って廃止された。)。水質保全法は,公共用水域の水質の保全を図るなどのために必要な事項を定め,もって産業の相互協和と公衆衛生の向上に寄与することを目的とするものであり(同法1条),工場排水規制法は,製造業等における事業活動に伴って発生する汚水等の処理を適切にすることにより,公共用水域の水質の保全を図ることを目的とするものである(同法1条)。水質二法による工場排水規制の概要は,次のとおりである。
経済企画庁長官は,公共用水域のうち,水質の汚濁が原因となって関係産業に相当の被害が生じ,若しくは公衆衛生上看過し難い影響が生じているもの又はそれらのおそれのあるものを「指定水域」として指定するとともに(水質保全法5条1項),当該指定水域に係る「水質基準」を定めるものとされている(同条2項)。水質基準とは,「特定施設」を設置する工場等から指定水域に排出される水の汚濁の許容限度であり(同法3条2項),特定施設とは,製造業等の用に供する施設のうち,汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)を排出するもので政令で定めるものである(工場排水規制法2条2項)。また,主務大臣(特定施設の種類ごとに,政令により定められる。同法21条1項)は,工場排水の水質が当該指定水域に係る水質基準に適合しないと認めるときは,これを排出する者に対し,汚水等の処理方法に関する計画の変更,特定施設の設置に関する計画の変更等を命ずること(同法7条),汚水等の処理方法の改善,特定施設の使用の一時停止その他必要な措置を執るべき旨を命ずること(同法12条)等の,特定施設から排出される工場排水に関して規制を行う権限を有するものとされており,主務大臣の上記命令に違反した者は,罰則を科される(同法23条)。
2 熊本県漁業調整規則(昭和26年熊本県規則第31号。以下「県漁業調整規則」という。なお,この規則は,昭和40年熊本県規則第18号の2により廃止された。)は,漁業法(昭和37年法律第156号による改正前のもの)65条及び水産資源保護法4条の規定に基づいて制定されたものであり,水産動植物の繁殖保護,漁業取締りその他漁業調整を図り,併せて漁業秩序の確立を期するため,必要な事項を定めることを目的とするものである(県漁業調整規則1条)。
県漁業調整規則は,何人も水産動植物の繁殖保護に有害な物を遺棄し,又は漏せつするおそれのあるものを放置してはならない旨を定め,これに違反する者があるときは,熊本県知事は,その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ,又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができるものとされている(同規則32条)。上記の規定又は命令に違反した者に対しては罰則が科される(同58条)。
3 原審は,前記の事実関係の下において,チッソ水俣工場の排水につき,上告人国においては上記の水質二法に基づく規制権限を,上告人県においては上記の県漁業調整規則に基づく規制権限を,それぞれ行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,昭和35年1月以降に水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取して水俣病となった者及び健康被害が拡大した者に対して,同項による損害賠償責任を負うと判断した。
上告人らの論旨は,原審の上記判断は,水質二法,県漁業調整規則の関係規定及び国家賠償法1条1項の解釈適用を誤ったものであり,法令に違反する旨を主張するものである。
4 そこで,以下,この点について検討する。
(1)国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は,その権限を定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下において,その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは,その不行使により被害を受けた者との関係において,国家賠償法1条1項の適用上違法となるものと解するのが相当である(最高裁昭和61年(オ)第1152号平成元年11月24日第二小法廷判決・民集43巻10号1169頁,最高裁平成元年(オ)第1260号同7年6月23日第二小法廷判決・民集49巻6号1600頁参照)。
(2)これを本件についてみると,まず,上告人国の責任は,次のとおりである。
ア 水質二法所定の前記規制は,① 特定の公共用水域の水質の汚濁が原因となって,関係産業に相当の損害が生じたり,公衆衛生上看過し難い影響が生じたりしたとき,又はそれらのおそれがあるときに,当該水域を指定水域に指定し,この指定水域に係る水質基準(特定施設を設置する工場等から指定水域に排出される水の汚濁の許容限度)を定めること,汚水等を排出する施設を特定施設として政令で定めることといった水質二法所定の手続が執られたことを前提として,② 主務大臣が,工場排水規制法7条,12条に基づき,特定施設から排出される工場排水等の水質が当該指定水域に係る水質基準に適合しないときに,その水質を保全するため,工場排水についての処理方法の改善,当該特定施設の使用の一時停止その他必要な措置を命ずる等の規制権限を行使するものである。そして,この権限は,当該水域の水質の悪化にかかわりのある周辺住民の生命,健康の保護をその主要な目的の一つとして,適時にかつ適切に行使されるべきものである。
イ 前記の事実関係によれば,昭和34年11月末の時点で,① 昭和31年5月1日の水俣病の公式発見から起算しても既に約3年半が経過しており,その間,水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取する住民の生命,健康等に対する深刻かつ重大な被害が生じ得る状況が継続していたのであって,上告人国は,現に多数の水俣病患者が発生し,死亡者も相当数に上っていることを認識していたこと,② 上告人国においては,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であり,その排出源がチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあったこと,③ 上告人国にとって,チッソ水俣工場の排水に微量の水銀が含まれていることについての定量分析をすることは可能であったことといった事情を認めることができる。なお,チッソが昭和34年12月に整備した前記排水浄化装置が水銀の除去を目的としたものではなかったことを容易に知り得たことも,前記認定のとおりである。そうすると,同年11月末の時点において,水俣湾及びその周辺海域を指定水域に指定すること,当該指定水域に排出される工場排水から水銀又はその化合物が検出されないという水質基準を定めること,アセトアルデヒド製造施設を特定施設に定めることという上記規制権限を行使するために必要な水質二法所定の手続を直ちに執ることが可能であり,また,そうすべき状況にあったものといわなければならない。そして,この手続に要する期間を考慮に入れても,同年12月末には,主務大臣として定められるべき通商産業大臣において,上記規制権限を行使して,チッソに対し水俣工場のアセトアルデヒド製造施設からの工場排水についての処理方法の改善,当該施設の使用の一時停止その他必要な措置を執ることを命ずることが可能であり,しかも,水俣病による健康被害の深刻さにかんがみると,直ちにこの権限を行使すべき状況にあったと認めるのが相当である。また,この時点で上記規制権限が行使されていれば,それ以降の水俣病の被害拡大を防ぐことができたこと,ところが,実際には,その行使がされなかったために,被害が拡大する結果となったことも明らかである。
ウ 本件における以上の諸事情を総合すると,昭和35年1月以降,水質二法に基づく上記規制権限を行使しなかったことは,上記規制権限を定めた水質二法の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,著しく合理性を欠くものであって,国家賠償法1条1項の適用上違法である。
従って,同項による上告人国の損害賠償責任を認めた原審の判断は,正当として是認することができる。この点に関する上告人国の論旨は採用することができない。
(3)次に,上告人県の責任についてみると,以上説示したところによれば,前記事実関係の下において,熊本県知事は,水俣病にかかわる前記諸事情について上告人国と同様の認識を有し,又は有し得る状況にあったのであり,同知事には,昭和34年12月末までに県漁業調整規則32条に基づく規制権限を行使すべき作為義務があり,昭和35年1月以降,この権限を行使しなかったことが著しく合理性を欠くものであるとして,上告人県が国家賠償法1条1項による損害賠償責任を負うとした原審の判断は,同規則が,水産動植物の繁殖保護等を直接の目的とするものではあるが,それを摂取する者の健康の保持等をもその究極の目的とするものであると解されることからすれば,是認することができる。この点に関する上告人県の論旨を採用できない。
第4 平成13年(受)第1172号上告代理人都築弘ほかの上告受理申立て理由第5について
1 被上告人らの上告人らに対する請求(前記第2で判示したところにより棄却されるべき部分を除く。)については,国家賠償法4条,民法724条後段所定の除斥期間の適用の有無が問題となるところ,原審は,その適用を否定した。
上告人らの論旨は,原審の上記判断は,上記各規定の解釈適用を誤ったものであり,法令に違反する旨を主張するものである。
2 そこで,以下,この点について検討する。
(1)民法724条後段所定の除斥期間は,「不法行為ノ時ヨリ二十年」と規定されており,加害行為が行われた時に損害が発生する不法行為の場合には,加害行為の時がその起算点となると考えられる。しかし,身体に蓄積する物質が原因で人の健康が害されることによる損害や,一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病による損害のように,当該不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると解するのが相当である。このような場合に損害の発生を待たずに除斥期間が進行することを認めることは,被害者にとって著しく酷であるだけでなく,加害者としても,自己の行為により生じ得る損害の性質からみて,相当の期間が経過した後に損害が発生し,被害者から損害賠償の請求を受けることがあることを予期すべきであると考えられるからである。原審の判断は,以上の趣旨をいうものとして,是認することができる。論旨は採用することができない。
(2)上記見解に立って本件をみると,本件患者のそれぞれが水俣湾周辺地域から他の地域へ転居した時点が各自についての加害行為の終了した時であるが,水俣病患者の中には,潜伏期間のあるいわゆる遅発性水俣病が存在すること,遅発性水俣病の患者においては,水俣湾又はその周辺海域の魚介類の摂取を中止してから4年以内に水俣病の症状が客観的に現れることなど,原審の認定した事実関係の下では,上記転居から遅くとも4年を経過した時点が本件における除斥期間の起算点となるとした原審の判断も,是認し得るものということができる。この点に関する上告人らの論旨も採用できない。
第5 平成13年(受)第1172号上告代理人都築弘ほかのその余の上告受理申立て理由について
所論の点に関する原審の事実認定は,原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り,上記事実関係の下においては,原審の判断は是認することができる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用できない。
第6 平成13年(オ)第1196号附帯上告代理人松本健男ほかの附帯上告理由について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件附帯上告の理由は,理由の不備及び食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,上記各項に規定する事由に該当しない。
第7 平成13年(受)第1174号附帯上告代理人松本健男ほかの附帯上告受理申立て理由について
所論の点に関する原審の事実認定は,原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り,上記事実関係の下においては,原審の判断は是認することができる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用できない。
第8 結論
以上によれば,上告人らの上告は,前記第2の限度で理由があるから,主文第1項記載の部分につき原判決を破棄し,同第3項記載の部分につき原判決を変更すべきものであるが,その余の上告はいずれも理由がないので,これを棄却することとする。また,附帯上告人らの附帯上告には理由がないので,これを棄却する。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁判所裁判長裁判官北川弘治,裁判官福田博,同滝井繁男,同津野修
除斥期間の起算点(最判平成18年6月16日民集60巻5号1997頁 )
乳幼児期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染し,これによる損害につきB型肝炎を発症した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となるか。
第1 事案の概要
1 原審が適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1)当事者
ア 平成16年(受)第673号被上告人(第1審原告)X1(以下「原告X1」という。)は,昭和39年▲月▲日生まれであり,昭和61年10月ころ,B型肝炎と診断され,その後,入通院を経て,現在,小葉改築傾向のある慢性B型肝炎の患者として経過観察中である。
原告X1は,原判決別紙〔a〕1(ただし,番号10,11を除く。)のとおり,昭和39年12月~昭和46年2月,集団ツベルクリン反応検査及び集団予防接種(以下,これらを併せて「集団予防接種等」という。)を受けた。
原告X1の弟は,B型肝炎ウイルスの持続感染者(キャリア)であるが,父母は持続感染者ではない。ただし,父母は,いずれも過去にB型肝炎ウイルスに感染したことがある。
イ 平成16年(受)第672号上告人(第1審原告)X4(以下「原告X4」という。)は,昭和26年▲月▲日生まれであり,昭和59年8月ころ,B型肝炎と診断され,その後,入通院を経て,現在,慢性B型肝炎の患者として経過観察中である(内視鏡的には斑紋肝,組織学的には小葉改築を伴う肝炎との診断を受けている。)。
原告X4は,原判決別紙〔a〕2のとおり,昭和26年9月~昭和33年3月,集団予防接種等を受けた。
原告X4の父母,妻子は,B型肝炎ウイルスの持続感染者ではない。ただし,父,妻,子は,いずれも過去にB型肝炎ウイルスに感染したことがある。
ウ 平成16年(受)第672号上告人(第1審原告)X5(以下「原告X5」という。)は,昭和36年▲月▲日生まれであり,昭和61年10月,B型肝炎と診断され,その後,入通院を経て,現在,小葉改築のない慢性B型肝炎の患者として経過観察中である。
原告X5は,原判決別紙〔a〕3のとおり,昭和37年1月~昭和42年10月,集団予防接種等を受けた。
原告X5の父母は,B型肝炎ウイルスの持続感染者ではない。ただし,父,妹,弟は,いずれも過去にB型肝炎ウイルスに感染したことがある。
エ 第1審原告X2(以下「原告X2」という。)は,昭和39年▲月▲日生まれであり,昭和57年ころ,献血の際にHBs抗原陽性であると指摘され,昭和60年3月,北海道勤労者医療協会の職員採用時の検査において肝機能障害の指摘を受け,その後,入通院を経て,小葉改築のない慢性B型肝炎の患者として経過観察中であったが,平成2年ころ,セロコンバージョン(HBe抗原陽性からHBe抗体陽性への変換)が起きていることが確認された。
原告X2は,原判決別紙〔a〕4(ただし,番号7を除く。)のとおり,昭和40年2月~昭和45年2月,集団予防接種等を受けた。
原告X2の父母は,B型肝炎ウイルスの持続感染者ではない。ただし,父,母,弟は,いずれも過去にB型肝炎ウイルスに感染したことがある。
なお,原告X2は,本件訴訟が原審に係属中の平成14年▲月▲日に死亡し,その妻子である平成16年(受)第673号被上告人X6,同X7,同X8が,本件訴訟を承継した(以下においては,これらの訴訟承継人を含めて「原告X2」ということもある。)。
オ 平成16年(受)第673号被上告人(第1審原告)X3(以下「原告X3」という。)は,昭和58年▲月▲日生まれであり,昭和59年4月22日,B型肝炎ウイルスの持続感染者であることが判明した。
原告X3は,原判決別紙〔a〕5のとおり,昭和58年8月25日に集団ツベルクリン反応検査を受け,同月27日に集団BCG接種を受けた。
原告X3の父,兄は,いずれも過去にB型肝炎ウイルスに感染していない。母は,昭和55年12月4日の検査ではHBs抗原陰性,昭和57年12月8日の検査ではHBs抗原,HBs抗体とも陰性であったが,昭和59年4月13日に急性肝炎と診断され,入院した。入院時の検査によると,HBs抗原,HBe抗原がともに陽性であり,B型肝炎ウイルスによるものと判明したが,その後の経過は良好で,入院後間もなくHBs抗原が消失し,同年5月8日,退院した。
(2)B型肝炎
ア B型肝炎は,B型肝炎ウイルスに感染することによって発症する肝炎(ウイルスを排除しようとする免疫反応により,自らの肝細胞を破壊し,肝臓に炎症を起こした状態)であり,慢性化して長期化すると,肝硬変,肝がんを発症させることがある。B型肝炎については,これまでに感染予防ワクチンが開発されて実用化され,治療法としてインターフェロン療法,ステロイド離脱療法が限定された範囲での有効性を認められ,新薬であるラミブジンの効果が期待されているものの,決定的な効果を有する治療法はいまだ開発されていない。
なお,肝炎ウイルスについては,昭和45年に検査方法が確立され,また,B型肝炎ウイルスは,昭和48年に発見された。
イ B型肝炎ウイルスは,血液を介して人から人へ感染する。ただし,皮膚接触による感染,経口感染,精液等の体液による感染についても,体液に血液が混じっていることがあり得ることや,B型肝炎ウイルスの感染力の強さなどから,その可能性は否定されない。
一般的予防法としては,血液付着の回避,医療器具等血液付着のおそれのある器具の消毒又は廃棄がある。B型肝炎ウイルスに汚染された医療器具等の消毒方法としては,器具等の使用後速やかに当該器具等に付着している血清たんぱくを十分に洗い流し,その後に滅菌消毒することであり,最も信頼性の高い消毒方法は加熱滅菌であり,オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)消毒(水蒸気のある状態で圧力を高くし,121℃の熱で20分),煮沸消毒(15分以上),乾熱滅菌が有効である。以上の加熱滅菌が不可能な場合には薬物消毒の方法を用いる。その際,塩素系の次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度1000ppm,1時間)が多用され,金属材料に対しては,2%のグルタールアルデヒド液,エチレンオキサイドガス,ホルムアルデヒドガス等が用いられる。上記以外の消毒剤については有効性が明らかでなく,日常広く使用されている消毒用アルコール,クレゾール等は消毒効果がない。
ウ B型肝炎ウイルスには,HBs抗原,HBc抗原,HBe抗原の3種類の抗原と,これに対応するHBs抗体,HBc抗体,HBe抗体の3種類の抗体があり,これらにDNAポリメラーゼ等を加えて,B型肝炎ウイルスマーカーと呼ぶ。
B型肝炎ウイルスマーカーの持つ意味は,次のとおりである。
① HBs抗原陽性 B型肝炎ウイルスが肝臓に住み着いてB型肝炎ウイルスに感染している状態にあることを示す。
② HBs抗体陽性 かつてB型肝炎ウイルスに感染したことがあり,現在治癒していることを示す。
③ HBc抗体陽性 高値であれば,B型肝炎ウイルスが肝臓に住み着き,B型肝炎ウイルスに感染している状態にあることを示し,低値であれば,かつてB型肝炎ウイルスに感染したことがあることを示す。
④ HBe抗原陽性 血中のB型肝炎ウイルス量が多く,感染力の高い状態にあることを示す(HBe抗原陽性状態におけるB型肝炎ウイルスの感染力は,血清1ccを1億倍に希釈した後の溶液1ccを注射することによっても感染を起こすことがチンパンジーによる実験で確認された。なお,C型肝炎ウイルスは,1000~1万倍希釈までしか感染力を有しない。)。
⑤ HBe抗体陽性 血中のB型肝炎ウイルスが少なくなり,感染力も低くなった状態を示す。
⑥ DNAポリメラーゼ 陽性であれば,B型肝炎ウイルスが盛んに増殖している状態を示し,HBe抗体陽性の場合でも,ウイルスに感染力があることを意味し,陰性であれば,B型肝炎ウイルスが増殖していない状態にあることを示す。
エ 免疫不全等に陥っていない成人が初めてB型肝炎ウイルスに感染した場合で,B型肝炎ウイルスの侵入が軽微な場合には,身体に変調を来さない不顕性のまま抗体(HBs抗体)が形成されて免疫が成立し,以後再び感染することはなくなるが,B型肝炎ウイルスの侵入が強度な場合には,黄だん等の症状を伴う顕性の急性肝炎又は劇症肝炎となる。顕性の肝炎が治癒した場合には,上記抗体が形成されて免疫が成立し,以後再び感染することはなくなる。なお,成人がB型肝炎ウイルスに感染してから顕性の肝炎を発症するまでの期間は1~6か月である。
乳幼児は,生体の防御機能が未完成であるため,B型肝炎ウイルスに感染してウイルスが肝細胞に侵入しても免疫機能が働かないため,ウイルスが肝臓にとどまったまま感染状態が持続することがあり,持続感染者となる。持続感染者となった場合でも,その後の経過の中でセロコンバージョンが起きれば,以後,肝炎を発症することはほとんどなくなる。しかし,セロコンバージョンが起きないまま成人期(20~30代)に入ると,B型肝炎ウイルスと免疫機能との共存状態が崩れて肝炎を発症することがあり,肝炎が持続すると慢性B型肝炎となり,肝細胞の破壊と再生が長期間継続され,肝硬変又は肝がんへと進行することがある。そして,持続感染者に最もなりやすいのは2,3歳ころまで(最年長で6歳ころまで)で,それ以後は,感染しても一過性の経過をたどることが多い。
オ 現在の我が国におけるB型肝炎ウイルスの持続感染者は,推定で約120万~140万人であるが,感染者の年齢層によって感染者比率に差異があり,40歳代以上の感染者比率は1~2%,30歳代以下の感染者比率は1%未満である。なお,昭和61年からHBe抗原陽性の母親から生まれた子を対象として,公費でワクチン等を使用した母子間感染阻止事業(母子感染の主要な経路は出生時の経胎盤と考えられることから,出生後に新生児に感染防止措置を施すこととしたもの)が開始された結果,昭和61年生まれ以降の世代における新たな持続感染者の発生はほとんどみられなくなった。
(3)B型肝炎に関する知見
B型肝炎ウイルスの発見は,1973年(昭和48年)のことであるが,同一の注射器(針,筒)を連続して使用することなどにより,非経口的に人の血清が人体内に入り込むと肝炎が引き起こされることがあること,それが人の血清内に存在するウイルスによるものであることは,我が国の内外において,1930年代後半から1940年代前半にかけて広く知られるようになっていた。そして,欧米諸国においては,遅くとも,1948年(昭和23年)には,血清肝炎が人間の血液内に存在するウイルスにより感染する病気であること,感染しても黄だんを発症しない持続感染者が存在すること,注射をする際,注射針のみならず注射筒を連続使用する場合にもウイルスが感染する危険があることについて,医学的知見が確立していた。また,我が国においても,遅くとも昭和26年当時には,血清肝炎が人間の血液内に存在するウイルスにより感染する病気であり,黄だんを発症しない保菌者が存在すること,そして,注射の際に,注射針のみならず注射筒を連続使用した場合にもウイルス感染が生ずる危険性があることについて医学的知見が形成されていた。
(4)我が国における予防接種の経緯
我が国では,予防接種法(昭和23年7月1日施行),結核予防法(昭和26年4月1日施行)等に基づき,集団予防接種等が実施されてきた。平成16年(受)第672号被上告人・同年(受)第673号上告人(第1審被告)国(以下「被告」という。)は,昭和23年厚生省告示第95号において,注射針の消毒は必ず被接種者1人ごとに行わなければならないことを定め,昭和25年厚生省告示第39号において,1人ごとの注射針の取替えを定めたが,我が国において上記医学的知見が形成された昭和26年以降も,集団予防接種等の実施機関に対して,注射器(針,筒)の1人ごとの交換又は徹底した消毒の励行等を指導せず,注射器の連続使用の実態を放置していた。
そして,原告らが集団予防接種等を受けた北海道内では,昭和44,45年ころ以降においては,集団BCG接種については管針法(接種部位の皮膚を緊張させ,懸濁液を塗った後,9本針植付けの管針を接種皮膚面に対してほぼ垂直に保ち,これを強く圧して行うもの)による1人1管針の方法が大勢を占めていたが,集団ツベルクリン反応検査については,注射針,注射筒とも連続使用され,その他の集団予防接種については,注射針は1人ごとに取り替えられたものの,注射筒,種痘針等は連続使用され,そのころ以前にされた集団予防接種等については,注射針,注射筒,種痘における種痘針,乱刺針とも,1人ごとに取り替えられずに連続使用された。また,原告X3が集団予防接種等を受けた際においては,集団BCG接種では1人ごとに管針が取り替えられたが,集団ツベルクリン反応検査では注射針が1人ごとに取り替えられたものの,同検査における注射筒については連続使用された。
2 本件は,B型肝炎ウイルスに感染した原告らが,被告に対し,上記1(1)の各集団予防接種等(ただし,原告X3に対するBCG接種を除く。いずれも各原告が6歳までに接種等を受けたものであり,以下,これらを併せて「本件集団予防接種等」という。)によってB型肝炎ウイルスに感染し,さらに,原告X3を除く原告ら(以下,この4名を「X3を除く原告ら」という。)は,B型肝炎を発症して肉体的・精神的・社会的・経済的損害を被ったなどと主張し,国家賠償法1条1項に基づき,各1150万円及びこれに対する平成元年7月12日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。
3 原審は,前記事実関係の下,次のとおり判断して,原告X1,同X2及び同X3の各請求を各550万円及びうち500万円に対する平成元年7月12日から,うち50万円に対する判決確定の日の翌日からそれぞれ年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却し,原告X4及び同X5の各請求を全部棄却すべきものとした。
(1)本件においては,原告らのB型肝炎ウイルス感染の原因が本件集団予防接種等であると認め得る直接証拠は見当たらず,また,疫学的な因果の連鎖を的確に示す客観的な事実を認め得る間接証拠も見当たらない。しかし,①X3を除く原告らがB型肝炎ウイルスに感染したのは,それぞれが本件集団予防接種等を受けた時期に対応する乳児期から小児期(6歳ころ)までであり,本件集団予防接種等とB型肝炎ウイルスの感染との間には,いずれの集団予防接種等に対応するのか具体的に特定できないものの,大枠ではあるが,疫学的観点からの時間的関係において因果関係を認め得る事実関係にあること,また,原告X3がB型肝炎ウイルスに感染したのは,生後11か月の期間(昭和58年▲月▲日~昭和59年4月22日)であり,同原告はこの間に集団ツベルクリン反応検査を受けていること,②上記1(2)~(4)に記載したようなB型肝炎ウイルスの感染の機序,これに関する知見及び本件集団予防接種等における注射針,注射筒等の使用方法によれば,本件集団予防接種等がいずれも通常人においてB型肝炎ウイルス感染の危険性を覚えることを客観的に排除し得ない状況で実施されたこと,③原告らのB型肝炎ウイルス感染の原因として考えられる他の具体的な原因が見当たらないことに照らすと,本件集団予防接種等と原告らのB型肝炎ウイルス感染との間の因果関係を肯定するのが相当である。
(2)我が国において,遅くとも昭和26年当時には,血清肝炎が人間の血液内に存在するウイルスにより感染する病気であり,黄だんを発症しない保菌者が存在すること,注射の際に,注射針のみならず注射筒を連続使用した場合にもウイルス感染が生じる危険性があることについて,医学的知見が形成されていたから,被告においては,遅くとも,原告X4が最初に集団ツベルクリン反応検査を受けた昭和26年当時には,集団予防接種等の際,注射針,注射筒を連続して使用するならば,被接種者間に血清肝炎ウイルスが感染するおそれがあることを当然に予見できたと認めるのが相当である。したがって,その当時,被告は,集団予防接種等において注射器の針を交換しない場合はもちろんのこと,針を交換しても肝炎ウイルスが感染する可能性があったことを認識し,又は認識することが十分に可能であり,本件集団予防接種等を実施するに当たっては,注射器(針,筒)の1人ごとの交換又は徹底した消毒の励行等を各実施機関に指導してB型肝炎ウイルス感染を未然に防止すべき義務があったにもかかわらず,これを怠った過失がある。
(3)本件集団予防接種等は,被告の伝染病予防行政の重要な施策として,被告からの細部にまでわたる指導に基づいて,各自治体により実施されたことが明らかであり,本件集団予防接種等が強制接種であったか勧奨接種であったかにかかわらず,被告の伝染病予防行政上の公権力の行使に当たるから,被告は,本件集団予防接種等によって生じた損害について,国家賠償法1条1項に基づく賠償責任を負う。
(4)原告らに対する慰謝料として各500万円を認めるのが相当であり,弁護士費用に係る損害として各50万円を認めるのが相当である。なお,原告らの請求に係る弁護士費用については,本件請求における認容額を基準として将来において支払われるべきものとする合意がされているから,弁護士費用に係る損害に対し判決確定以前にさかのぼって遅延損害金を付すのは相当でない。
(5)民法724条後段は,期間20年間の除斥期間を定めたものと解される。X3を除く原告らについては,B型肝炎ウイルスに感染した接種行為を特定することはできないところ,本件のようにいずれも乳幼児期に接種され,かつ,その最初から最後までのいずれについても感染の可能性が肯定され得る場合には,その最後の接種の時を除斥期間の始期とするのが相当である。そして,原告X1に対する最後の集団予防接種は昭和46年2月5日,同X4に対するそれは昭和33年3月12日,同X5に対するそれは昭和42年10月26日,同X2に対するそれは昭和45年2月4日であるから,同X1及び同X2の損害賠償請求権については,本件訴えの提起時(平成元年6月30日)には除斥期間が経過していないが,同X4及び同X5の損害賠償請求権については,除斥期間が経過していた。
第2 平成16年(受)第673号上告代理人都築弘ほかの上告受理申立て理由
第2及び第3について
1 所論は,原告X1,同X2及び同X3(以下,この3名を「原告X1ら」という。)が本件集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染したものと認定した原審の判断について,経験則違反及び加害行為の特定を欠く法令違反がある旨をいうものである。
2 訴訟上の因果関係の立証は,一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく,経験則に照らして全証拠を総合検討し,特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性を証明することであり,その判定は,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを必要とし,かつ,それで足りるものと解すべきである(最高裁昭和48年(オ)第517号同50年10月24日第二小法廷判決・民集29巻9号1417頁参照)。
前記事実関係によれば,① B型肝炎ウイルスは,血液を介して人から人に感染するものであり,その感染力の強さに照らし,集団予防接種等の被接種者の中に感染者が存在した場合,注射器の連続使用によって感染する危険性があること,② 原告X1らは,最も持続感染者になりやすいとされる0~3歳時を含む6歳までの幼少期に本件集団予防接種等を受け,それらの集団予防接種等において注射器の連続使用がされたこと,③ 原告X1らは,その幼少期にB型肝炎ウイルスに感染して持続感染者となり,うち原告X1及び同X2は,成人期に入ってB型肝炎を発症したことが認められる。また,前記事実関係によれば,原告X1らの母親が原告X1らを出産した時点でHBe抗原陽性の持続感染者であったものとは認められないから,原告X1らは,母子間の垂直感染(出産時にB型肝炎ウイルスの持続感染者である母親の血液が子の体内に入ることによる感染。以下において,「垂直感染」の語は,この意味で用いる。)により感染したものではなく,それ以外の感染,すなわち,水平感染によるものと認められる。さらに,前記事実関係によれば,昭和61年から母子間感染阻止事業が開始された結果,同年生まれ以降の世代における新たな持続感染者の発生がほとんどみられなくなったことが認められるところ,この事実は,それ以前において,母子間の垂直感染による持続感染者が相当数存在したことを示すものであり,原告X1らが本件集団予防接種等を受けた時期に,集団予防接種等の被接種者の中にこうした垂直感染による持続感染者が相当数紛れ込んでいたことを示すものということができる(現に,原審の確定するところによれば,原告X3と同日に同一の保健所で集団ツベルクリン反応検査を受けた者を追跡調査したところ,被接種者の中にその母が持続感染者である者が見付かっている。)。そして,昭和61年以降垂直感染を阻止することにより同年生まれ以降の世代における持続感染者の発生がほとんどみられなくなったということは,同年生まれ以降の世代については,母子間感染阻止事業の対象とされた垂直感染による持続感染者の発生がほとんどなくなったというだけでなく,母親が持続感染者でないのに感染した原告らのような水平感染による持続感染者の発生もほとんどなくなったということを意味し,少なくとも,幼少児については,垂直感染を阻止することにより同世代の幼少児の水平感染も防ぐことができたことを意味する。前記のとおり,母子間感染阻止事業は,B型肝炎ウイルスの持続感染者である母親から出生した子に対し,出生時において感染防止措置を施すものであり,同事業の開始後も,そのような措置を施されなかった幼少児が多数存在するとともに,家庭内を含めて幼少児の生活圏内には相当数の持続感染者が存在していたと推認されることにかんがみれば,幼少児について,垂直感染を阻止することにより水平感染も防ぐことができたということは,一般に,幼少児については,集団予防接種等における注射器の連続使用によるもの以外は,家庭内感染を含む水平感染の可能性が極めて低かったことを示すものということもできる。以上の事実に加え,本件において,原告X1らについて,本件集団予防接種等のほかには感染の原因となる可能性の高い具体的な事実の存在はうかがわれず,他の原因による感染の可能性は,一般的,抽象的なものにすぎないこと(原告X1らの家族の中には,過去にB型肝炎ウイルスに感染した者が存在するけれども,家族から感染した可能性が高いことを示す具体的な事実の存在はうかがわれない。)などを総合すると,原告X1らは,本件集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染した蓋然性が高いというべきであり,経験則上,本件集団予防接種等と原告X1らの感染との間の因果関係を肯定するのが相当である。これと同旨の原審の判断は正当として是認することができる。なお,原告X1及び同X2は,複数の集団予防接種等を受けているところ,原審は,そのいずれによってB型肝炎ウイルスに感染したのかを特定していないが,前記第1の3のとおり,その集団予防接種等のいずれについても,被告が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在することを認めているのであるから,被告が賠償責任を負う理由として欠けるところはない。論旨はいずれも採用できない。
第3 平成16年(受)第672号上告代理人佐藤太勝ほかの上告受理申立て理由について
1 所論は,原告X4及び同X5についても,除斥期間は経過していない旨をいうものである。
2 民法724条後段所定の除斥期間の起算点は,「不法行為の時」と規定されており,加害行為が行われた時に損害が発生する不法行為の場合には,加害行為の時がその起算点となると考えられる。しかし,身体に蓄積する物質が原因で人の健康が害されることによる損害や,一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病による損害のように,当該不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると解すべきである(最高裁平成13年(受)第1760号同16年4月27日第三小法廷判決・民集58巻4号1032頁,最高裁平成13年(オ)第1194号,第1196号,同年(受)第1172号,第1174号同16年10月15日第二小法廷判決・民集58巻7号1802頁参照)。
上記見解に立って本件をみると,前記事実関係によれば,① 乳幼児期にB型肝炎ウイルスに感染し,持続感染者となった場合,セロコンバージョンが起きることなく成人期(20~30代)に入ると,肝炎を発症することがあること,② 原告X4は,昭和26年5月生まれで,同年9月~昭和33年3月に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染し,昭和59年8月ころ,B型肝炎と診断されたこと,③ 原告X5は,昭和36年7月生まれで,昭和37年1月~昭和42年10月に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染し,昭和61年10月,B型肝炎と診断されたことが認められる。そうすると,B型肝炎を発症したことによる損害は,その損害の性質上,加害行為が終了してから相当期間が経過した後に発生するものと認められるから,除斥期間の起算点は,加害行為(本件集団予防接種等)の時ではなく,損害の発生(B型肝炎の発症)の時というべきである。
したがって,原告X4につき昭和33年3月から,同X5につき昭和42年10月から除斥期間を計算し,本件訴えの提起時(平成元年6月30日)には除斥期間の経過によって同原告らの損害賠償請求権が消滅していたとした原審の判断には,民法724条後段の解釈適用を誤った違法がある。そして,前記事実関係によれば,原告X4がB型肝炎を発症したのは昭和59年8月ころであり,同X5が発症したのは昭和61年10月ころであるとみるべきであるから,本件訴えの提起時には,いずれも除斥期間が経過していなかった。
以上によれば,原告X4及び同X5の各請求を全部棄却すべきものとした原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決のうち原告X4及び同X5に関する部分は,破棄を免れない。
3 そこで,更に検討するに,原審は,前記第1の3のとおり,原告X4についても,同X5についても,本件集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染したものと認定し,被告がこれにつき法律上賠償の責任を負うべき関係が存在することを認めた上,上記原告らの損害を各550万円と算定しているのであるから,同原告らの請求を各550万円及びうち500万円に対する平成元年7月12日から,うち50万円に対する本判決確定の日の翌日からそれぞれ遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却すべきである。
第4 平成16年(受)第673号上告代理人都築弘ほかの上告受理申立て理由第4について
1 所論は,原告X1及び同X2について,除斥期間が経過している旨をいうものである。
2 しかしながら,前記事実関係によれば,原告X1がB型肝炎を発症したのは昭和61年10月ころであり,同X2が発症したのは昭和60年3月ころであるとみるべきであるから,本件訴えの提起時には,いずれも除斥期間が経過していなかったことが明らかである。これと結論において同旨の原判決は正当として是認することができる。論旨は採用できない。
第5 結論
以上によれば,原告X4及び同X5の上告に基づき,原判決及び第1審判決のうち同原告らに関する部分を変更し,同原告らの請求をいずれも550万円とその遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却し,被告の上告は,これを棄却すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁判所裁判長裁判官中川了滋,裁判官滝井繁男,同津野修,同今井功,同古田佑紀
不法行為が原因で心神喪失した被害者と民法724条後段の除斥期間(最判平成10年6月12日民集52巻4号1087頁)
不法行為が原因で心神喪失した被害者と民法724条後段の除斥期間
主 文
原判決中,上告人Aの国家賠償法に基づく損害賠償請求に関する部分を破棄する。
前項の部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。
上告人B及び同Cの上告を棄却する。
前項に関する上告費用は上告人B及び同Cの負担とする。
理 由
上告代理人中平健吉,同大野正男,同廣田富男,同山川洋一郎,同秋山幹男,同河野敬の上告理由について
一 本件訴訟において,予防接種法(昭和二八年法律第二一三号による改正前のもの)に基づいて実施された痘そうの予防接種により重度の心身障害者となった上告人αは,その両親である上告人β及び同γと共に,被上告人に対し,国家賠償法に基づく損害賠償(以下「国家賠償」という。)を求めている。原審の確定した事実関係の概要及び記録上明らかな本件訴訟の経過は,次のとおりである。
1 上告人αは,昭和二七年五月一九日,出生し,同年一〇月二〇日,呉市保健所において,予防接種法(昭和二八年法律第二一三号による改正前のもの)五条,一〇条一項一号に基づき呉市長が実施した痘そうの集団接種(以下「本件接種」という。)を受けた。ところが,上告人αは,同月二七日から,けいれん,発熱を発症し,以後,けいれんが止まらず,通常ならば直立や歩行ができる時期に至っても,これができない状態となった。
2 上告人αは,昭和三五年一月ころには,座ったり,身体を転がして移動することができるようになり,また,わずかに歩けるようになった時期もあったが,その後,高度の精神障害,知能障害,運動障害及び頻繁なけいれん発作を伴う寝たきりの状態となっている。
3 上告人αの同1及び2の症状は,本件接種を原因とするものである。
4 上告人らは,昭和四九年一二月五日,本件訴訟を提起した。なお,上告人αについては,同人が既に成年に達していたにもかかわらず,上告人β及び同γが同αの親権者と称して弁護士中平健吉外五名(以下「中平弁護士ら」という。)に本件訴訟の提起ないし追行を委任し,同弁護士らによって第一審の訴訟手続が追行された。
5 上告人αは,第一審判決の言渡しの後である昭和五九年一〇月一九日,禁治産宣告を受け,上告人βが後見人に就職した。上告人βは,上告人αの後見人として,改めて中平弁護士らに本件訴訟の追行を委任し,同年一一月一日,原審にその旨の訴訟委任状を提出し,同弁護士らは,以降の訴訟手続を追行した。
二 原審は,同事実関係の下において,上告人らの国家賠償請求について次のように判示して,第一審判決のうち上告人らの請求を一部認容した部分を取り消し,上告人らの請求をいずれも棄却した。
1 上告人らの本件訴訟の提起は,不法行為の時から二〇年を経過した後にされたことが明らかであり,上告人らの損害賠償請求権は,既に本件訴訟提起前の同二〇年の期間が経過した時点で法律上当然に消滅した。
2 民法七二四条後段の規定は損害賠償請求権の除斥期間を定めたものであるから,当事者からの主張がなくても,除斥期間の経過により同請求権が消滅したものと判断すべきであり,除斥期間の主張が信義則違反又は権利濫用であるという上告人らの主張は,主張自体失当である。
3 一定の時の経過によって法律関係を確定させるため,被害者側の事情等は特に顧慮することなく,請求権の存続期間を画一的に定めるという除斥期間の趣旨からすると,本件で訴えの提起が遅れたことにつき被害者側にやむを得ない事情があったとしても,本件で除斥期間の経過を認定することが正義と公平に著しく反する結果をもたらすということはできない。
三 上告人らの国家賠償請求に関する原審の同判断のうち,上告人β及び同γの請求を棄却した部分は是認できるが,同αの請求を棄却した部分は是認できない。その理由は,次のとおりである。
1 民法七二四条後段の規定は,不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものであり,不法行為による損害賠償を求める訴えが除斥期間の経過後に提起された場合には,裁判所は,当事者からの主張がなくても,除斥期間の経過により同請求権が消滅したものと判断すべきであるから,除斥期間の主張が信義則違反又は権利濫用であるという主張は,主張自体失当であると解すべきである(最高裁昭和五九年(オ)第一四七七号平成元年一二月二一日判決・民集四三巻一二号二二〇九頁参照)。
2 ところで,民法一五八条は,時効の期間満了前六箇月内において未成年者又は禁治産者が法定代理人を有しなかったときは,その者が能力者となり又は法定代理人が就職した時から六箇月内は時効は完成しない旨を規定しているところ,その趣旨は,無能力者は法定代理人を有しない場合には時効中断の措置を執ることができないのであるから,無能力者が法定代理人を有しないにもかかわらず時効の完成を認めるのは無能力者に酷であるとして,これを保護するところにあると解される。
これに対し,民法七二四条後段の規定の趣旨は,前記のとおりであるから,同規定を字義どおりに解すれば,不法行為の被害者が不法行為の時から二〇年を経過する前六箇月内において心神喪失の常況にあるのに後見人を有しない場合には,同二〇年が経過する前に同不法行為による損害賠償請求権を行使することができないまま,同請求権が消滅することとなる。
しかし,これによれば,その心神喪失の常況が当該不法行為に起因する場合であっても,被害者は,およそ権利行使が不可能であるのに,単に二〇年が経過したということのみをもって一切の権利行使が許されないこととなる反面,心神喪失の原因を与えた加害者は,二〇年の経過によって損害賠償義務を免れる結果となり,著しく正義・公平の理念に反するものといわざるを得ない。そうすると,少なくともこのような場合にあっては,当該被害者を保護する必要があることは,前記時効の場合と同様であり,その限度で民法七二四条後段の効果を制限することは条理にもかなうというべきである。
従って,不法行為の被害者が不法行為の時から二〇年を経過する前六箇月内において同不法行為を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合において,その後当該被害者が禁治産宣告を受け,後見人に就職した者がその時から六箇月内に同損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは,民法一五八条の法意に照らし,同法七二四条後段の効果は生じないものと解するのが相当である。
3 これを本件についてみると,原審の確定した事実は,上告人αは,本件接種の七日後にけいれん等を発症し,その後,高度の精神障害,知能障害等を有する状態にあり,かつ,この各症状はいずれも本件接種を原因とするものであったというのであるから,不法行為の時から二〇年を経過する前六箇月内においても,本件接種を原因とする心神喪失の常況にあったというべきである。そして,本件訴訟が提起された後,上告人αが昭和五九年一〇月一九日に禁治産宣告を受け,その後見人に就職した上告人βが,中平弁護士らに本件の訴訟委任をし,同年一一月一日にその旨の訴訟委任状を原審に提出することによって,上告人αの本件損害賠償請求権を行使したのであるから,本件においては前記特段の事情があるものというべきであり,民法七二四条後段の規定にかかわらず,同損害賠償請求権が消滅したということはできない。
そうすると,これと異なる見解に立ち,上告人αの国家賠償請求にっき,同請求権は本件訴訟が提起される前に既に消滅したとしてこれを棄却した原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法があり,この違法は,原判決のうち同請求に関する部分の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決はこの限度で破棄を免れない。
4 他方,上告人β及び同γについては,原審の適法に確定した事実関係の下においては,何ら除斥期間の適用を妨げる事情は認められないから,同人らの国家賠償請求につき,同請求権は本件訴訟が提起される前に既に消滅したものであるとしてこれらをいずれも棄却した原審の判断は,正当として是認できる。同部分に関する論旨は,採用できない。
四 以上の次第であるから,原判決中,上告人αの国家賠償請求に関する部分を破棄し,更に審理を尽くさせるため同部分につき本件を原審に差し戻すこととし,上告人β及び同γの本件上告は棄却する。
よって,上告人αの上告について裁判官河合伸一の意見,上告人β及び同γの上告について同裁判官の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
裁判官河合伸一の意見及び反対意見(略)
最高裁裁判長裁判官福田博,裁判官大西勝也,同根岸重治,同河合伸一
除斥期間(最判平成21年4月28日民集63巻4号853頁 )
被害者を殺害した加害者が,死亡の事実を相続人が知り得ない状況を殊更に作出したため相続人が知り得なかった場合の上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権と民法724条後段の除斥期間
上告代理人秋山賢三,同今村核の上告受理申立て理由について
1 本件は,殺人事件の被害者の有していた権利義務を相続した被上告人らが,加害者である上告人に対して,不法行為に基づく損害賠償を請求する事案であり,不法行為から20年が経過したことによって,民法724条後段の規定に基づき損害賠償請求権が消滅したか否かが争われている。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) αは,足立区立α小学校(以下「本件小学校」という。)に図工教諭として勤務していた者であり,上告人は,本件小学校に学校警備主事として勤務していた者である。
(2) 上告人は,昭和53年8月14日,本件小学校内においてαを殺害し(以下「本件殺害行為」という。),その死体を同月16日までに上告人の自宅の床下に掘った穴に埋めて隠匿した。
(3) αの両親であるβ及びγは,αの行方が分からなくなったため,警察に捜索願を出し,本件小学校の教職員らと共に校内やαの住んでいたアパートの周辺を捜すなどしたが,手掛かりをつかむことができなかった。
(4) βは,昭和57年▲月▲日に死亡し,γ及び被上告人ら(いずれもβとγの間の子であり,αの弟である。)が,その権利義務を相続した。
(5) 上告人は,本件殺害行為の発覚を防ぐため,自宅の周囲をブロック塀,アルミ製の目隠し等で囲んで内部の様子を外部から容易にうかがうことができないようにし,かつ,サーチライトや赤外線防犯カメラを設置するなどした。
(6) 上告人の自宅を含む土地は,平成6年ころ,土地区画整理事業の施行地区となった。上告人は,当初は自宅の明渡しを拒否していたが,最終的には明渡しを余儀なくされたため,死体が発見されることは避けられないと思い,本件殺害行為から約26年後の平成16年8月21日に,警察署に自首した。
(7) 上告人の自宅の捜索により床下の地中から白骨化した死体が発見され,丁泗α鑑定の結果,平成16年9月29日,それがαの死体であることが確認された。これにより,γ及び被上告人らは,αの死亡を知った。
(8) γ及び被上告人らは,平成17年4月11日,本件訴えを提起した。
(9) γは平成19年▲月▲日に死亡し,被上告人らがその権利義務を相続した。
3 民法724条後段の規定は,不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものであり,不法行為による損害賠償を求める訴えが除斥期間の経過後に提起された場合には,裁判所は,当事者からの主張がなくても,除斥期間の経過により上記請求権が消滅したものと判断すべきである(最高裁昭和59年(オ)第1477号平成元年12月21日判決・民集43巻12号2209頁参照)。
ところで,民法160条は,相続財産に関しては相続人が確定した時等から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない旨を規定しているが,その趣旨は,相続人が確定しないことにより権利者が時効中断の機会を逸し,時効完成の不利益を受けることを防ぐことにあると解され,相続人が確定する前に時効期間が経過した場合にも,相続人が確定した時から6か月を経過するまでの間は,時効は完成しない(最高裁昭和35年(オ)第348号同年9月2日判決・民集14巻11号2094頁参照)。そして,相続人が被相続人の死亡の事実を知らない場合は,同法915条1項所定のいわゆる熟慮期間が経過しないから,相続人は確定しない。
これに対し,民法724条後段の規定を字義どおりに解すれば,不法行為により被害者が死亡したが,その相続人が被害者の死亡の事実を知らずに不法行為から20年が経過した場合は,相続人が不法行為に基づく損害賠償請求権を行使する機会がないまま,同請求権は除斥期間により消滅することとなる。しかし,被害者を殺害した加害者が,被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出し,そのために相続人はその事実を知ることができず,相続人が確定しないまま除斥期間が経過した場合にも,相続人は一切の権利行使をすることが許されず,相続人が確定しないことの原因を作った加害者は損害賠償義務を免れるということは,著しく正義・公平の理念に反する。このような場合に相続人を保護する必要があることは,前記の時効の場合と同様であり,その限度で民法724条後段の効果を制限することは,条理にもかなうというべきである(最高裁平成5年(オ)第708号同10年6月12日判決・民集52巻4号1087頁参照)。
そうすると,被害者を殺害した加害者が,被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出し,そのために相続人はその事実を知ることができず,相続人が確定しないまま上記殺害の時から20年が経過した場合において,その後相続人が確定した時から6か月内に相続人が上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは,民法160条の法意に照らし,同法724条後段の効果は生じないものと解するのが相当である。
4 これを本件についてみるに,前記事実関係によれば,上告人が本件殺害行為後にαの死体を自宅の床下に掘った穴に埋めて隠匿するなどしたため,β,γ及び被上告人らはαの死亡の事実を知ることができず,相続人が確定せず損害賠償請求権を行使する機会がないまま本件殺害行為から20年が経過したというのである。
そして,γ及び被上告人らは,平成16年9月29日にαの死亡を知り,それから3か月内に限定承認又は相続の放棄をしなかったことによって単純承認をしたものとみなされ(民法915条1項,921条2号),これにより相続人が確定したところ,更にそれから6か月内である平成17年4月11日に本件訴えを提起したというのであるから,本件においては前記特段の事情があるものというべきであり,民法724条後段の規定にかかわらず,本件殺害行為に係る損害賠償請求権が消滅したということはできない。
5 以上と同旨の原審の判断は,正当として是認できる。論旨は採用できない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。(なお,裁判官田原睦夫の意見は略)
最高裁裁判長裁判官那須弘平,裁判官藤田宙靖,同堀籠幸男,同田原睦夫,同近藤崇晴
消滅時効(最判昭和42年7月18日民集21巻6号1559頁 )
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効が進行しないとされた事例
上告代理人石島泰,同鶴見祐策の上告理由第一点について。
一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合には,訴訟物は,右債権の一部の存否のみであって全部の存否ではなく,従って,右一部の請求についての確定判決の既判力は残部の請求に及ばないと解するのが相当である(当裁判所昭和三五年(オ)第三五九号,同三七年八月一〇日言渡判決,民集一六巻八号一七二〇頁参照)。ところで,記録によれば,所論の前訴(東京地方裁判所昭和三一年(ワ)第九五〇四号,東京高等裁判所同三三年(ネ)第二五五九号,第二六二三号)における被上告人の請求は,被上告人主張の本件不法行為により惹起された損害のうち,右前訴の最終口頭弁論期日たる同三五年五月二五日までに支出された治療費を損害として主張しその賠償を求めるものであるところ,本件訴訟における被上告人の請求は,前記の口頭弁論期日後にその主張のような経緯で再手術を受けることを余儀なくされるにいたったと主張し,右治療に要した費用を損害としてその賠償を請求するものであることが明らかである。右の事実によれば,所論の前訴と本件訴訟とはそれぞれ訴訟物を異にするから,前訴の確定判決の既判力は本件訴訟に及ばないというべきであり,原判決に所論の違法は存しない。所論は,独自の見解に基づき原判決を非難するものであって,採用できない。
同第二,三点について。
原審の確定するところによれば,本件不法行為により被上告人が受傷した後における治療の経過は原判示のとおりであり,被上告人の右受傷による後遺症である右足の内反足に対し甲医師のなした本件植皮手術が果して効果のある治療方法であるかどうかは,被上告人の受傷当時は勿論,その後内反足の症状が現われた後においても,医学的には必ずしも異論がなかったわけではないというのである。ところで,被害者が不法行為に基づく損害の発生を知った以上,その損害と牽連一体をなす損害であって当時においてその発生を予見することが可能であったものについては,すべて被害者においてその認識があったものとして,民法724条所定の時効は前記損害の発生を知った時から進行を始めるものと解すべきではあるが,本件の場合のように,受傷時から相当期間経過後に原判示の経緯で前記の後遺症が現われ,そのため受傷時においては医学的にも通常予想しえなかったような治療方法が必要とされ,右治療のため費用を支出することを余儀なくされるにいたった等,原審認定の事実関係のもとにおいては,後日その治療を受けるようになるまでは,右治療に要した費用すなわち損害については,同条所定の時効は進行しないものと解するのが相当である。けだし,このように解しなければ,被害者としては,たとい不法行為による受傷の事実を知ったとしても,当時においては未だ必要性の判明しない治療のための費用について,これを損害としてその賠償を請求するに由なく,ために損害賠償請求権の行使が事実上不可能なうちにその消滅時効が開始することとなって,時効の起算点に関する特則である民法724条を設けた趣旨に反する結果を招来するにいたるからである。
このような見地に立って本件を見れば,原審が,その認定した事実関係に基づき,前記の趣旨のもとに上告人主張の消滅時効は未だ完成していないと判断したのは正当であり,原判決に所論の違法は存しない。所論の実質は,ひっきよう,原審の認定にそわない事実を前提とし,独自の見解に基づき原審の前記判断を非難するものであって,採用できない。なお,記録によれば,本件植皮手術による治療費支払債務の弁済ないし右債務の負担による損害が被害者たる被上告人以外の者に生じたとする所論については,原審においてその主張立証がなされていないから,この点に関する所論も採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官横田正俊,裁判官柏原語六,同田中二郎,同下村三郎
民法724条「加害者ヲ知リタル時」(最判昭和48年11月16日民集27巻10号1374頁)
民法724条にいう「加害者ヲ知リタル時」
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人山下義則の上告理由第一点について。
民法七二四条にいう「加害者ヲ知リタル時」とは,同条で時効の起算点に関する特則を設けた趣旨に鑑みれば,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに,その可能な程度にこれを知った時を意味するものと解するのが相当であり,被害者が不法行為の当時加害者の住所氏名を的確に知らず,しかも当時の状況においてこれに対する賠償請求権を行使することが事実上不可能な場合においては,その状況が止み,被害者が加害者の住所氏名を確認したとき,初めて「加害者ヲ知リタル時」にあたる。
これを本件についてみるに,原審の確定したところによれば,被上告人は,昭和一七年初め頃軍機保護法違反の容疑で逮捕され,大泊警察署に留置されて取調中,同年四月一五日夜から翌一六日未明にかけて本件不法行為による被害を受けたが,その当時加害者である上告人が「α」なる姓の同署警部補であること及びその容貌を知ってはいたものの,その「α」の名と住所は知らず,逮捕後引き続き身柄拘束のまま取調,起訴,有罪の裁判及びその執行を受け,昭和二〇年九月四日頃終戦後の混乱の収まらない状況の中においてようやく釈放されたものであって,その釈放前は勿論釈放後も,加害者である上告人の所在及び名を知ることが困難であったところ,その後加害者の探索に努めた結果,昭和二三年頃に至り加害者が秋田県内に居るらしいことを,また昭和二六年頃その名が「α」なることを知るに至り,札幌法務局人権擁護部に照会して,昭和三六年一一月八日頃,上告人が秋田県本荘市から東京に移転したとの回答を受けたので,更に調査の結果,その頃東京における住所を突きとめ,加害者本人に間違いないことを知ったというのであって,被上告人は,この時に加害者を知ったものというべく,それから三年以内である昭和三七年三月七日に本訴を提起したものであるから,上告人主張の消滅時効は未だ完成していないとした原審の判断は,正当である。原判決に所論の違法はなく,論旨は,採用できない。
同第二点について。
所論の点に関する原審の認定は,原判決挙示の証拠に照らし首肯することができないわけではなく,その過程に所論の違法は認められない。論旨は,畢竟,原審の専権に属する証拠の取捨判断,事実の認定を非難するにすぎず,採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官大塚喜一郎,裁判官岡原昌男,同小川信雄,同吉田豊
後遺症の顕在化と消滅時効の進行成(最判昭和49年9月26日裁判集民事112号709頁)
上告人の交通事故による損害賠償請求事件について,事故による後遺症が顕在化した時点で,損害の発生を予見し,賠償請求することが社会通念上可能であったと言え,消滅時効が完成している事例
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人松本健男,同酉川雅偉の上告理由について。
不法行為の被害者につきその不法行為によって受傷した時から相当の期間経過後に右受傷に基因する後遺症が現われた場合には,右後遺症が顕在化した時が民法七二四条にいう損害を知った時にあたり,後遺症に基づく損害であって,その当時において発生を予見することが社会通念上可能であったものについては,すべて被害者においてその認識があったものとして,当該損害の賠償請求権の消滅時効はその時から進行を始めると解するのが相当である(最高裁昭和四〇年(オ)第一二三二号同四二年七月一八日第三小法廷判決・民集二一巻六号一五五九頁参照)。このような見地に立って本件を見るに,原審の確定するところによれば,本件交通事故により上告人が受傷したのちにおける治療の経過は原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の説示するとおりであって,上告人の右受傷による所論の後遺症は遅くとも昭和四一年二月一二日より以前に顕在化し,その後において症状は徐々に軽快こそすれ,悪化したとは認められないというのであるから,上告人としては右の時点で所論の後遺症に基づく本件逸失利益及び精神的苦痛の損害の発生を予見し,その賠償を請求することが社会通念上可能であったものというべく,したがって,原審が右認定にかかる事実関係に基づき,本件損害賠償請求権の消滅時効は遅くとも前記昭和四一年二月一二日にはその進行を始め,本訴が提起された昭和四四年二月一二日までに右消滅時効が完成していると判断したのは正当であり,原判決に所論の違法はない。論旨は採用できない。
よって,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官大隅健一郎,裁判官藤林益三,同下田武三,同岸盛一,同岸上康夫
明示の一部請求と時効中断範囲(最判昭和34年2月20日民集13巻2号209頁)
債権の一部についてのみ判決を求める旨明示した訴の提起と消滅時効中断の範囲
主 文
原判決中,同判決末尾添付の別紙第二欄記載の各金員及びこれに対する昭和二七年一二月一〇日から完済まで年五分の割合による金員の支払を命じた部分を破棄し,右部分につき本件を東京高等裁判所に差戻す。
本件その余の上告を棄却する。
被上告人らは,上告人に対し,それぞれ本判決末尾添付の別紙目録該当欄記載の各金員を返還し且つこれに対する昭和三一年三月二九日から返還済まで年五分の割合による金員を支払え。
本判決第二項の部分に関する上告費用は上告人の負担とし,前項の裁判に関する費用は被上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人鈴木於用の上告理由並びに民訴第一九八条第二項の裁判を求める申立の趣旨及び理由は,いずれも本判決末尾添付の別紙(一)(二)(三)記載のとおりである。
右上告理由第一点について。
裁判上の請求による時効の中断が,請求のあった範囲においてのみその効力を生ずべきことは,裁判外の請求による場合と何等異るところはない。そして,裁判上の請求があったというためには,単にその権利が訴訟において主張されたというだけでは足りず,いわゆる訴訟物となったことを要するものであって,民法一四九条,同一五七条二項,民訴二三五条等の諸規定はすべてこのことを前提としているものと解すべきである。
ところで,一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合,原告が裁判所に対し主文において判断すべきことを求めているのは債権の一部の存否であって全部の存否でないことが明らかであるから,訴訟物となるのは右債権の一部であって全部ではない。
それ故,債権の一部についてのみ判決を求める旨明示した訴の提起があった場合,訴提起による消滅時効中断の効力は,その一部の範囲においてのみ生じ,その後時効完成前残部につき請求を拡張すれば,残部についての時効は,拡張の書面を裁判所に提出したとき中断するものと解すべきである。(民訴二三五条参照)若し,これに反し,かかる場合訴提起と共に債権全部につき時効の中断を生ずるとの見解をとるときは,訴提起当時原告自身裁判上請求しない旨明示している残部についてまで訴提起当時時効が中断したと認めることになるのであって,このような不合理な結果は到底是認し得ない。
これを本件について見るに,本訴が本件不法行為により各自の蒙った損害の全額を明らかにした上そのうち一割に相当する各金額についてのみ権利を行使する旨明示して提起されたものであることは原判示のとおりであるから,右訴の提起による消滅時効中断の効力は右当初訴求の金額の範囲に限って生ずべく,その後請求の拡張により訴訟物となった残額には及ばないものと解すべきところ,原判決がこれを右残額に及ぶものと解し,この理由をもって右残額に関する上告人の時効の抗弁をたやすく排斥し去ったのは,法令の解釈を誤り審理不尽の違法に陥ったものであって,論旨は理由がある。
されば,原判決中請求拡張にかかる残額につき被上告人らの請求を認容した部分を破棄し,なお時効完成の有無につき更に審理を遂げさせるためこれを原審に差戻すべきものとする。
右上告理由第二点ないし第五点について。
論旨は,すべて原審が適法にした証拠の取捨判断,事実の認定を非難するに帰し,上告適法の理由とならない。
されば,原判決中前記破棄すべき部分を除くその余については本件上告を棄却すべきものとする。
民訴第一九八条第二項の裁判を求める申立について。
上告人が右申立の理由として主張する事実関係は,被上告人らの争わないところである。そして,本件原判決の一部が破棄を免れないこと前説示の如くなる以上,原判決に付せられた仮執行宣言がその限度で効力を失うべきこと勿論である。
されば,右仮執行宣言に基き給付した金員を仮執行宣言失効の限度において返還を求めると共にこれに対する給付の翌日から返還済まで民事法定利率たる年五分の割合による損害金の支払を求める上告人の申立は,これを正当として認容すべきである。
よって,民訴四〇七条,三九六条,三八四条,一九八条二項,九五条,八九条,九三条一項本文に従い,主文のとおり判決する。
この判決は,藤田裁判官の少数意見(略)を除き,全裁判官一致の意見である。
最高裁判所裁判長裁判官小谷勝重,裁判官藤田八郎,同河村大助,同奥野健一
消滅時効-取締役の第三者責任(最判昭和49年12月17日民集28巻10号2059頁)
商法266条の3第1項前段所定の第三者の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効には,民法167条が適用になり,民法724条は不適用
上告代理人藤田一良の上告理由について。
商法二六六条の三第一項前段に基づく第三者の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効につき民法724条の適用があるかどうかは,商法二六六条の三第一項前段所定の取締役の責任(以下「取締役の責任」という。)の法的性質,民法724条が短期消滅時効を設けた趣旨等の観点から検討して決すべきものである。
思うに,
(1) 取締役の責任は,法がその責任を加重するため特に認めたものであって,不法行為責任たる性質を有するものではないから(最高裁昭和三九年(オ)第一一七五号同四四年一一月二六日大法廷判決・民集二三巻一一号二一五〇頁),取締役の責任については不法行為責任に関する消滅時効の特則である民法724条は当然に適用されるものではない。
(2) また,民法724条が短期消滅時効を設けた趣旨は,不法行為に基づく法律関係が,通常,未知の当事者間に,予期しない偶然の事故に基づいて発生するものであるため,加害者は,損害賠償の請求を受けるかどうか,如何なる範囲まで賠償義務を負うか等が不明である結果,極めて不安定な立場におかれるので,被害者において損害及び加害者を知りながら相当の期間内に権利行使に出ないときには,損害賠償請求権が時効にかかるものとして加害者を保護することにあると解されるところ,取締役の責任は,通常,第三者と会社との間の法律関係を基礎として生ずるものであって,取締役は,不法行為の加害者がおかれる前記のような不安定な立場に立たされるわけではないから,取締役の責任に民法724条を適用すべき実質的論拠はなく,従って,同条を商法二六六条の三第一項前段に基づく第三者の取締役に対する損害賠償請求権に類推適用する余地もない。
そして,右損害賠償請求権の消滅時効期間については,他に特に定めた規定がないから民法一六七条一項を適用すべきである。これと同趣旨の原審の判断は,正当として是認できる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用できない。
よつて,民訴法四〇一条,九五条,八九条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官坂本吉勝,裁判官関根小郷,同天野武一,同江里口清雄,同高辻正己
消滅時効-損害及び加害の事実を知ったとき(最判平成16年12月24日裁判集民事215号1109頁)
交通事故による後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効が遅くとも症状固定の診断を受けた時から進行するとされた事例
上告代理人芝康司ほかの上告受理申立て理由について
1 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)被上告人は,平成8年10月14日,上告人の過失によって生じた交通事故により,加療約6か月間を要する右膝蓋骨骨折の傷害を負い,右膝痛等の後遺障害(以下「本件後遺障害」という。)が残ったが,平成9年5月22日に症状固定という診断を受けた。
(2)被上告人は,本件後遺障害につき,上告人が加入していたJA共済を通じ,自動車保険料率算定会(以下「自算会」という。)に対し,自動車損害賠償保障法施行令別表第2(以下「後遺障害等級表」という。)所定の後遺障害等級の事前認定を申請したところ,平成9年6月9日,非該当との認定を受けた。
(3)被上告人は,平成11年7月30日,自算会の上記事前認定について異議の申立てをしたところ,自算会より,後遺障害等級表12級12号の認定を受けた。被上告人は,これに対し更に異議の申立てをしたが,退けられた。
(4)被上告人は,平成13年5月2日,上告人に対し,不法行為に基づく損害賠償として,本件後遺障害に基づく逸失利益,慰謝料等の合計2424万8485円及び遅延損害金の支払を求める本件訴訟を提起した。上告人は,これに対し,損害賠償請求権が民法724条所定の3年の時効により消滅した旨の主張をし,消滅時効を援用した。
2 原審は,本件後遺障害が後遺障害等級表12級12号に相当すると認定した上,次のとおり判断して,上告人の消滅時効の抗弁を排斥し,被上告人の請求を764万0060円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容すべきものとした。
被上告人は,後遺障害等級表12級12号の認定を受けるまでは,本件後遺障害に基づく損害賠償請求権を行使することが事実上可能な状況の下にその可能な程度にこれを知っていたということはできないから,被上告人の本件後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点は,上記認定がされた時以降であると解すべきである。
3 しかし,原審の上記判断は是認できない。その理由は,次のとおりである。
(1)民法724条にいう「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」とは,被害者において,加害者に対する賠償請求をすることが事実上可能な状況の下に,それが可能な程度に損害及び加害者を知った時を意味し(最高裁昭和45年(オ)第628号同48年11月16日第二小法廷判決・民集27巻10号1374頁参照),同条にいう被害者が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと解するのが相当である(最高裁平成8年(オ)第2607号同14年1月29日第三小法廷判決・民集56巻1号218頁参照)。
(2)前記の事実関係によれば,被上告人は,本件後遺障害につき,平成9年5月22日に症状固定という診断を受け,これに基づき後遺障害等級の事前認定を申請したというのであるから,被上告人は,遅くとも上記症状固定の診断を受けた時には,本件後遺障害の存在を現実に認識し,加害者に対する賠償請求をすることが事実上可能な状況の下に,それが可能な程度に損害の発生を知ったものというべきである。自算会による等級認定は,自動車損害賠償責任保険の保険金額を算定することを目的とする損害の査定にすぎず,被害者の加害者に対する損害賠償請求権の行使を何ら制約するものではないから,上記事実認定の結果が非該当であり,その後の異議申立てによって等級認定がされたという事情は,上記の結論を左右するものではない。そうすると,被上告人の本件後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効は,遅くとも平成9年5月22日から進行すると解されるから,本件訴訟提起時には,上記損害賠償請求権について3年の消滅時効期間が経過していることが明らかである。
4 以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,上告人による消滅時効の援用が権利の濫用に当たるとの再抗弁について更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻す。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁判所裁判長裁判官滝井繁男,裁判官福田博,同北川弘治,同梶谷玄,同津野修
消滅時効-損害及び加害の事実を知ったとき/名誉毀損新聞(最判平成14年1月29日民集56巻1号218頁 )
民法724条にいう被害者が損害を知った時の意義
上告代理人喜田村洋一の上告理由について
一 本件は,被上告人社団法人共同通信社が被上告人X新聞社に配信し,同被上告人の発行する新聞紙に掲載された記事が上告人の名誉を毀損するものであるとして,上告人が被上告人らに対して不法行為に基づく損害賠償を請求する訴訟である。原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人共同通信社は,地方新聞等全国の報道機関を社員(加盟社)とする社団法人であり,全国的な内容のニュースを加盟社に配信する業務を行う通信社である。
同被上告人から記事の配信を受けた加盟社は,当該記事を自社の発行する新聞紙に掲載するかどうか及びどのような見出しを付するかについては,自ら決定するが,当該記事を掲載する場合には,裏付け取材をすることなく,記事内容に何ら実質的な変更を加えることなく,当該記事が配信された日又はその翌日に発行する新聞紙面にこれを掲載することを常としている。
被上告人X新聞社は,同共同通信社の加盟社であり,日刊紙X新聞を発行している新聞社である。
(2) 被上告人共同通信社は,昭和六〇年九月一二日,同X新聞社に対し,第一審判決別紙二記載の記事(以下「本件配信記事」という。)を配信し,同被上告人は,同月一三日付けのX新聞紙上に,「花子さん殴打事件 甲野,口封じに圧力」,「乙山の身辺に出没」等の見出しを付して,同別紙一記載の記事(以下「本件記事」という。)を掲載した。
(3) 上告人は,平成三年ころ,被上告人共同通信社が配信した本件配信記事とは異なる記事(以下「別件記事」という。)に関する別件損害賠償請求訴訟の過程で同被上告人の加盟社に対する記事配信のシステムを知り,同被上告人の加盟社が発行する全国の新聞紙に別件記事と同内容の記事が掲載されているのではないかと考え,調査会社を使って調査したところ,平成四年初めころまでに,被上告人X新聞社が同共同通信社の加盟社であること及び同X新聞社を含む三〇社以上の加盟社が発行する新聞の紙面に別件記事と同内容の記事が掲載されていたことを知った。
(4) 上告人は,平成三年一二月一六日,株式会社Tタイムズ社が発行する日刊新聞「Tタイムズ」紙の昭和六〇年九月一三日付け紙面に本件記事と同内容の記事が掲載されたことに関し,同社に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。Tタイムズ社は,同記事が被上告人共同通信社から配信を受けた記事に基づくものであることを明らかにして,同被上告人に対して訴訟告知をした。同訴訟告知書は,平成四年七月九日に上告人に送達された。
これによって,上告人は,被上告人共同通信社の加盟社である同X新聞社が発行する新聞紙上にも本件配信記事に基づく記事が掲載されている可能性が高いことを知った。
(5) 被上告人X新聞社は,本件記事掲載当時,掲載記事についての閲覧,謄写サービスを行っていなかったが,閲覧,謄写の申込みに対しては,Z県内の各市町村立図書館等がX新聞のバックナンバーをそろえており,Z県立図書館等が閲覧,謄写サービスを行っているので,これらの施設を利用するよう回答していた。
Z県立図書館では,当時から,掲載紙,掲載年月日,記事内容が特定されれば,申込者に対して,当該記事の写しを郵送するサービスを行っていた。
(6) 上告人は,本件記事掲載時から継続して勾留されていたが,自己に関する新聞報道に強い関心を持ち,拘置所内にいても,知人を通じるなどして強力な情報収集能力を発揮するだけの知識,技能を有している。
(7) 本件訴えが提起されたのは,平成七年七月二五日であるが,被上告人らは,上告人の被上告人らに対する本件名誉毀損に基づく損害賠償請求権について,上告人が本件配信記事の存在を知った同四年七月九日を起算日とする消滅時効を援用した。
二 原審は,次のように判断して,上告人の被上告人らに対する損害賠償請求権は時効により消滅したとし,請求原因について判断することなく,上告人の請求を棄却すべきものとした。
(1) 民法724条にいう「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」とは,被害者において,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程度に損害及び加害者を知った時を意味するものと解するのが相当であり,被害者に現実の認識が欠けていても,その立場,知識,能力などから,わずかな努力によって損害や加害者を容易に認識し得るような状況にある場合には,その段階で,損害及び加害者を知ったものと解するのが短期消滅時効の起算点に関する特則を設けた同条の趣旨にかなう。
(2) 上告人は,拘置所内にあっても,その知識,技能により,自らあるいは支援者たる知人を通じてZ県立図書館に本件記事の写しの郵送を申し入れ,これを人手することが容易であったから,さほどの困難もなく,本件記事の存在及び内容を確知し,損害賠償請求権を行使することが可能な状況にあった。
(3) したがって,上告人は,本件配信記事の存在を知った平成四年七月九日の時点において,被上告人らに対する損害賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程度に損害及び加害者を知ったものと認めるのが相当である。
三 しかし,原審の上記判断は是認できない。その理由は,次のとおりである。
民法724条は,不法行為に基づく法律関係が,未知の当事者間に,予期しない事情に基づいて発生することがあることにかんがみ,被害者による損害賠償請求権の行使を念頭に置いて,消滅時効の起算点に関して特則を設けたのであるから,同条にいう「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」とは,被害者において,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程度にこれらを知った時を意味するものである(最高裁昭和四五年(オ)第六二八号同四八年一一月一六日第二小法廷判決・民集二七巻一〇号一三七四頁参照)。そして,次に述べるところに照らすと,同条にいう被害者が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に了した時をいうと解すべきである。
不法行為の被害者は,損害の発生を現実に認識していない場合がある。特に,本件のような報道による名誉毀損については,被害者がその報道に接することなく,損害の発生をその発生時において現実に認識していないことはしばしば起こり得ることであるといえる。被害者が,損害の発生を現実に認識していない場合には,被害者が加害者に対して損害賠償請求に及ぶことを期待することができないが,このような場合にまで,被害者が損害の発生を容易に認識し得ることを理由に消滅時効の進行を認めることにすると,被害者は,自己に対する不法行為が存在する可能性のあることを知った時点において,自己の権利を消滅させないために,損害の発生の有無を調査せざるを得なくなるが,不法行為によって損害を被った者に対し,このような負担を課することは不当である。他方,損害の発生や加害者を現実に認識していれば,消滅時効の進行を認めても,被害者の権利を不当に侵害することにはならない。
民法724条の短期消滅時効の趣旨は,損害賠償の請求を受けるかどうか,いかなる範囲まで賠償義務を負うか等が不明である結果,極めて不安定な立場に置かれる加害者の法的地位を安定させ,加害者を保護することにあるが(最高裁昭和四九年(オ)第七六八号同年一二月一七日第三小法廷判決・民集二八巻一〇号二〇五九頁参照),それも,飽くまで被害者が不法行為による損害の発生及び加害者を現実に認識しながら三年間も放置していた場合に加害者の法的地位の安定を図ろうとしているものにすぎず,それ以上に加害者を保護しようという趣旨ではない。
これを本件について見ると,上告人は,平成四年七月九日の時点においては,被上告人共同通信社の加盟社である同下野新聞社の発行する新聞紙上に本件配信記事に基づく記事が掲載されている可能性が高いことを知ったにすぎず,本件記事が実際に掲載されたこと,すなわち同被上告人が上告人の名誉を毀損し,不法行為に基づく損害が発生したことを現実に認識していなかったというのであるから,同日をもって消滅時効の起算点とすることはできない。
四 そうすると,上告人の被上告人らに対する損害賠償請求権が時効により消滅したとする原審の判断には,民法724条の解釈適用を誤った違法があり,この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,上告人の被上告人らに対する請求について更に審理判断させるため,本件を原審に差し戻す。よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁裁判長裁判官金谷利廣,裁判官千種秀夫,同奥田昌道,同濱田邦夫
![]() Tel:0564-83-9831 Fax:0564-83-9832
Tel:0564-83-9831 Fax:0564-83-9832![]() フローラ法律事務所 弁護士早川真一
フローラ法律事務所 弁護士早川真一
☆相談のご予約~契約資料等をお持ちください★
※お電話の際,非通知設定には決してなされないで下さい。

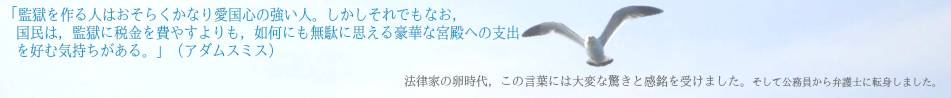
 【裁判例】
【裁判例】
